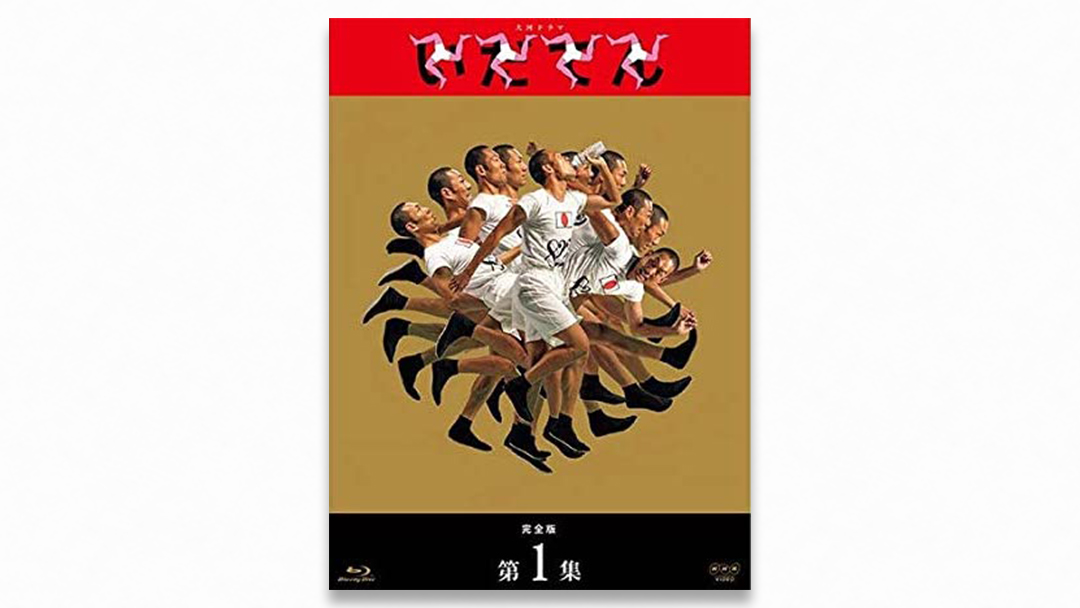
[特別無料公開] 『いだてん』というニッポンの自画像|成馬零一
今朝のメルマガは、いよいよAmazon・書店での一般発売が開始された成馬零一さんの新著『テレビドラマクロニクル 1990→2020』からのピックアップをお届けします。今回は宮藤官九郎脚本の大河ドラマ『いだてん』をめぐる論考の一部を特別無料公開! 『あまちゃん』スタッフと豪華俳優陣で臨んだ本作は、それまで「男の子たちの物語」を描き続けてきた宮藤が「大きな物語」に挑んだ集大成とも言える作品でした。
2019年の『いだてん』
2019年に宮藤が脚本を担当した大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』(NHK)は、日本のテレビドラマ史、サブカルチャー史の金字塔と言える作品である。
主人公は1912年に日本人で初めてオリンピック(ストックホルム五輪)に出場した日本マラソンの父・金栗四三(中村勘九郎)と1964年の東京オリンピック招致に尽力した日本水泳の父・田畑政治(阿部サダヲ)の二人。
物語は1959年の昭和の東京からはじまり、ミュンヘン・IOC総会で、外交評論家でジャーナリストの平沢和重(星野源)がスピーチする場面が描かれる。翌1960年、東京オリンピック開催が64年に決まった東京で、落語家の古今亭志ん生(ビートたけし)がオリンピックについて話(噺)し始めると、時代は明治42(1909)年へと遡っていく……。
物語は
第一部・金栗四三編前半(第1〜13回)明治
第一部・金栗四三編後半(第14〜24回)大正
第二部・田畑政治編前半(第25〜39回)昭和(戦前)
第二部・田畑政治編後半(第40〜47回)昭和(戦後)
という大きく分けて二部構成、細かく分けると四部構成となっており、1940年に開催予定だった幻の東京オリンピックと、戦後復興による高度経済成長を象徴する1964年の東京オリンピック。この二つの東京オリンピックを落語によって対峙させ、そこで翻弄される人々を描くことで、2020年の東京オリンピックへと向かう現在(2019年放送当時)の日本を照らし返す作品となっていた。
制作統括は訓覇圭、音楽は大友良英、チーフ演出は井上剛といった『あまちゃん』チームが再結集。外部ディレクターとしてドラマ『モテキ』や映画『バクマン。』(2015年)で知られる大根仁、VFXスーパーバイザーとして『シン・ゴジラ』などを手がけた尾上克郎も参加。
脇を固める俳優は、役所広司を筆頭に、綾瀬はるか、森山未來、杉咲花、シャーロット・ケイト・フォックス、竹野内豊といった主演級の俳優が揃っており、実に豪華だ。主演の阿部サダヲを筆頭に、松尾スズキ、星野源、皆川猿時、荒川良々といった大人計画の俳優陣はもちろんのこと、峯田和伸、生田斗真、神木隆之介、松坂桃李、勝地涼、橋本愛、安藤サクラ、小泉今日子、薬師丸ひろ子といった宮藤の過去作に登場した俳優たちが多数出演している。そして、志ん生を演じるのが、宮藤が尊敬し、今の仕事を志すきっかけとなったビートたけし。
参加スタッフ、俳優ともに最高の座組であり、まさに総力戦である。
今までのクドカンドラマとしても最大のスケールとなる、プレオリンピック・イヤーにふさわしい大型企画だったが、このような国家規模の歴史劇を書く際に、落語という庶民の「笑い」をぶつけるのが、実にクドカンドラマらしいと言えるだろう。
「富久」と聖火ランナー
宮藤たちが『いだてん』を作ると知った時はドキュメンタリー番組『プロジェクトX〜挑戦者たち〜』(NHK)のオリンピック編とでもいうような、硬派な作品になるのだろうと思われた。
同時に「オリンピックとスポーツ」というモチーフは、アイドルと芸能を通して東日本大震災を描いた『あまちゃん』チームが取り組むにしては、ややミスマッチに思えた。
震災とアイドルの『あまちゃん』から、東京オリンピックとスポーツの『いだてん』という流れは、現代を描くという意味では圧倒的に正しい選択だが、ど真ん中すぎてどこか息苦しく感じ、「何もこのチームでやらなくもていいのではないか」と、当初は思っていた。何より国家規模の物語というのがクドカンらしくない。
しかし、作品の語り手(ナレーション)を担当するのが古今亭志ん生だと知って、俄然興味が湧いてきた。
クドカンドラマは、田舎のスナックのような小さな共同体の中にある狭い人間関係を延々と描くものがほとんどだ。そのため、友達の知り合いの話を聞かされているかのような距離感の心地よい狭さがあるのだが、そこでローカルな家族の歴史や細かいサブカルチャーの引用を用いて〝歴史〞のようなものを紡いできた。
それが顕著に現れていたのが『タイガー&ドラゴン』だろう。本作は落語の演目が物語に絡むという虚実が混濁したドラマだったが、噺家が登場し、ストーリーの根幹に「富久」という落語が導線のように引かれている『いだてん』、『タイガー&ドラゴン』の手法を発展させて、日本の近代史を語る多層的な物語だった。
物語冒頭、タクシーに乗った志ん生は、渋滞の道路を走り抜ける男をサイドミラー越しに目撃する。
男は足袋を履いており、「『富久』の幇間じゃねぇか」と志ん生は笑う。
後に志ん生に弟子入りする五りん(神木隆之介)は、母の遺品の絵葉書に書かれていた「志ん生の富久は絶品」という言葉の真相を知るため志ん生の元を訪問する。
「富久」は、(五代目)志ん生が得意とした演目で、宝くじと火事という東京の名物を題材にした落語だ。
年の暮れに、酒でしくじり職を失った幇間(酒の席で客の機嫌をとり芸を見せて盛り上げる仕事、太鼓持ち)の久蔵が長屋に籠もっていると、大家が一枚の宝くじを買わないかとやってくる。なけなしの一分でくじ札を買った久蔵が札を神棚に供えると、その日の夜に火事となり町中で半鐘が鳴る。大家に言われて、仕事をしくじった久蔵は旦那の元に走る。かと思うと、今度は家にあるくじ札が千両の当たりだと知って急いで家に戻るといった感じで年の瀬の江戸の町を「火事だ、火事だ」と言いながら走り回る。
『いだてん』は、そんな久蔵の姿に、オリンピックの聖火ランナーや金栗四三たち陸上選手の姿と、仏教の神様で足の速い人のたとえとして使われる「いだてん(偉駄天)」を重ねている。
〝走る〞という行為は本作の重要なテーマで、拡大して考えるならば、田畑や嘉納治五郎たち日本人が近代を〝走り抜ける〞物語が『いだてん』だったと言えるだろう。
一方、『あまちゃん』に登場した「潮騒のメモリー」の歌詞にある「その火を飛び越えて」を「その日(=3・11)」と井上剛が連想したことを考えると、富久における火事には、日本に訪れた様々な困難、関東大震災や東京大空襲のイメージが投影されているのかもしれない。東京を焼き尽くした火事の炎を平和の象徴である聖火へと反転させる物語。そのような読みも可能だろう。
クドカンドラマの集大成
『いだてん』は、主演級の俳優が多数出演しているため、全員主役の群像劇を見ているかのようだ。
日本人初のオリンピック参加を目指して大日本体育協会を設立し、ストックホルムオリンピックの参加資金のために奔走する嘉納治五郎(役所広司)の姿は、2017年に役所が主演を務め日曜劇場で放送された池井戸潤原作のドラマ『陸王』(TBS系、2017年)の主人公のようでもあり、金栗四三と美川秀信(勝地涼)が故郷の熊本から旅立ち、東京高等師範学校の寄宿舎で暮らす姿は、夏目漱石の『三四郎』のような青春文学の味わいがある。
一方、裏の主人公と言えるのが、語り部の落語家・古今亭志ん生。森山未來が演じる若き日の志ん生・美濃部孝蔵が落語家の橘家円喬(松尾スズキ)と出会い落語家として成長していく姿が金栗たちの物語と併走する形で描かれるのだが、町のチンピラとして浅草で放蕩生活を送っている孝蔵を取り囲む遊女の小梅(橋本愛)や人力車夫の清さん(峯田和伸)たち下町の人々が、啖呵を切る姿は宮藤の『池袋』を思い出させる。また孝蔵と円喬の、弟子と師匠の関係を軸とした落語家の物語や、落語の演目「富久」が本編と重ねて語られるという虚実入り交じったストーリー展開は、『タイガー&ドラゴン』を思わせる。
そして、スポーツを愛する若者たちの集団・天狗倶楽部のパリピ的な振る舞いは、明治の木更津キャッツアイと言って過言ではあるまい。天狗倶楽部は実際に明治時代に存在したスポーツ同好会だが、彼らの姿を見つけた時、宮藤は歓喜したに違いない。天狗たちのリーダー的存在である三島弥彦(生田斗真)のタメのあるドヤ顔は『木更津』のぶっさんを彷彿とさせる。
また、第1回「夜明け前」(演出:井上剛)で物語の全体像を見せた後、第2〜5回の中で第1回で見せた予選会の裏側を見せるという構成は、『木更津』でみせた入れ子的構成をより大規模な形で描いたものである。
つまり序盤の時点で『池袋』『木更津』『タイガー&ドラゴン』という宮藤の初期代表作のテイストが散見できるのだ。そして、舞台が大正となり金栗が東京府立第二高等女学校の教師となり、女子スポーツが勃興するようになると、『ごめんね青春!』のテイストも盛り込まれるようになる。
全員主人公の群像劇
元々、宮藤は時系列が複雑に錯綜する群集劇を得意とする作家だが、『いだてん』のような膨大な登場人物を全員主人公であるかのように描いていく試みは、複数のヒーローの物語が同時展開されていく「マーベル・シネマティック・ユニバース(以下MCU)」や『スター・ウォーズ』等のハリウッド映画でも見られるメディア展開の手法である。
日本ではEXILEが所属する芸能事務所・LDHが主催するエンターテインメントプロジェクト『HiGH&LOW』シリーズが、全員主役とでもいうような群像劇を展開している。このような大規模群像劇は現代のフィクションにおける一つの最適解だ。
現代のフィクションにおいて群像劇が求められる背景には、大きく分けて二つの理由がある。
まず第一に、インターネットが普及してTwitter等のSNSにおいて可視化されている、複数の人間たちが交差しながら同一時間軸で蠢いているタイムラインの感覚をフィクションで再現しようとした結果だと言えるだろう。これは怪獣映画『シン・ゴジラ』や、中島哲也監督の『告白』や『来る』(2018年)といった映画でも見られる傾向であり、ネット上の過密な情報量を物語の中に落とし込んだ結果、生まれた映像表現である。
テレビドラマでは2018年に放送された野木亜紀子脚本のドラマ『フェイクニュース』(NHK)がSNSの可視化に挑んでいた。本作はSNSを見ている時の酩酊感、膨大な情報の海に酔っ払っているかのような心地良さと不快感が再現された怪作で『MIU404』の終盤でも同じような酩酊感が再現されていた。
第二に、群像劇は現代的なテーマを描くことに適している。
近年のディズニー映画が特に顕著だが、ジェンダーの問題や民族差別といったテーマを内包した作品を作り、ポリティカル・コレクトネスに対応することは、ハリウッド映画を筆頭とする世界市場で流通するフィクションにとって、一番の課題である。
そこで求められることは、唯一無二の正解を示すことではなく、人間には多様な生き方があり、マイノリティ(少数派)の生き方を否定してはいけないというダイバーシティ(多様性)を描くことだ。その上でもっとも重要なことは、様々なタイプのキャラクターが登場することであり、だからこそ群像劇というスタイルが求められる。
『ブレイキング・バッド』(2008〜15年)、『ウォーキング・デッド』(2010年〜)、『ゲーム・オブ・スローンズ』(2011〜19年)といった2010年代にヒットした海外ドラマの多くは壮大な群像劇であり、長編化したストーリーは無数のスピンオフ作品を生み出していく。
同時に求められているのは圧倒的な情報量だ。エンタメとしての(SNSに匹敵する情報量がもたらす)快楽の追求と、多様性を描くというテーマを追求した結果、群像劇というスタイルが世界中で求められている。そう考えると、テレビドラマにおいては異色作に見える『いだてん』の群像劇スタイルは、世界標準で見ればスタンダードだったと言える。
しかし、残念ながら視聴率の面で『いだてん』は最後まで苦戦し、平均視聴率8・2%(関東地区)という歴代大河の中でもっとも低いものとなってしまった。
現在と過去を往復しながら、無数の登場人物が交差する『いだてん』は、今までの大河ドラマ視聴者からは、主人公の印象が弱く、話が複雑でわかりにくいというネガティブな評価が多かった。戦国時代や幕末といった誰もが見知っている時代を舞台に、織田信長や坂本龍馬といった馴染みのキャラクターが出てくる従来の大河ドラマと違い、明治以降のスポーツ関係者という馴染みのない人々を主人公としていることも視聴者を弾く結果となっていた。
過去のクドカンドラマ同様、本作の評価は終始高かった。しかし毎週1話放送という連続ドラマの視聴形態とは相性が悪かった。もしも、Netflixのドラマのように全話と言わないまでも1クールずつ一挙配信していたら、『いだてん』の評価はまた違ったものだったかもしれない。
近代大河はなぜ鬼門なのか?
元々、大河ドラマにおいて明治以降は鬼門であった。1980年代には新基軸として近現代路線を打ち出そうとし、1984年には2・26事件から東京裁判までの昭和史を描いた『山河燃ゆ』、85年には明治から大正を舞台にした『春の波涛』、86年には昭和(終戦から放送当時(昭和60年)の現代まで)を舞台にした『いのち』が作られている。
しかし、『いのち』以外のドラマは視聴率の面で成功したとは言いがたく、もともと五部作だったものが三部作に縮小されるという苦い過去があった。
それ以降、近現代を舞台にした大河ドラマは『いだてん』まで作られていなかったのだが、近代大河の視聴率面での失敗の背景には戦時下(第二次世界大戦)の日本を、戦国時代や幕末を舞台にするような感覚で描くことが、様々な理由で難しいということが挙げられるだろう。
これは朝ドラが、戦前・戦中・戦後を描き続けたことと、パラレルな関係にある。朝ドラが描き続けている戦争が、女性から見た被害者としての戦争の歴史であるのに対して、昭和を舞台に軍人を主人公にして戦争を描くと、アジアを侵略した加害者としての日本人の視点にならざるを得ないため、山本五十六や東条英機を、織田信長や坂本龍馬と同じ感覚で劇中に登場させることはとても困難だ。
それは司馬遼太郎が『坂の上の雲』(文春文庫)以降の歴史を、フィクションとして描けなかった問題ともつながっている。「まことに小さな国が、開化期をむかえようとしている」という言葉で始まる本作は明治維新によって近代国家に生まれ変わった日本が日清戦争、日露戦争に勝利することで欧米列強に肩を並べるまでの姿を描いた歴史小説だ。
主人公は陸軍の司令官となった秋山好古と海軍に入隊し連合艦隊の参謀となる秋山真之。そして俳人の正岡子規の3人。彼ら少年たちの成長物語と近代国家としての日本の成長を重ねて物語は進んでいくのだが、日露戦争の終結をもって、庶民と国家が幸福な形で結びついていた楽天的な時代が終わりを告げることを暗示して物語は幕を閉じる。
本作は司馬の没後、2009〜11年にかけて大河ドラマの枠で断続的に特別番組としてドラマ化されたのだが、司馬は存命中に「作品のスケールをドラマでは描けないことと、戦争賛美と誤解される」という理由から映像化を許可しなかったという。
戦争を通して少年たちが成長するという物語が日露戦争までしか成立しないと司馬が思い、それ以降の時代を小説として描けなかったことは、そのまま大河ドラマが明治以降を描けなかったことと相似形になっていると言えるだろう。
『いだてん』は『坂の上の雲』の結末となる日露戦争以降の時代を舞台にしており、『坂の上の雲』には登場しない、スポーツ選手や落語家といった軍人以外の立場の青年たちが、次々と登場する。『いだてん』は、さながらクドカン版『坂の上の雲』とでも言うような作品で、戦争と軍人ではなく、スポーツとオリンピックを題材にすることで、近代から現代へと連なる男の子たちの物語を紡ぎ出すことに挑んでいた。
チーム男子の相互承認
クドカンドラマが2000年代に衝撃を与えたのは、1980年代後半のトレンディドラマ以降、女性中心の価値観で作られていたテレビドラマの世界に、男の子たちの物語を持ち込んだからだった。
中でも『池袋』『木更津』『タイガー&ドラゴン』は、クドカンらしさがもっとも現れた初期代表作であり、男子校的な男の子たちの明るいノリが持ち込まれた作品だった。
それは後に「チーム男子」や〝マイルドヤンキー〞と呼ばれる感覚の先駆けでもあった。高校を卒業しても地元にとどまり、恋人よりも仲間といる方が楽しいという、小学生男子がそのまま大人になったような、男の子同士のわちゃわちゃ感には独自の健全さがあった。
『新世紀エヴァンゲリオン』の主人公・碇シンジが象徴するように、90年代のフィクションで描かれる男の子たちは、とても鬱屈していた。その原因を過去に辿って考えた時、まずはじめに日本という国家のために戦うという物語が1945年の敗戦によって挫折したことが挙げられるだろう。そして、戦後は軍事ではなく経済大国として勝利するためにエコノミック・アニマルとして会社のために働き、高度経済成長を実現したが、その戦いもまたバブル崩壊によって挫折し、国や会社のために戦う(働く)ことで、承認を得ることが困難となっていった。
だからこそ1980年代はラブコメやトレンディドラマが流行し、男たちは恋人に承認欲求を託し、恋愛で満たされない者たちはフィクションの中に自閉し、虚構の世界を生きるオタクとなった。『エヴァ』にはそんな、国家からも会社組織からも女からも承認されない男たちの困難が、露悪的な形で刻印されていた。1990年代はこのような鬱屈した少年というネガティブな形でしか男の子の物語を描けなかったのだ。
対して宮藤は、異性ではなく男同士で承認し、支え合う〝男の子たちの世界〞を描いた。国や会社組織から放置された少年たちが自分たちだけの世界を作り、そこで自給自足することでポジティブなかたちで男の子を描いたのだ。
もちろん、長瀬智也や岡田准一といったジャニーズアイドルが主演だったため、同世代の男性視聴者に届いていたとは言いがたい。それらの作品は基本的に女性視聴者に向けたアイドルドラマであり、男の子同士のユートピアを描いた作品としてBL的に消費されたという側面は大きいだろう。
しかし、それでもあの時代に、他の作家が避けていた男の子たちの物語を描き続けたからこそ、宮藤は他の追随を許さないドラマ脚本家となりえたのだ。国にも会社にも女にも承認を求めず、男としての自分を男同士で祝福する物語を描ききった宮藤にとって、国家、政治、宗教といった自分たちを律する巨大な価値観は本来不要なものだ。そんな宮藤がオリンピックとスポーツという題材を通して国家や戦争といった巨大な物語と改めて向き合おうとしたのが、『いだてん』という物語だった。
楽しいの? 楽しくないの? オリンピック
ストックホルム五輪に参加する金栗四三も三島弥彦も、お国のためではなく自分のために走っている。「楽しいから走る」「走りたいから走る」という個人的な動機こそが立脚点となっているのは、クドカンドラマならではだと言えるだろう。
そんな金栗たちが、国家間の代理戦争としてのオリンピックに巻き込まれ、競技スポーツによって無垢な魂が失われていくことは第1回で永井道明(杉本哲太)が「勝ち負けにこだわる人間の醜さを、競技スポーツの弊害を私は見ました」と語るロンドンオリンピックで起こった「ドランドの悲劇」によって、すでに暗示されていた。
過去作を見る限り、勝敗を競い「戦いに勝つ」という価値観は、クドカンドラマともっとも相容れない考えだ。
『木更津』で描かれる草野球は仲間同士で楽しむものであり、『あまちゃん』のアキは、東京の芸能界でトップアイドルになることではなく、ローカルアイドルとして地元で仲間たちと共に生きることを選択する。クドカンドラマにおいて大事なのは「勝つか負けるか」ではなく、嘉納治五郎が言うように「楽しいか楽しくないか」なのだ。
しかし、こういった「楽しい/楽しくない」という個人の美学を貫けるのは、彼らが国家のもたらす政治的空間から放置されてきたからである。国や会社、あるいは女性からの承認が得られなくなったことを、男の子の困難と書いたが、それは自由の裏返しだったとも言えるだろう。
『木更津』の背景にあったのは、バブル崩壊以降のデフレ不況で就職できなかったが、ニートやマイルドヤンキーが許容されるくらいには経済的文化的に豊かな社会環境であり、だからこそ宙ぶらりんでいられるモラトリアム空間が成立した。
そんな2000年代に対し、東日本大震災を経た日本には、人々が国や政治について真剣に考えないと生き残れないという切迫感が日々増している。
だからこそ宮藤は『11人もいる!』と『あまちゃん』で震災に直面した日本という政治的背景を描かねばならなかったし、その後の『ゆとり』や『監獄』でも、社会派テイストが強まっている。これは宮藤が年を重ねて、社会に対する視野が広がったということもあるが、何より時代の変化が大きい。だからこそ宮藤は一度、過去に遡り、国や政治的空間と対峙せざるを得ない人々を描いたのだ。
同じ目的に挑む同志
宮藤がテレビドラマの中で描いてきたのは、歴史に名を残すような偉人ではなく、無名の人々。もっと言うと地元でくすぶっている負け犬たちの物語だ。
スタジアムで観客から喝采を浴びるスポーツ選手や、オリンピック誘致に尽力した政治家や官僚たちの姿はクドカンドラマの住人たちとうまく結びつかず、どうしてオリンピックなのか? と最初は疑問だった。しかし、放送が始まると、「なるほど、宮藤が描きたいことはこういうことだったのか」と理解できるようになった。
物語は東京オリンピック開催に沸き立つ昭和から始まり、明治末へと遡る。
世界でも知られる柔道の創始者で「日本スポーツの父」と言われた嘉納治五郎は、日本人初のオリンピック出場選手を決めるために奔走していた。嘉納は五輪に出場する選手を決める選考会を開催、マラソンで世界新記録を出した〝いだてん〞の金栗と三島財閥の御曹司で〝痛快男子〞と呼ばれた天狗倶楽部の三島弥彦が選ばれ、五輪に出場するためストックホルムへと向かう。しかし世界の壁は厚く、短距離で参加した三島は予選敗退。そして金栗もレース中に熱中症となり、途中退場する。
苦い敗北を味わう二人。だが、それ以上にショックだったのは、金栗が心を通わせたポルトガルの選手・ラザロ(エドワード・ブレダ)がレース中に命を落としたことだ。国を背負う選手たちを精神的に追い込み、時に命すら落とさせてしまう競技スポーツの負の側面から本作は目を逸らさない。
しかし、だからといって単純なスポーツ批判、オリンピック批判にも向かわない。
コーチの大森兵蔵(竹野内豊)は三島に対して「一緒に走る選手のことはライバルではなく、タイムという同じ敵に立ち向かう同志と思いたまえ」と言う。
ラザロの死に心を痛める選手たちが、墓標の前で祈る場面には深い哀しみが満ちていた。だが同時に、同志としての一体感も伝わってくる。そこには、国や文化を超えて平和を願うというオリンピックの精神が確かに体現されていた。
タイムをオリンピックに置き換えれば、金栗にとって、三島も大森も嘉納治五郎も、旅費を捻出してくれた兄の金栗実次(中村獅童)も同じ目的に挑む同志なのだ。
つまり、すべてのキャラクターは、同じ時代を生きる対等な同志と言える。それは宮藤が過去作で描いてきた精神そのものだった。
タスキを渡していく駅伝ドラマ
第14回「新世界」(演出:井上剛、大根仁)から時代は大正となり、帰国した金栗は、4年後のベルリンオリンピックに出場するために鍛錬に励む。やがて金栗に続くように新しいスポーツに励む者が登場し、女子スポーツが勃興。金栗は箱根駅伝の開催に尽力したことでも知られているのだが、まるでタスキを渡すように金栗の意志は後続の若者たちへと引き継がれていく。
一方、孝蔵は橘家円喬と出会い落語を教わることで落語家・古今亭志ん生へと成長していく。円喬を演じた松尾スズキは宮藤の所属する劇団大人計画の主宰で、宮藤にとって師匠と言える存在だ。(1)
そして志ん生を演じるビートたけしは、宮藤が芸能の仕事を志すきっかけとなった尊敬する芸人だ。二人の師匠が重要な役割を果たす志ん生の物語には、宮藤にとって自伝的な側面が強い。物語は駅伝のように、金栗と村田富江(黒島結菜)たち女学校の生徒、金栗や三島の影響でスポーツの面白さに目覚めたシマ(杉咲花)と人見絹枝(菅原小春)、そして円喬と志ん生の師弟関係といった世代間のタスキの受け渡しが繰り返し描かれている。
関東大震災
第23回「大地」では、大正12年に起きた関東大震災が描かれる。演出は井上剛。『その街のこども』『あまちゃん』『LLS』とこれまで3回、震災を描いてきた井上だが、それまでの作品が、どちらかというと間接的な見せ方だったのに対して、今回の『いだてん』では真正面から描いている。
『いだてん』は過去の風景を実に緻密に再現している。特に浅草の町並みはとても丁寧に描かれており、資料を元に忠実に再現しているのだが、リアルすぎて幻想的に見えるというパラドキシカルな映像となっていた。
揺れがおさまると金栗は、みんなの安否を知るために東京の街を走る。街は火事で真っ赤に染まっている。一方、孝蔵は、地震が起きるやいなや、妊娠中の妻・おりん(夏帆)をほっぽりだして外に出る。地震で東京中の酒がこぼれて地面に吸われてしまうと思った孝蔵は近くの酒屋に入ると、四斗樽の栓を抜いて酒を飲み干す。地面が揺れてるのか酔っ払っているのかわからない孝蔵が家に戻ると、おりんは激怒し夫婦喧嘩。落語の演目「厩火事」と重ねてひと笑い入れた後、孝蔵は火の海となった東京について語り続ける。
瓦礫の街となった浅草で金栗は、「止まれ!」と自警団に呼び止められ、「日本人じゃないな!」と言われる。金栗の熊本訛りから日本人じゃないと誤解されるギャグだが、日本人かどうかというやりとりが延々と続く場面は、震災の時に起きた朝鮮人虐殺事件を知っていると背筋が寒くなる。村田富江の父・大作(板尾創路)は、この災害のどさくさで根拠のない流言飛語が出回り、「大きな余震が来る」「監獄から囚人が逃げた」「井戸に毒薬が撒かれている」といったデマが流れていると語るのだが、ここで「朝鮮人」という単語を出すか出さないかで、ギリギリのせめぎあいが作り手の間にあったのではないかと思う。
村田富江と再会した金栗は凌雲閣の方に目を向ける。そこで「浅草のシンボル、凌雲閣が8階んとこでぶった切られ、残った部分も火事で焼けちまってた」と瓦礫の中で語る孝蔵の姿が挟み込まれる。
劇中には当時のモノクロ映像が挟み込まれる。その映像が孝蔵の身体や足元に映し出される中、地震の様子が孝蔵の独白によって語られる場面はとても演劇的だ。
オリンピックの場面でも、当時のドキュメンタリー映像と役者の演技が合成された映像がたびたび登場するのだが、こういった映像は、映画ともドキュメンタリーとも言えない不思議な手触りを見ている側に与える。潤沢な予算をかけてスケールの大きな群衆シーンを撮る一方で、個人の内面に入っていくようなパーソナルな映像が挟み込まれるのも『いだてん』の特徴だが、こういった様々なレイヤーの映像が混濁しているシーンは、その場にカメラを構えた画というよりは、人の脳の中にある記憶を追体験しているような気持ちにさせられる。
時代が現在(1961年)に戻り、寄席から家に戻ってきて酒を飲む志ん生は「やっぱり力ぁ入っちまうな、地震の話は、40年経つが、どう頑張っても笑いにもっていけねえ」と言う。当初は語り部に見えた志ん生だが、このあたりからオリンピックを通した近代史をいかに「笑える」噺に持っていくかという志ん生自身の戦いという側面が際立っていく。
志ん生の葛藤は、「『震災』や『オリンピック』の物語を〝笑い〞にできるか?」という宮藤たちの葛藤でもあった。
復興運動会
続く、第24回「種まく人」(演出:一木正恵)は『あまちゃん』終盤を思わせる震災復興の物語だ。
震災で家を失い、心身ともに疲弊した東京の人々のため、嘉納治五郎は、建設中の明治神宮外苑競技場の中に「外苑バラック」を建設。6400人を収容する自治区が競技場の中に生まれる。のちに(旧)国立競技場となる神宮外苑は『いだてん』を象徴する土地だ。震災の時には避難自治区となり、戦争の際には若い兵隊たちを送り出す学徒出陣のセレモニーの場所となり、1964年の東京オリンピック開催の時には戦後復興の象徴となり、その時代時代を象徴する存在へと姿を変えていく。
金栗は一度熊本に戻ったが、不安を煽るような震災の記事を見ているうちに居ても立ってもいられなくなり、みんなが集めてくれた救援物資を持って上京。弟子たちと手分けして食べ物を配りながら走る。リュックを背負って東京中を走る姿はまさに偉駄天で、同行した妻のスヤ(綾瀬はるか)は、いだてん夫人と呼ばれている。
一方、孝蔵は気がついたら寄席に向かっていた。閉じていると思った寄席は営業しており、大入り満員。観客は娯楽に飢えており、不謹慎な震災ネタも面白いようにウケた。
そして、嘉納治五郎は金栗の提案で、神宮外苑で復興運動会を開こうとする。しかし、自治会長の清さんは迷惑そうな態度をとる。バラックの衛生状態は決して良いとは言えず、ストレスはピークとなっていた。「参加できねぇヤツぁどうすんだよ、怪我人だって大勢いる、動けないヤツは放ったらかしか」という台詞には、五輪開催を目指す嘉納治五郎たち政府関係者と市井の人々との感覚のズレを感じる。しかし(地震で行方不明となっている)シマの耳に届いたら、駆けつけるかもしれないという夫の増野(柄本佑)の言葉が後押しとなって復興運動会は開催される。
復興運動会の様子は実に楽しく、人々が明るく振る舞う姿は観ている側に勇気を与える。『あまちゃん』ならば、クライマックスとなる場面だろう。
しかし物語は折り返し地点であり、ここから戦時下へと向かっていくことを私たちは知っている。行方不明のシマは結局見つからないまま、物語は第一部を終える。
日本の象徴としての田畑
第25回「時代が変る」(演出:井上剛)より、主人公は金栗四三から政治記者の田畑政治へとバトンタッチ。大正から昭和に時代が変わると、牧歌的だった日本スポーツの黎明期は終わりを告げ、生臭い爛熟期へと変わっていく。
「喋りのいだてん」と呼ばれる田畑に主軸が移ると物語は様変わり。嘉納治五郎たちがあれだけ苦労した渡航費の工面も、田畑は大蔵大臣の高橋是清(萩原健一)に直談判し、あっさりと予算をぶんどってしまう。口の悪い田畑の振る舞いは、ともすれば今まで積み上げてきた金栗たちの物語を全否定するものになりかねない危うさだが、そうならないのは多種多様な人々の生き様を描いてきた『いだてん』ならではだろう。むしろ、田畑のせわしない視点がかぶさることで、物語に明確な柱が立ったように思う。
田畑を演じるのは大人計画の看板俳優・阿部サダヲ。『池袋』では風俗が大好きなお巡りさん・浜口。『木更津』ではヤクザとつながりのある草野球チームのコーチ・猫田という胡散臭い男を演じていた。奇妙な動きをしながら機関銃のようにまくし立てる阿部の芝居には、独自のグルーヴ感と愛嬌があるが、同時にちょっと不愉快な圧みたいなものがあった。
それが一番出ているのが『木更津』の猫田だ。ぶっさんたちの先輩で野球部のコーチである猫田は、上下関係を重んじ、上には媚びへつらい、下には高圧的な態度を取ろうとする。宮藤は磯山晶との対談の中で、『木更津』で描かれた「男子校のノリ」や地元の上下関係ですべてが決まってしまう世界観について「僕にとっては、本当につらい関係性ですからね」(2)と語り、『木更津』は悪意からスタートしていると語っているが、その悪意がもっとも強く現れていたのが猫田だ。
磯山は対談の中で「大の大人が朝5時に起きて草野球をするなんて信じられない。なぜ阿部さんは毎週やってるのだろう?」と宮藤がよく言っていたと語っている。(3)
こういった話を読んでいると、田畑が猫田と重なって見えてくる。阿部は小中高と野球部だったそうで、おそらく宮藤にとって阿部はそういった体育会系のノリを体現する存在なのだろう。
出世作となった『マルモのおきて』(フジテレビ系、2011年)を筆頭に、阿部が演じる役は必ずしも嫌な奴ばかりではない。むしろ、近年では繊細で優しい青年役の方が多いのだが、同じ劇団の宮藤が書く阿部のキャラクターに猫田的な存在が多くなるのは、宮藤が阿部をそう見ているからだ。
(つづく)
(1)松尾スズキは脚本を読んで「円喬と孝蔵の関係を、僕と宮藤君自身の関係に重ねていると感じました」と語っている。『NHK大河ドラマ・ガイド いだてん 前編』(NHK出版)「出演者紹介&インタビュー 橘家円喬 松尾スズキ」
(2)(3)宮藤官九郎『木更津キャッツアイ ワールドシリーズ』(角川書店)「今だから話せるあとがき対談 磯山 晶×宮藤官九郎」
▼プロフィール
成馬零一(なりま・れいいち)
1976年生まれ、ライター、ドラマ評論家。テレビドラマ評論を中心に、漫画、アニメ、映画、アイドルなどについて、リアルサウンド等で幅広く執筆。単著に『TVドラマは、ジャニーズものだけ見ろ!』(宝島社新書)、『キャラクタードラマの誕生 テレビドラマを更新する6人の脚本家』(河出書房新社)、『テレビドラマクロニクル 1990→2020』(PLANETS)がある。
【この続きは本書にて。公式オンラインストアにて限定特典附録付き発売中!】
成馬零一さん最新刊『テレビドラマクロニクル 1990→2020』が、2021年4月23日より全国書店等で発売中です。バブルの夢に浮かれた1990年からコロナ禍に揺れる2020年まで、480ページの大ボリュームで贈る、現代テレビドラマ批評の決定版!
[カバーモデル:のん]
さらにPLANETSの公式オンラインストアでご購入いただくと、本書に収録できなかった現在進行形のドラマ史の最新展開をさらに9万字超のテキストで補完する特別電子書籍『テレビドラマクロニクル 2020→2021:コロナ禍の進行はテレビドラマをどう変えたか』をプレゼント! 詳しくはこちらから。
![[特別無料公開] 『いだてん』というニッポンの自画像|成馬零一](http://wakusei2nd.com/wp-content/uploads/2021/04/1080×608_idaten.jpg)
![[特別無料公開]初期クドカンの集大成としての『タイガー&ドラゴン』|成馬零一](http://wakusei2nd.com/wp-content/uploads/2021/03/書影(白)-1.jpg)
![[特別無料公開]『テレビドラマクロニクル 1990→2020』はじめに|成馬零一](http://wakusei2nd.com/wp-content/uploads/2021/03/書影(白)-1.jpg)
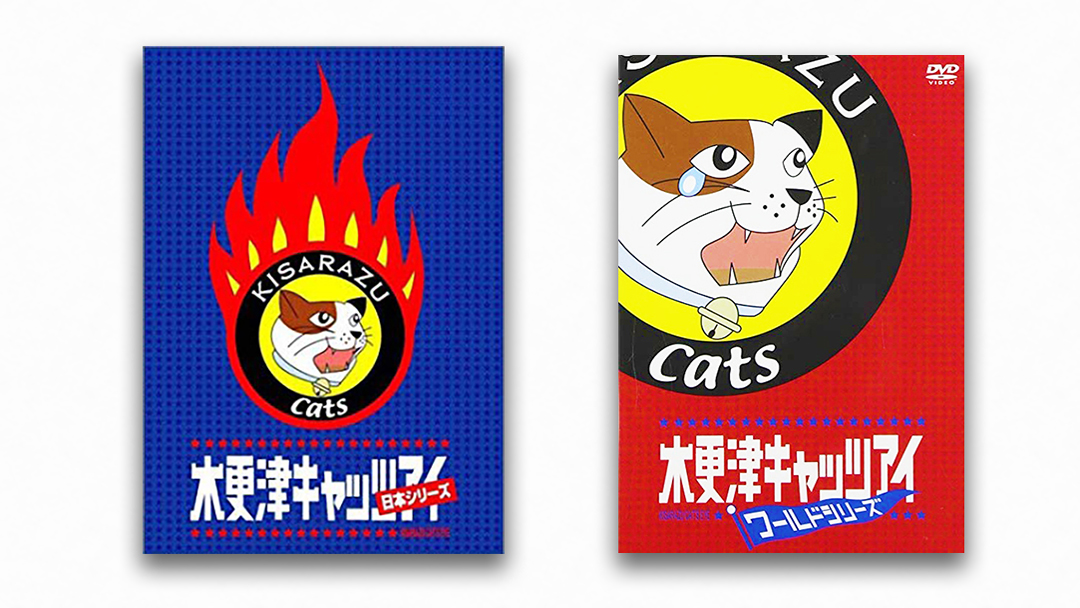
2000年代の宮藤官九郎(1)──『木更津キャッツアイ』が成し遂げたドラマ史の転換(後編)テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉

2000年代の宮藤官九郎(1)──『木更津キャッツアイ』が成し遂げたドラマ史の転換(前編)テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉

堤幸彦とキャラクタードラマの美学(5)──時代への抗いとしての『SPEC』(前編) 成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉

堤幸彦とキャラクタードラマの美学(3)──『池袋ウエストゲートパーク』が始動した2000年代(後編)成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉

堤幸彦とキャラクタードラマの美学(3)──『池袋ウエストゲートパーク』が始動した2000年代(前編)成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉
.jpg)
堤幸彦とキャラクタードラマの美学(2)──メタミステリーとしての『ケイゾク』(後編) 成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉

堤幸彦とキャラクタードラマの美学(2)──メタミステリーとしての『ケイゾク』(前編) 成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉












