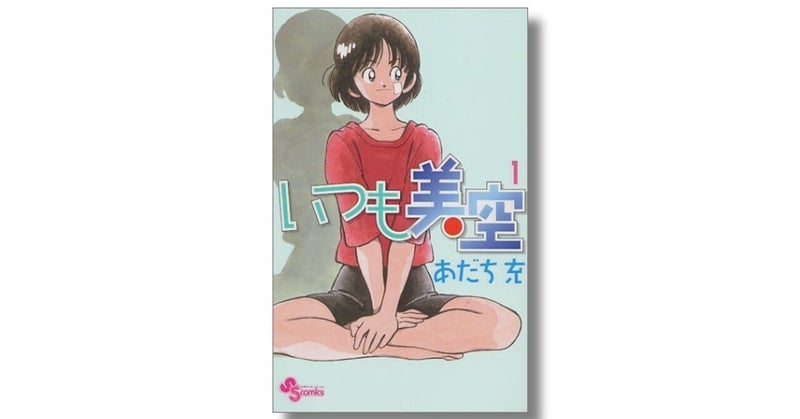空虚な中心をめぐる物語としての『KATSU!』| 碇本学
ライターの碇本学さんが、あだち充を通じて戦後日本の〈成熟〉の問題を掘り下げる連載「ユートピアの終焉──あだち充と戦後日本の青春」。
21世紀初頭に連載されたボクシング漫画『KATSU!』をめぐる分析の最終回です。主人公の亡き父・赤松隆介が物語における「空虚な中心」となった本作の成否を、現在公開中の映画『ドライブ・マイ・カー』など同型の構造をもつ作品群と対比しながら考察します。
碇本学 ユートピアの終焉──あだち充と戦後日本社会の青春
第19回 ③ 空虚な中心をめぐる物語としての『KATSU!』
映画『ドライブ・マイ・カー』に通じる物語構造
今回は『KATSU!』に通じる現在公開中の映画『ドライブ・マイ・カー』の話から始めてみたい。なぜならば、映画『ドライブ・マイ・カー』の物語の構造が『KATSU!』と近いものがあるからだ。
『KATSU!』はあだち充の兄の勉が亡くなるなどの外的な要因も含めて、プロ編に突入することはせずに物語を途中で切り上げて、新しく編集者となった市原武法と共に次作『クロスゲーム』を始めることになった。
映画『ドライブ・マイ・カー』のような方法論が取れていれば、『KATSU!』はあだち充がフリージャズ的な手法で無意識で描いてしまっていた物語の主軸がもっと活きていたのではないかとも思える。今回は両作品に通じるものはなにかについて論じてみたい。
映画『ドライブ・マイ・カー』は村上春樹の短編集『女のいない男たち』に収録された「ドライブ・マイ・カー」を『ハッピーアワー』や『寝ても覚めても』で知られる濱口竜介監督が映像化したもので、2021年開催の第71回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品され、同映画祭の脚本賞、国際映画批評家連盟賞、エキュメニカル審査員賞、AFCAE賞を受賞した。
短編小説「ドライブ・マイ・カー」は原稿用紙70枚ほどの長さであるが、映画版では『ドライブ・マイ・カー』だけではなく、『女のいない男たち』に収録されている短編小説「シェエラザード」「木野」もモチーフとして使われている。また、演劇作品『ゴドーを待ちながら』や『ワーニャ伯父さん』も劇中劇として取り入れられたものとなっており、上映時間はほぼ3時間と長尺なものとなっている。
舞台俳優であり演出家の家福は、愛する妻の音と満ち足りた日々を送っていた。しかし、音は秘密を残して突然この世からいなくなってしまう──。2年後、広島での演劇祭に愛車で向かった家福は、ある過去をもつ寡黙な専属ドライバーのみさきと出会う。さらに、かつて音から紹介された俳優・高槻の姿をオーディションで見つけるが…。
喪失感と“打ち明けられることのなかった秘密”に苛まれてきた家福。みさきと過ごし、お互いの過去を明かすなかで、家福はそれまで目を背けてきたあることに気づかされていく。最愛の妻を失った男が葛藤の果てに辿りつく先とは──。〔参考文献2〕
上記が簡単な作品の流れである。
家福の妻の音が死ぬまでが物語の冒頭パートのようになっており、その2年後、家福が演劇祭で上演される『ワーニャ伯父さん』の演出をするために広島に滞在することになる。そこで演劇祭の事務局が選んだ専属ドライバーとなるみさきと出会う。そこから物語の本編が始まるという構成になっている。
冒頭パートにあたる妻の音が生きている頃に主人公の家福が『ゴドーを待ちながら』の舞台に出演している場面がある。その舞台終わりの家福の楽屋を音が訪ねてきて、紹介するのが物語のキーマンであり、家福とは対照的な俳優の高槻だった。ここで音を中心にして家福と高槻というふたりの男が出会うことになり、2年後の広島の演劇祭に繋がっていく。
高槻は出演者オーディションに合格し、ワーニャ伯父さん役を家福から指名されることになる。ふたりは稽古の後に何度かバーで一緒に飲むことになるが、高槻はその場にいた一般人がスマホのカメラのシャッター音を鳴らすと、芸能人である自分たちを盗撮したと思って凄むという行動を取ってしまう危なさがあった。その凶暴さやキレる早さに家福は付き合っていれないと思って、当初は深くは関わらないようにしていたが、彼は本番前に大きな事件を起こしてしまう。高槻は音が生きていた時に性的な関係を持っていたであろう人物であり、彼にとって音はある種のメンターであったような発言をしている。そのメンターを失った彼はその夫であった家福に近づいてきたようにも見えるのだ。家福と高槻は同じ女性を愛したが、同時に彼女を失ってしまい、バランスが取れなくなった男性として描かれている。
演劇『ゴドーを待ちながら』はアイルランド生まれのフランスの劇作家であるサミュエル・ベケットが1952年に発表した2編からなる戯曲であり、1953年のパリのバビロン座で初演された。賛否両論を巻き起こしながらも前衛劇として異例の成功を収めた。
存在しているのかいないのか、来るのか来ないのか分からない「ゴドー」という人物をずっと待ち続けるという内容であり、不条理演劇の元祖ともいわれる。
今作では『ゴドーを待ちながら』と『ワーニャ伯父さん』が劇中劇として取り入れられているが、前者は原作小説には登場しておらず、後者は原作小説にタイトルのみだが登場している。
濱口監督が前作『寝ても覚めても』でチェーホフの『三人姉妹』を使っていたこともあり、原作に『ワーニャ伯父さん』の文字を見つけ、テキストの強度に圧倒されて、ワーニャと家福がシンクロし始めるような事態が監督の中で起きたという。そのため、『ワーニャ伯父さん』はもうひとつの原作と言っていいほどの存在感を映画の中で発揮している。
では、『ゴドーを待ちながら』はなぜ使用されたのかという疑問に関しては、共同脚本を書いた大江崇允に関係があったようだ。
大江はもともと演劇をやっていたこともあり、主に前半部の監督補として、演劇部分のリアリティをチェックしていた。そして、大江が一番好きな演劇が『ゴドーを待ちながら』だと聞いた濱口監督が作中に取り入れるかたちとなった。
冒頭パートでわずかにしか登場しないこの『ゴドーを待ちながら』は、この『ドライブ・マイ・カー』のテーマのひとつを正確に現している。つまり、いるのかいないのか、来るのか来ないのかわからない「ゴドー」という中心をめぐる物語は、そのまま妻の音という中心を欠いた家福の物語を暗喩している。
大江が好きだという理由だけではなく、この中心を欠くという部分に濱口監督はワーニャと家福を重ねたように、『ゴドーを待ちながら』に登場する浮浪者のウラミディールとエストロゴンと家福を重ねたのではないだろうか。
noteで読む >>