
成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010) 堤幸彦(6)『池袋ウエストゲートパーク』後編ーー堤、クドカン、窪塚洋介。それぞれのIWGP
ドラマ評論家の成馬零一さんが、90年代から00年代のテレビドラマを論じる『テレビドラマクロニクル(1995→2010)』。今回は『池袋ウエストゲートパーク』論の後編です。ドラマ版と原作小説を比較しながら、作品に関わった3人のクリエイター、石田衣良と堤幸彦と宮藤官九郎の影響を検討。さらに本作以降、窪塚洋介が背負うことになった時代性について考察します。
石田衣良からみた『IWGP』
次に原作小説とドラマのストーリーの違いについて考察したい。
石田衣良はシナリオ版『池袋ウエストゲートパーク』(角川書店)の解説で、小説とドラマの違いについてこう書いている。
メディアが違うから、原作(寒色系シリアス)とドラマ(暖色系コメディ)のトーンは違うけれど、両者は最も大切な部分で共通していたとぼくは思う。
それは圧倒的なスピード感とキャラクターの立体感だ(もうひとついうなら池袋という現実の街のライブ感)。ぼくも作家なので、文体にはかなり気をつかう。IWGPでなにを一番大切にしているかというと、人物の描写と文章のスピード感なのだ。
それを宮藤さんは即興性豊かな組み立てと特異なコメディセンス(その場の思いつきともいう、だがなんと切れ味のいい思いつきか)でしっかりと再現してしまった。(「風を切ってフルスイング 石田衣良」:『宮藤官九郎脚本 池袋ウエストゲートパーク』著:宮藤官九郎・角川書店より)
石田はドラマ化に際して「小説とテレビではメディアが違います。原作に気兼ねなどしなくていいから、とにかく思い切りフルスイングしてください。そしたら空振りだって納得できますから」(同書)と磯山に伝えたそうだが、ドラマ版『池袋』と小説を比べると、物語の流れは大筋では同じだが、細部が微妙な変更が施されており、その改変の仕方が見事だというのが当時の印象だった。
のちに数々のオリジナルドラマを手がけることになる宮藤だが、本作は原作モノだったこともあり、作家性に関してはまだ未知数だったが、まずは優秀なアレンジャーとして、その才能は大きく印象づけたと言えよう。
「ダサさ」をまとうことで見えてくるもの
原作の改変ポイントは多数あるが、中でも大きく変わったのは主人公のマコトの造形だろう。小説はマコトの一人称で進むハードボイルド小説の構造となっている。台詞もカッコよくてクールだ。
それをドラマ版では工業高校上がりの馬鹿なヤンキーで素人童貞という側面を強く打ち出している。
原作小説の第一巻が発売されたのは1998年、ドラマ化されたのは2年後だが、最先端の都市の風俗(ストリートカルチャー)というものは、活字になった時点でどんどん古びてしまう。 小説の『池袋』もその側面は強く、情報の鮮度という意味ではドラマ版は圧倒的に不利である。また、小説では成立したカッコいい語りも生身の人間が喋ったら台無しになることも多い。仮に小説をそのまま映像化していたら目も当てられない作品となっていただろう。
だが、宮藤の脚本はカッコよく書かれていた石田衣良の世界を少し斜めから見て、あえてかっこ悪く――宮藤がドラマ内で用いる言葉で言うなら「ダサく」――することで、物語を読み替えて言った。
それはそのまま、トレンディドラマで描かれていたような匿名性の高いおしゃれな街としての東京ではなく、地元(ジモト)としての池袋という、具体的な土地の持つ固有性を打ち出していくという作業だった。
宮藤の脚本は脚本の構成はごちゃごちゃしているが、一つ一つが具体的だ。会話の中には固有名詞がたくさん登場し、その延長で、実在するテレビ番組や芸能人が登場する。
権利関係の処理の問題もあってか、実在する商品名や固有名詞を出すことをためらうドラマは今も少なくないが、固有名詞が具体的であればあるほど、そこに描かれている人間たちの実在感は増していく。すべてのものに固有の名前があり、ワイドショーや雑誌で語られる記号としての東京や女子高生やカラーギャングではなく、くだもの屋のマコトや風呂屋のタカシといった、固有名を取り戻すことで、流行り廃りの激しい風俗の根底にある地に足の付いた感覚を取り戻したことこそが、テレビドラマにおける宮藤の最大の功績だろう。
それは人間関係の描き方にも現れている。特に画期的だったのはマコトの母親・リツコ(森下愛子)の描き方だ。
原作小説では、ほとんど描写されてないリツコのディテールはコミカルではあるが、シングルマザーながらにマコトを育ててきた母親としての優しさやたくましさが描かれていた。
のちに織田裕二主演の連続ドラマ『ロケット・ボーイ』(フジテレビ系)の脚本を宮藤に依頼するプロデューサーの高井一郎は『池袋』の脚本について「よく見ると普遍的な親子愛や友情が隠れて描かれていますよね」(「特集・宮藤官九郎」『クイックジャパンvol.35(太田出版)』より)と語っている。
小ネタで彩られたサブカルドラマとして語られがちな宮藤の作風の奥底にある本質を高井は早くから見抜いていた。
それは一言で言えば家族も含めた共同体(仲間)に対する信頼である。
80年代のトレンディドラマ以降、テレビドラマで家族が描かれる機会は年々減っていた。橋田壽賀子・脚本の『渡る世間は鬼ばかり』(TBS系)を例外とすれば、家庭内暴力や不倫といったネガティブな形でしか家族は描かれなくなっていた。
『未成年』(TBS系)等の野島伸司のドラマは、その反動もあってか、家族再生を試みるのだが、そこで描かれたのは血の繋がらない中間共同体的なもの、『池袋』で言うとGボーイズ的な共同体だった。そういった共同体は反社会的な性質を帯びて、やがては暴走して崩壊する。それは学生運動末期の連合赤軍事件やオウム真理教の地下鉄サリン事件などに連なる、日本の疑似家族共同体の失敗の歴史の反復とも言えよう。
対して宮藤が面白いのは、一方で疑似家族的な仲間のつながりを描きながら、対立軸として血縁関係にある親子を描かないところだ。むしろ、親子も友達のように付き合ってしまうことで、今まで重々しいものだった家族という概念自体を軽いものとして扱っていたのである。
原作小説とドラマ版の大きな違い
noteで読む >>
![[特別無料公開] 『いだてん』というニッポンの自画像|成馬零一](http://wakusei2nd.com/wp-content/uploads/2021/04/1080×608_idaten.jpg)
![[特別無料公開]初期クドカンの集大成としての『タイガー&ドラゴン』|成馬零一](http://wakusei2nd.com/wp-content/uploads/2021/03/書影(白)-1.jpg)
![[特別無料公開]『テレビドラマクロニクル 1990→2020』はじめに|成馬零一](http://wakusei2nd.com/wp-content/uploads/2021/03/書影(白)-1.jpg)
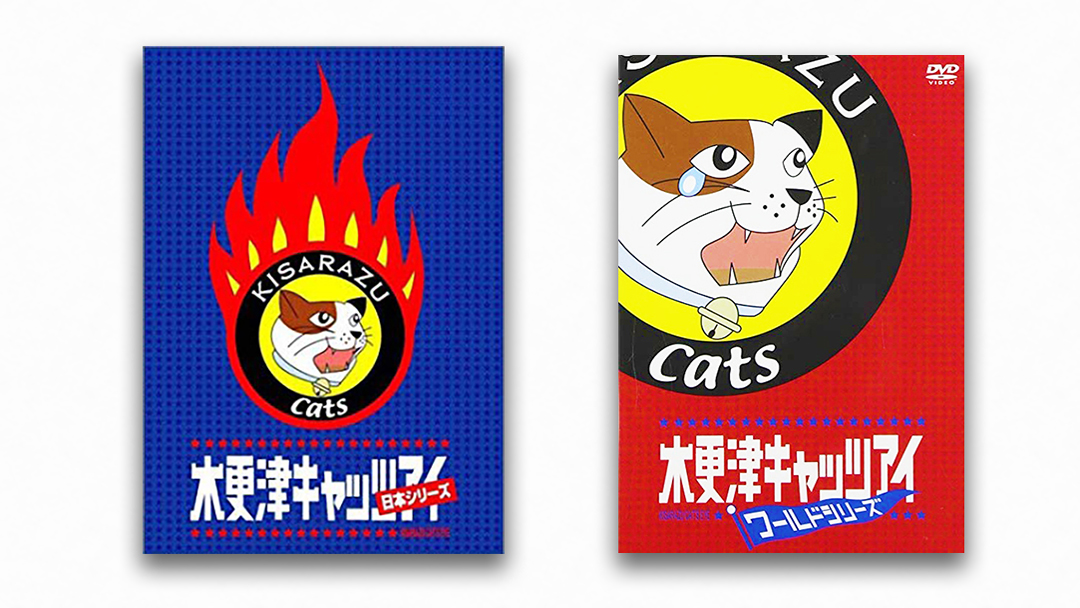
2000年代の宮藤官九郎(1)──『木更津キャッツアイ』が成し遂げたドラマ史の転換(後編)テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉

2000年代の宮藤官九郎(1)──『木更津キャッツアイ』が成し遂げたドラマ史の転換(前編)テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉

堤幸彦とキャラクタードラマの美学(5)──時代への抗いとしての『SPEC』(前編) 成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉

堤幸彦とキャラクタードラマの美学(3)──『池袋ウエストゲートパーク』が始動した2000年代(後編)成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉

堤幸彦とキャラクタードラマの美学(3)──『池袋ウエストゲートパーク』が始動した2000年代(前編)成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉
.jpg)
堤幸彦とキャラクタードラマの美学(2)──メタミステリーとしての『ケイゾク』(後編) 成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉

堤幸彦とキャラクタードラマの美学(2)──メタミステリーとしての『ケイゾク』(前編) 成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010)〈リニューアル配信〉











