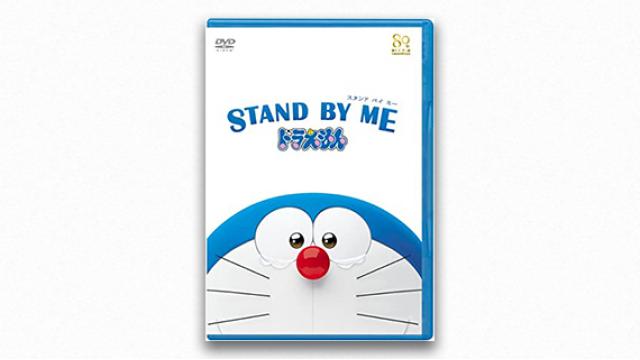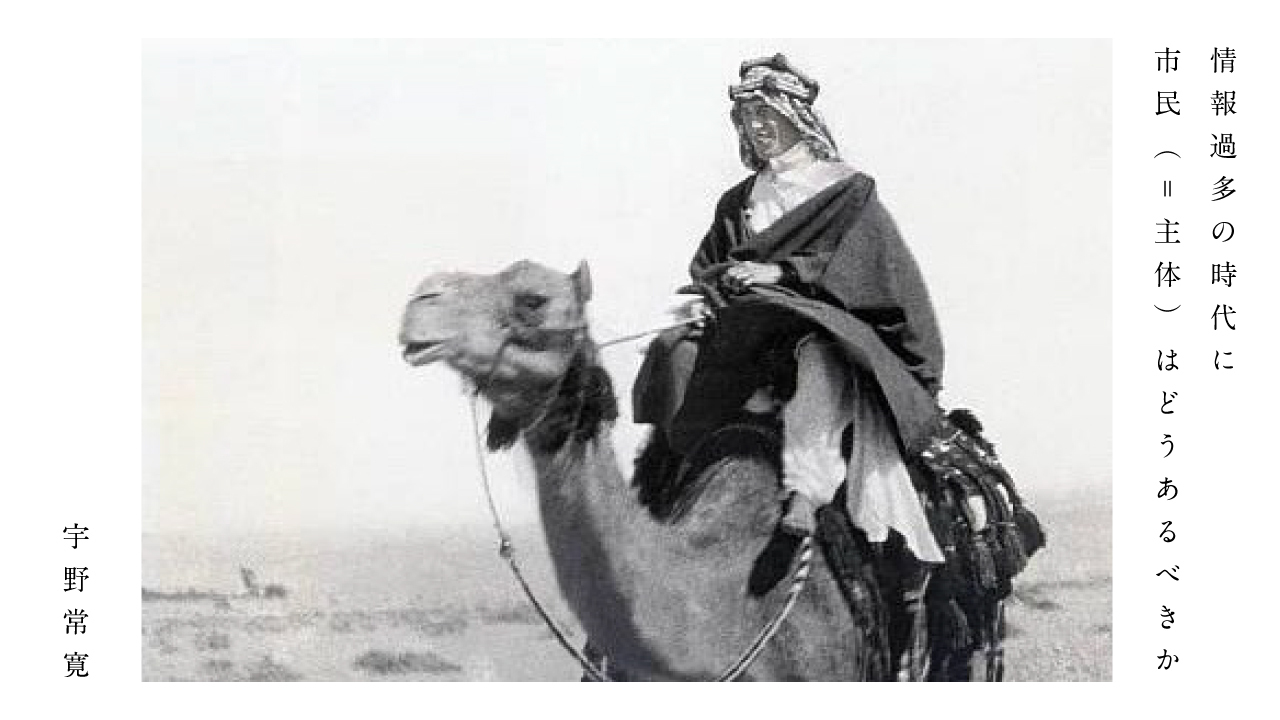
宇野常寛インタビュー<情報過多の時代に市民(=主体)はどうあるべきか>
明けましておめでとうございます。今年もPLANETSをよろしくお願いいたします。新年最初のメルマガは、PLANETS編集長・宇野常寛の特別インタビューをお届けします。
最後のフロンティアとして20世紀末に登場したインターネットが、逆に人々を閉じ込めている現代社会。その「外部」はどこにあるのか、長いコロナ禍の中で熟成させてきた思考を展開してもらいました。
(初出:「週刊読書人」2022年11月4日号(3463号))
情報社会における市民=主体はどうあるべきか
──パンデミックの蔓延、人々のインターネットへの常時接続、未曾有の状況の前に放棄された思考、民主主義という制度に支持された監視と統制……閉塞した現状をいかにして開くことができるのか。その思考実験が、異人たちの人生と思想を通じ、弛まず繰り返される本でした。
宇野 この本はコロナ禍の中で書かれた本で、その影響はやはり大きいです。ただ、僕の関心はたぶん世間とはかなり変わっていて、このパンデミックがインフォデミックに支えられていたことにあります。たとえば「コロナは風邪に過ぎない」とか、「特定の国家の生み出したウイルス兵器だ」といったデマや陰謀論が随分と流布し、影響力を持ちました。これらの言葉を信じた人は、単に愚かだったというよりは「わからない」ことに耐えられなかったのだと思います。二〇二〇年の時点で、COVID-19は人類にとって未知の存在でしたが、それをどうにかして理解可能なものにして受け止めるために、デマや陰謀論に縋ったのだと思います。また、「新しい生活様式」は新しい格差を生むと批判する人たちは、「新しい再分配」を進めるよりも「古い生活様式」に回帰することを主張しがちです。格差を批判する割には、感染爆発のときエッセンシャルワーカーがまっさきに犠牲になることには無頓着です。これは一例ですが、こういう端的に愚かな言説が支持を集めてしまうのは、要するに人間がウイルスという問題そのものにはほとんど関心をいだいていない、というか直視できなかったという現実があったように思います。人間は、新型コロナウイルスという未知の物事との手探りのコミュニケーションから逃避して、代わりに正解のわかっている人間間の相互評価のゲームに逃避したのだと思います。
ただ、正確には、コロナ禍はこの傾向を加速しただけで、それ以前から現代人はSNSの相互評価のゲームに没入して、物事そのものには触れられなくなっていたはずです。SNSのプラットフォームが普及して以降、人間はある問題に対してその解決法を探ったり、問題そのものの妥当性を検討するよりも、どう解答すると他のプレイヤーから評価を獲得できるかを考えるようになった。これが、ほとんどのプレイヤーが情報発信の能力を持つ社会を支配する相互評価のゲームです。たとえばこの国の民主主義にしても、この国の第二極は、支持者向けの言論ポルノとして第一極への対決姿勢を示し過ぎている、と批判されます。ところが真の野党を作らなければいけないと主張する第三極も、結局同じことをしている。第一極に対し劣勢な第二極を後出しジャンケン的に嘲笑することで、コンプレックス層を動員することに夢中になってしまっている。しかし残念ながら、全ての人が発信能力を持つこの相互評価のゲームにおいては彼らの戦略は有効なものでほとんど定石と言っていい。
この相互評価のゲームでは、既に大勢の人が話題にしている内容にコミットすること、そしてその話題についての主流派の意見に対してYESと言うかNOと言うか、潮目を読んでどちらかの意見を扇情的に投稿することが、最も簡単に承認を得る方法です。そのことに危機感を持って『遅いインターネット』では、二十一世紀初頭におこった送り手と受け手が明確に分かれていたメディアの時代から、全てのプレイヤーが受信者と発信者を兼ねるプラットフォームへの変化について、メディアの立場から介入してみたいと考えました。そして今回の『砂漠と異人たち』は、そこから一歩推し進めて、情報社会における市民=主体は、どうあればよいのかを考えてみようとしたのです。
今までとは違う言葉で話すこと
──民主主義とは「承認の再分配の装置」であり、Somewhereにとっての「世界に素手で触れる手触りを与える装置」だとも書かれていました。
宇野 この社会をとりまくゲームは二層構造になっています。イギリスのジャーナリスト、デイヴィッド・グッドハートは現代のクリエイティブ・クラスのような「どこでも」生きていける人々のことをAnywhere、前世紀の労働者のような「どこかで」しか生きていけない人々をSomewhereと呼んでいます。
現代の資本主義社会で、世の中を自分の手で変え得ると実感できるのは、グローバルな情報産業や金融産業のごく一部のプレイヤーだけです。彼らは国民国家という枠を超えて、グローバルな資本主義にコミットし、求心力の強いサービスや商品を投入することで、世界中の人々の生活を直接変えていきます。
かつてはTBSの日曜劇場のような世界観が生きていて、モノづくりを中心とした作業に従事することで、一労働者が国の経済発展に寄与し世界に関われていると実感できていた。しかしいまは、世界を前進させている産業はグローバルなものに変っています。このような社会では民主主義が、Somewhereが世界に素手で触れるための数少ない回路になっているんです。
人々が政治的に声をあげることは、一概に否定すべきことではありません。ただ自分が世の中に関わり得る証のために、手段ではなく目的として、政治的発言を消費する人たちはまた別の話です。敵対勢力への攻撃的な政治的発言を通し、ほかのプレイヤーから承認を得ようとするときに、デマや陰謀論に取り込まれやすい。こうした動きが現在世界中で観察されています。
──「ハラリの語る妥当さの無力と、ウエルベックのパフォーマンスの哀しい空回りのあいだに、いま僕たちは生きている」とありました。多くの人が、自分が信じたいものを信じ発信する時代に、シンプルな主張を伝えることがいかに難しいのか、つくづく感じるところです。
宇野 たぶんハラリも、正しい言葉が人を動機付けないことなどわかっているんです。ただ一方にオードリー・タンのような彼から見ればやや踏み込みすぎた技術主義者が現れたときに、自分たちの現状を確認するための良心的で常識的な発言を、国際的な知識人として繰り返さざるを得なくなっている。対してウエルベックの露悪的なパフォーマンスは二〇世紀文学の言葉が、この現実に対して無力であることを自覚しているためのものだと思うのだけれど、結局は自分はなにもかもわかっている人間なのだと自分に言い聞かせたい人の、幼稚なナルシシズムへのヒーリングにしかなっていない。
世代の違う二人のパフォーマンスは、いままでとは違う言葉で話さなければ、この状況の突破口を探すことは難しいと感じさせます。僕はハラリと同世代ですが、ハラリのような責任は幸いにして負っていないので、もっとミーハーで不真面目な言葉も用いて、この状況に一石を投じられないかと考えているんです。
──第二部のロレンス篇は、一緒に走らせてもらったかのような読後感でした。この旅の過程でどんどん景色が変わり、時には景色を堪能するために速度を落としたり、回り道したり……。そして、衝撃の結末が待っていました(笑)。
宇野 そこはぜひ、本で読んで楽しんで欲しいです(笑)。
高校生のときに、映画『アラビアのロレンス』を観て以来、ずっと興味をもっていて、いつかロレンスについて書きたいと思っていました。コロナ禍でロレンスのことをより考えるようになったのは、彼が世界の「外部」を目指して、砂漠に向った人物だったからです。現在のインターネットによってもたらされる閉塞とは、外部幻想の飽和なのだと思うのです。
そもそもコンピュータは、フロンティアの果ての西海岸で生まれた、革命の世紀の敗北の落とし子です。自己の内面の変革から世界の見え方を変えようとした、ヒッピーカルチャーの一ジャンルがシリコンバレーの源流の一つです。サイバースペースはそもそも、資本主義の外部を捏造するはずだった。それが二十一世紀に入り、新たなフロンティアとして資本主義に取り込まれ、結果人類をより強く縛り付ける繭になった。インターネットはその成立ちから、社会の外部にはなり得ぬ装置だという皮肉です。
僕の中で外部幻想によって自壊した人間の象徴がロレンスだったので、彼について書くことで、シリコンバレー的夢の破綻に、現代人はどう向き合うべきかが探れるのではないかと考えました。
noteで読む >>