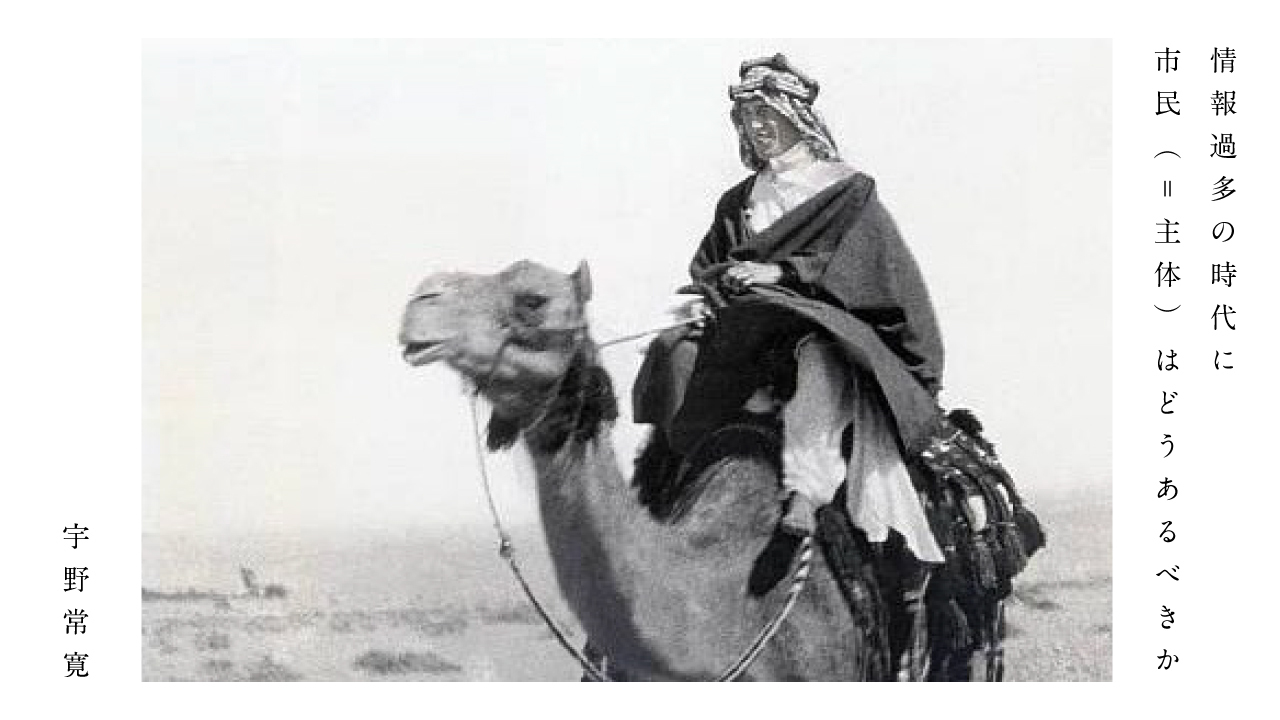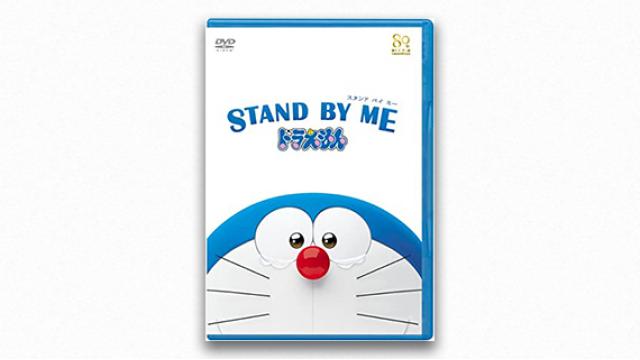〈補完〉後の未来――『ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:Q』 宇野常寛コレクション vol.9 【毎週月曜配信】
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回取り上げるのは『ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:Q』です。旧作を刷新するべく新たな勢力や謎を盛り込み、現代の時代状況へと切り込んだ本作。しかし、新勢力・ヴィレによるネルフ的マチズモの乗り越えという構図は、その旧さと歪さにより批評性の空転をもたらします。
※本記事は「原子爆弾とジョーカーなき世界」(メディアファクトリー)に収録された内容の再録です。
1995年秋、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』のテレビ放映が始まった。当時すっかりアニメオタクだった僕は、あのガイナックスの最新作がテレビで観られるということで期待に胸を膨らませながら待ち構えていた。今となっては信じられないことかもしれないけれど、当時(90年代前半から半ば)まではアニメは「冬の時代」だった。アニメオリジナルの企画が激減し、アニメ雑誌の表紙やファンコミュニティの話題の中心は有名漫画原作のアニメ化作品ばかりになっていた。その80年代のアニメブームを彩った数々の専門誌も、多くが何年も前に姿を消していた。当時僕は『ガンダム』の富野由悠季や、『パトレイバー』の押井守ファンで、つまり80年代のアニメブームに「間に合わなかった」ことをひどくうらめしく思っていた高校生で、函館じゅうの古本屋をめぐって当時の専門誌やムック本を買いあさりながらこの状況を退屈に、そして苦々しく思っていた。そんな中はじまった「エヴァ」はその圧倒的なクオリティと時代性でアニメに限らず国内の文化シーンをたちまち塗り替えていった。
僕はいちファンとしてこの現象を熱心に追いかけながらも、何か引っかかるものを感じていた。テレビ版最終回の直後に大塚英志が読売新聞に寄稿したエヴァ批判は切り抜いて何度読み返したかわからないし、太田出版から発売された『庵野秀明スキゾ/パラノ エヴァンゲリオン』は本屋で数時間ぶっ続けの立ち読みで読み通した。けれど、その引っかかるものはなかなか解消できなかった。当時たくさんの人間がエヴァに苛立っていたけれど、そういうのとはちょっと違った。彼らはエヴァが、身も蓋もない現実を描いてしまったことに苛立っていた。個人の人生を意味付けてくれる「歴史」の存在がサブカルチャーの世界ですら機能しなくなったこと(これは「ガンダム」シリーズの描く「宇宙世紀」に耽溺することで歴史=個人と世界をつなぐものの代替とする回路にハマれない消費者が現れたことを意味する)、退屈な消費社会の日常を一瞬でキャンセルしてくれる「世界の終わり」への渇望がしょせんローカルな人間関係での承認獲得の問題に矮小化されてしまっていること(これは押井守が『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』で試みた高橋留美子の描く無時間的なラブコメ空間に対する外部への喚起が、もはや機能しないことを意味する)を突きつけられ、彼らは動揺していた。僕もこの苛立ちにはひどく共感していた。しかしそれとは別に、僕には引っかかっているところがあった。当時はうまく言葉にできなかったけれど、僕が感じていたのはエヴァの「旧さ」だった。
この作品は間違いなく時代と寝ている。そして地殻変動のようなものを起こしてしまっている。さまざまな作品を過去のものにしてしまっている。しかし「それゆえ」に、その偉大さゆえにいま共感を集めているこのメンタリティはすぐに陳腐化してしまうのではないか。具体的には今、芽吹き始めている新しい時代の感覚を決定的に取り逃してしまっているのではないか……。当時感じていた違和感を今言葉にすると概ね、こうなる。テレビ版から97年春の劇場版、そして夏の劇場版での完結に至るまでのあいだ、僕はそんな違和感を抱え続け、そして言葉にできないでいた。しかし、今ならできる。