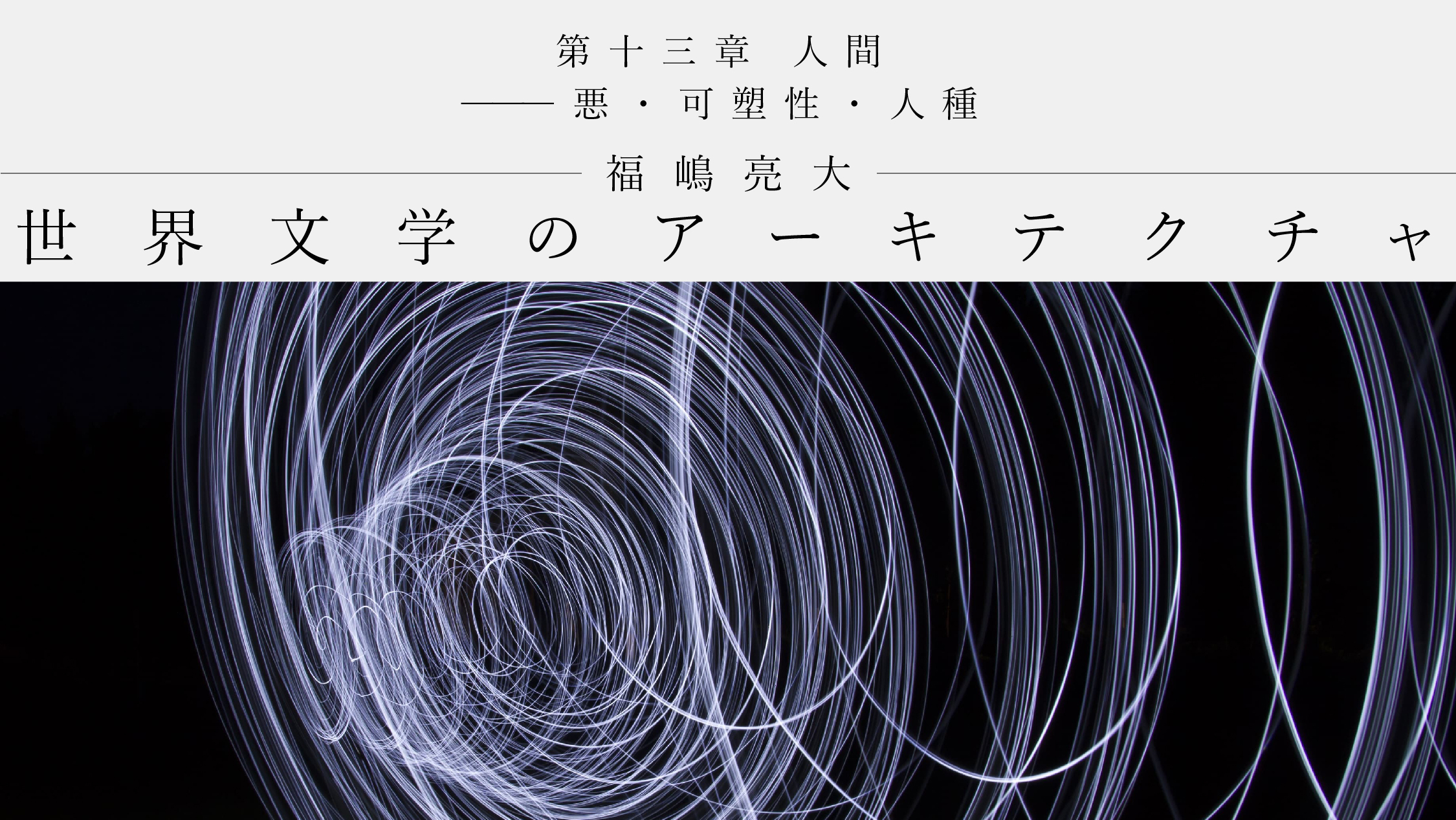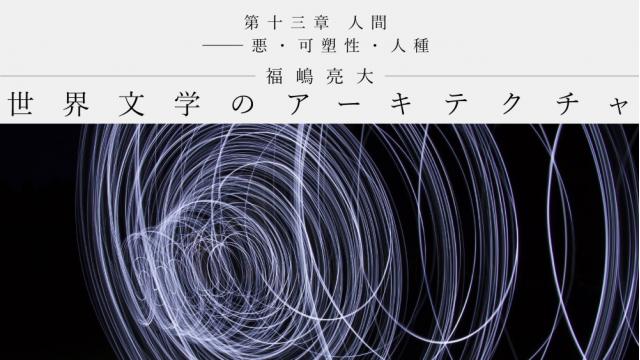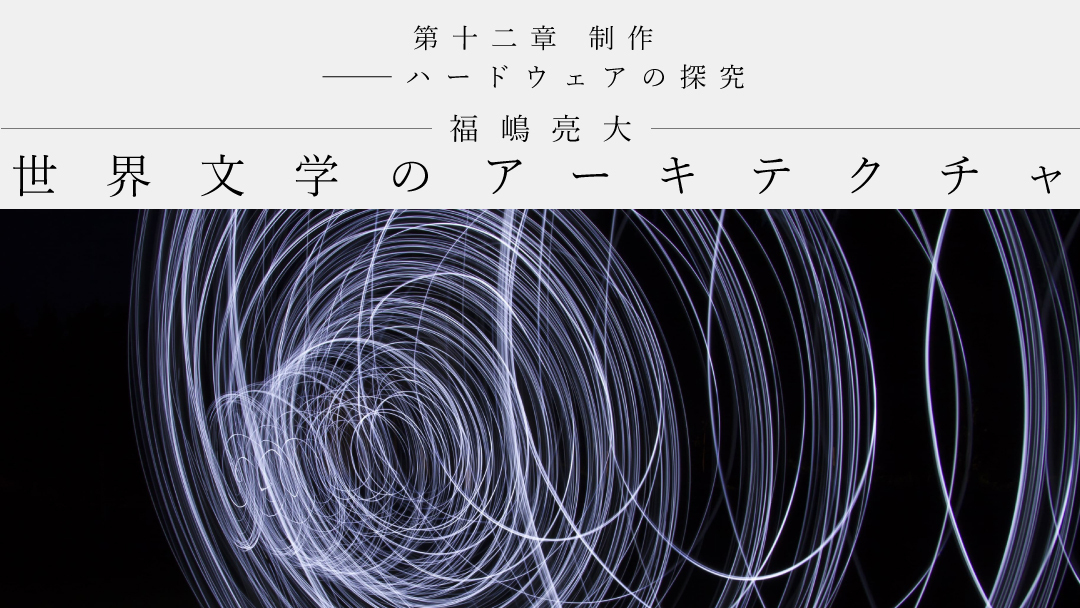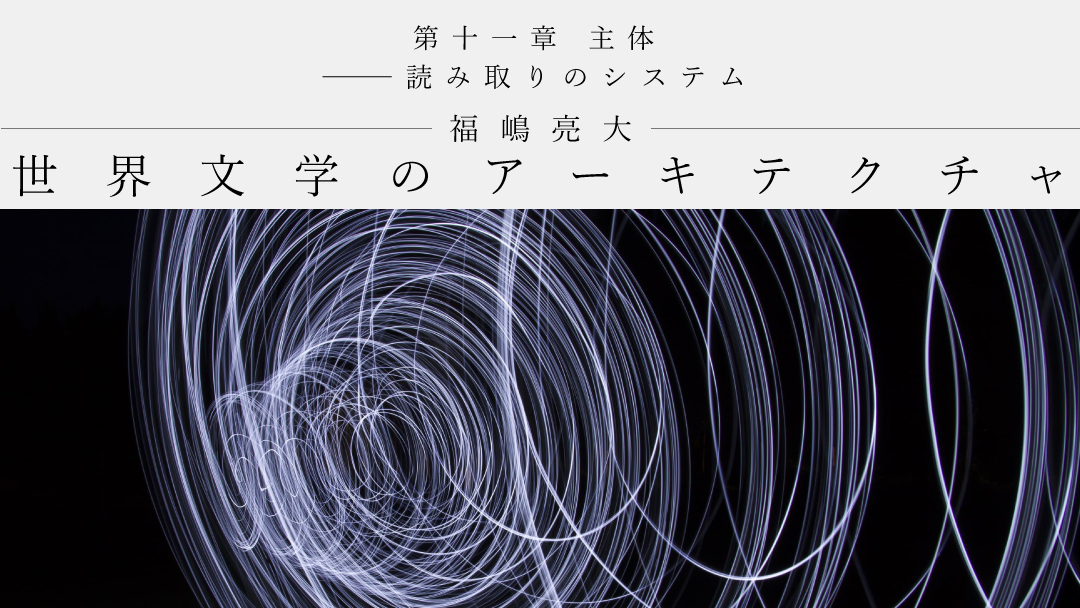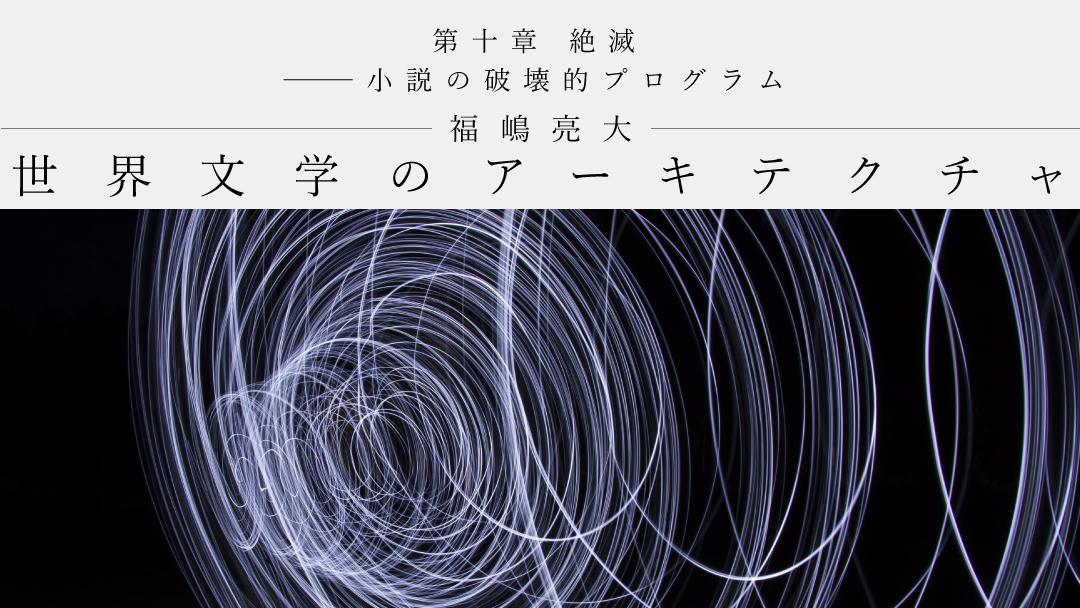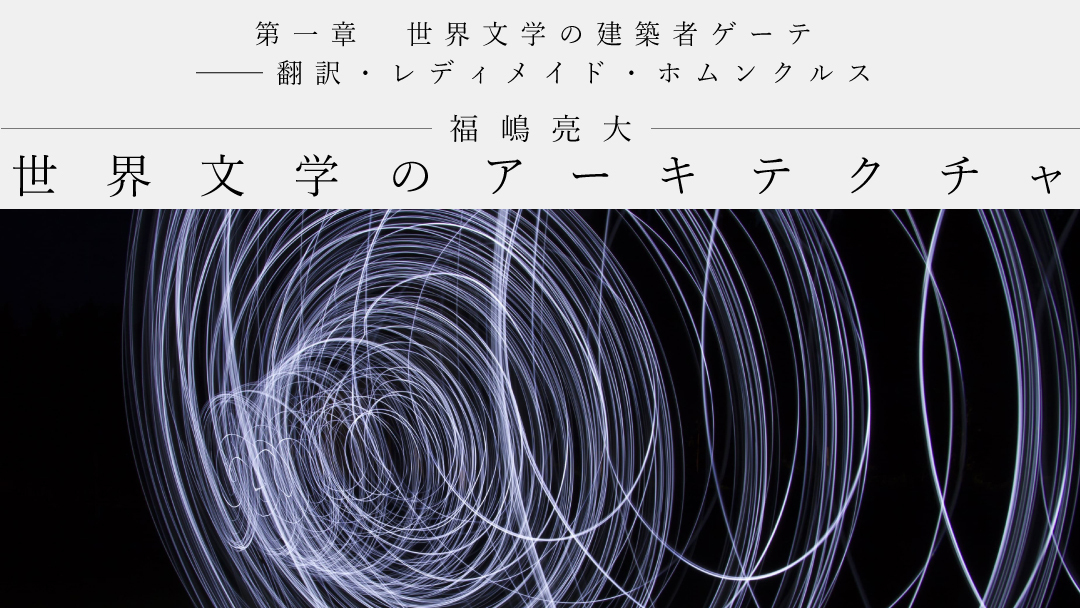
第一章 世界文学の建築者ゲーテ――翻訳・レディメイド・ホムンクルス(前編)|福嶋亮大
本日のメルマガは、批評家・福嶋亮大さんの連載「世界文学のアーキテクチャ」をお届けします。
19世紀の出版革命以後、文学作品の急激な民主化が起こった時代に「世界文学」はどのような概念として持ち出されたのか、その歴史を辿ります。福嶋亮大 世界文学のアーキテクチャ
第一章 世界文学の建築者ゲーテ――翻訳・レディメイド・ホムンクルス(前編)
1、ヴァイマルの文芸ネットワーク
序章で述べたように《世界文学》という概念の発明はもっぱら、一七四九年に生まれて一八三二年に亡くなったヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテに帰せられる。つまり、一八世紀ヨーロッパの文化的財産の継承者であり、かつ一九世紀前半にますます世界化してゆくヨーロッパの資本主義社会を生き抜いたドイツの哲人文学者が、《世界文学》に新たな生命を吹き込んだのである。
二つの世紀にまたがるゲーテの長い人生は、ヨーロッパの大変貌の時代と重なりあっている。近年のグローバル・ヒストリーを牽引する経済史家ケネス・ポメランツは主著『大分岐』のなかで、《一七五〇年》を世界史的な分水嶺と見なした。一八世紀半ばまではヨーロッパも東アジアも、経済成長に関しては並行的な進化を遂げてきた。ポメランツによれば、中国、日本、インドでも「スミス的成長」(商業的農業とプロト工業をベースとする経済成長)が顕著に見られたのであり、ヨーロッパだけが経済的に突出していたとは言えない。しかし、一七五〇年以降、ヨーロッパは豊富な石炭資源とアメリカ新大陸の市場を背景として急速な経済発展を遂げ、アジアをはじめ他地域を圧倒するようになった[1]。このポメランツの興味深い仮説に従うならば、まさに「大分岐」の生じるタイミングで生まれたゲーテは、ヨーロッパの奇跡的な躍進とともに成長した作家であったと言えるだろう。
ゲーテの世界文学論も、ヨーロッパそのものが世界的存在に成長してゆく状況と連動している。ただ、ゲーテは《世界文学》のアイディアを体系的な論文のなかで熟成させたわけではなかった。それは一七九二年生まれの弟子ヨハン・ペーター・エッカーマンが記録した、一八二〇年代のゲーテの談話に登場する考え方である。
国民文学というのは、今日では、あまり大して意味がない。世界文学の時代が始まっているのだ。だから、みんながこの時代を促進させるよう努力しなければだめさ。(一八二七年一月三一日。以下、年月日を記した引用はすべてエッカーマン『ゲーテとの対話』[山下肇訳、岩波文庫]に拠る)
偏狭なうぬぼれに陥らないために「好んで他国民の書を渉猟しているし、誰にでもそうするように」推奨していたゲーテにとって、世界文学とは何よりもまず実践的な目標であった。ゲーテは《世界文学》を新時代のミッションとして位置づけ、今後の文学は否応なく国境を越えて流通するだろうし、作家たちはその流れをいっそう加速させるべきだと主張した。このような文学の「自由貿易」のモデルは、作品の販路を拡大させる市場の成立と不可分である。
ゲーテにとって、文学作品の流通の拡大は、文学の内容にも質的な変化をもたらすものであった。イギリス人、ドイツ人、フランス人がお互いの作品を批評し「補正」しあうことが「世界文学にとっては大きな利点となり、この利点はますます現れてくるだろうね」とゲーテは楽しげに述べている(一八二七年七月一五日)。ゲーテ自身、ヨーロッパ文学はもちろんのこと、中国やアメリカの文芸まで目配りしていた。先に引用した世界文学についての意見も、ゲーテが翻訳で読んだ中国小説(清の『花箋記』と推測されている)への好印象――その自然描写や説話の用い方をゲーテは称賛している――をきっかけとして語られたものである。
もとより、このような批評や補正をやるには、知識の迅速かつ正確なやり取りが欠かせない。《世界文学》のアイディアが、エッカーマンとのくつろいだ座談の場で語られたことは、このアイディアそれ自体がコミュニケーション環境と一体であったことを示唆している。知識を交換し伝達するのに、ゲーテは談話や書簡というメディアを存分に活用し、それによってゲーテという存在そのものが、世界性を帯びた知の集積回路のように機能することになった。後述するように《世界文学》は一九世紀の新たなコミュニケーション革命を背景としていたのである。
そもそも、政治の中心都市ベルリンから離れたヴァイマルのゲーテ邸には、王侯貴族だけではなく文芸に関わる翻訳家や業者も、しきりに出入りしていた(ゲーテは都市の喧騒を嫌っていた)。ゲーテはときに、その翻訳業者の浅薄さに強い苛立ちを覚えることもあった。「文学という点では、全くのディレッタントのようだな。というのも、彼はドイツ語などさっぱり出来ぬくせに、早速やるつもりの翻訳やら、その扉に印刷する肖像やらの話をしたりする始末だからね」(一八二七年一月二一日)。しかし、このような一知半解の業者も含めた出版や翻訳のビジネスの隆盛がなければ、世界市場=世界文学も成り立ちようがなかったのは明らかだろう。辺境のヴァイマルは文芸ネットワークの結節点となり、精神の自由貿易をいっそう加速させたのである。
2、通貨としてのドイツ語
世界文学論の唱えられた一八二〇年代は、出版史上の画期点である。ロマン主義研究の大家であるモース・ペッカムは、紙の原材料不足が綿花によって解消されたことをきっかけとして、一八二〇年代に印刷物の爆発的増加が起こり、それが新たな読者層誕生の引金になったと指摘した。
一八三〇年までに、出版に革命的変化が起こっていた。印刷物はいまや安価で、人類史上初めて、読み書き能力があらゆる階級に著しく浸透していた。イギリスでは人口は四倍に増加していたが、読み書きができる人口は三二倍になったのである。たんに出版業が影響を受けたというだけではない。あらゆる種類のコミュニケーションと紙を媒介とする記録保存のすべて――雑誌、新聞、手紙、そして事業、政府、軍の通信と命令――が、その影響を受けたのである。[2]
語呂合わせ的に言えば、神ならぬ紙が大衆に知を配信し、出版も含めた通信技術全般の状況を変えたのである。この出版革命とリテラシーの飛躍に後押しされて、一八三〇年代以降、ヨーロッパには中産階級のリーディング・パブリック(読者公衆)が登場するようになった。
この新たな公衆の勃興に対して、旧来の知識人は自らが押しのけられつつあると感じ、しばしば強い嫌悪感を示した。イギリスではすでに一八二〇年代に、ある評論家が「文学がヨーロッパのいたるところで全く商売となっていることは恥ずべき悪弊である。これほど堕落した趣味を育て、無知なものに識者にまさる力を与えたものは、これまでなかった」と嘆き悲しんだ。彼らは新興の出版市場のもたらす文学の「堕落」や「無知」に対抗するために、cultureという言葉を導入した[3]。今の日本ではもはや想像しにくいが、文化や教養という言葉には、もともと市場へのアンチテーゼという意味があった。
とはいえ、反市場的な「文化」を旗印にしたところで、この大規模なコミュニケーション革命を後戻りさせることは不可能であった。ゲーテ自身、知的な仕事が次第に一部のエリートの専有物ではなくなりつつあることを、はっきり自覚していた。彼の自伝『詩と真実』には「誰もが今や哲学的に考えるのみならず、徐々に自らを哲学者と考える資格を与えられた」と明言されている。ゲーテにとって、哲学をやるにはもはや特別な才能ではなく、いわば試験管を扱うような技術があればよかった[4]。つまり、誰でも哲学者になれる時代が訪れたのである。
このような知の民主化を背景として、文学や思想が世界市場の商品として流通するようになったとき、翻訳の重要性が増したのは当然である。この点で、ドイツには固有の強みがあった。というのも、当時のドイツ語は他言語を媒介する通貨のような役割を果たしていたからである。ゲーテはエッカーマンに対して、ドイツ語がいかに柔軟に、ヨーロッパ諸言語の富を吸収してきたかを雄弁に語っていた。
今、ドイツ語がよくわかれば、他の言葉をたくさん知らなくても済むということも否定できませんからね。フランス語だけは別ですよ。フランス語は、社交用の言葉で、とりわけ旅行のさいには欠かせませんものね。だれでもわかるし、どこへいっても、優秀な通訳のかわりに、フランス語で用が足りますから。しかし、ギリシャ語やラテン語、イタリア語、スペイン語、となると、それらの国の最高の作品は立派なドイツ語訳でちゃんと読むことができる。(一八二五年一月一〇日)
このような見解はゲーテの次世代のロマン派の文学者たちにも受け継がれた。例えば、ロマン派の旗手ノヴァーリスの考えでは、ドイツ人とは翻訳によって文化を創り出してきた唯一の民族であった。ゲーテ以降の作家たちは、ドイツ人ないしドイツ語の卓越性を、異質なものの貪欲な吸収に認めたのである。ドイツ語の「多面的な受容力」を誇ったアウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルをはじめとする優れた翻訳者たちの仕事[5]のおかげで、ドイツ語の市場にはヨーロッパ文学が大量に入り込むことになった。
もともと、ゲーテは一八世紀フランスのヴォルテールやディドロを高く評価しており、彼らからいかに大きな恩恵を受けたかをしきりに語っていた。そのゲーテがますますその名声を高めるにつれて、今度はフランスやイギリスの作家がゲーテさらにはドイツ語の文芸に対して強い関心を抱くようになる。特に、ゲーテの翻訳者として最も名高く、かつゲーテ本人からも厚い信頼を寄せられていたのが、一七九五年生まれのイギリスの作家トマス・カーライルである。
カーライルはドイツ文学に精通しており、シラーの『ヴァレンシュタイン』の翻訳やドイツ文芸のイギリスへの紹介は、ゲーテにも高く評価された。『衣裳哲学』で示された彼の屈折の多い文体も、とりわけドイツの作家ジャン・パウルからそのアイロニカルな性格を受け継いでいた。ゲーテはこの四〇歳以上も年下のイギリスの若者と、書簡で頻繁にやりとりするようになった。両者は一度も対面では会ったことがなかったものの、その遠隔コミュニケーションの記録からは、原作者と翻訳者のあいだの親密な精神的同化のプロセスを読み取ることができる。
後にヴィクトリア朝を代表する批評家となったカーライルは、もともと文学の自律的価値を訴えていたにもかかわらず、ゲーテの死後には神学的・道徳的な立場から苛烈な文学批判に回るようになり、ドイツのエンゲルス――文学の時代はすでに終わったと見なし、政治的行動を賛美した――にも影響を及ぼした[6]。それは、一八二〇年代から三〇年代にかけて続いた老ゲーテとの書簡のやりとりからは予想しにくい「転向」だが、この興味深い問題については後の章で述べよう。ここで注目したいのは、ゲーテがカーライル宛ての書簡のなかで、翻訳の仕事を経済的な観点から説明したことである。
ドイツ語を理解し、また学ぶ人は、あらゆる国民がその商品を持ち寄る市場のなかに身を置いているのです。そして、自分自身を富ましながら、通訳の役割を演じているのです。したがって、あらゆる翻訳者は、この一般的な精神的商業の仲介者として努力し、相互の交換を促進することを仕事とする人と見なされるべきです。[7]
ここでゲーテはコミュニケーションの通貨としてのドイツ語の利点を語りながら、国民どうしの「相互の交換」を促す翻訳者を「精神的商業」の主要なプレイヤーと見なしている。ゲーテの《世界文学》という理念が、いかに深く経済的なイメージと結びついていたかが、ここからも了解されるだろう。
3、思想としての翻訳
そもそも、ゲーテ自身、名うての翻訳者であった。一八世紀フランスの思想家ドゥニ・ディドロの傑作小説『ラモーの甥』――哲学者の「私」と音楽家ラモーの甥の対話体小説で、ディドロの生前には刊行されず長く知られていなかった――を見出し翻訳したのは、ドイツ人のゲーテである。哲学者ヘーゲルも『ラモーの甥』をゲーテの翻訳で読み、それをさっそく主著『精神現象学』(一八〇七年)で活用した。シャーマン的な変性意識のモチーフを含んだ『ラモーの甥』が、その受容においてもフランス語からドイツ語へと折り返されたのは興味深い[8]。『ラモーの甥』は単一の言語においてではなく、二つの言語の織り成す襞において奇跡的に生き延びてきた稀有な小説なのである。
ゲーテの作品もまた、翻訳の効果を強く受けていた。ゲーテはドイツ語ではもう自作の『ファウスト』を読む気にならないものの「仏訳で読んでみると、全篇があらためてじつに清新で生気に満ちた印象をうけるね」とエッカーマンに楽しげに語っている(一八三〇年一月三日)。そもそも、『ファウスト』は二〇代半ばのゲーテの草稿に始まり、一八〇八年刊行の第一部から、ゲーテ死後の一八三三年刊行の第二部に到るまで、実に半世紀以上にわたって、文字通り何度も転生し続けた異例の作品であった。そこにフランス語版が加わったとき、『ファウスト』は再び「生気に満ちた」若々しさを取り戻すことができた。
そう考えると、ファウストがまず聖書の翻訳者として現れることは意義深い。一人きりで書斎に閉じこもったファウストは、まるでルターのように聖書のドイツ語訳を試みるが、第一行目の「はじめに言ありき」に対して早くも強い不満を覚える。「もっと別の訳し方」をせねばならないと決意するファウストが「はじめに意ありき」「はじめに力ありき」という訳語を思いつきながらいずれにも満足できず、ついに霊の助けを得て「はじめに行ありき」というしっくりくる訳語にたどり着くシーン(一二二三行以下/『ファウスト』[山下肇訳、潮出版社]の引用は以下行数のみ示す)は、まさに聖書のハッキングの犯行現場と呼ぶにふさわしい。
こうして、本来は不可侵のテクスト(聖書)ですら、ファウストの翻訳にさらされるうちにそのデータが改竄され、行為を促す新たな命令に置き換えられる。ハッカー的翻訳者としてのファウストはこの「はじめに行ありき」という偽のプログラムに耳打ちされて、新しい人生を探査する冒険へと導かれる。ファウストひいては『ファウスト』という作品そのものにブレイクスルーをもたらしたのは、別の生を開く翻訳の実践なのである。
だとすれば、とりわけドイツ語の環境においては、翻訳そのものが根源的な思想であり批評運動であったと言わねばならない。そのことは、ゲーテの後輩である詩人フリードリヒ・ヘルダーリンの仕事からも分かる。ヘルダーリンは古代ギリシアの劇作家ソフォクレスの翻訳に取り組んだが、それはギリシア語を逐語的にドイツ語に置き換えようとする荒業を伴っていた。そうすると当然ドイツ語としては破格のものになるが、それによってかえってドイツ語の表現には新しい局面が開かれた。
後にヴァルター・ベンヤミンは翻訳を「死後の生(Fortleben)」を指し示す行為と見なしながら、ヘルダーリン的な逐語性を「アーケード」と評し、それが原文の意味ではなく「純粋言語」を伝達しようとする特異な試みであると指摘した[9]。つまり、ベンヤミンにとって、ヘルダーリン的翻訳とは、言語を言語たらしめる根源的な何かを抽出し、それをテクストからテクストへと送り届けるアーケード=通路にほかならない。これはいささか神秘的な見解であるとはいえ、たんなる意味の表現には回収されない特別なコミュニケーションを翻訳に見出したのは、ヘルダーリン=ベンヤミンの大きな功績である。
かたやゲーテにとっても、翻訳は作品に「死後の生」を贈与することに等しい――まさに『ファウスト』がフランス語訳によって新たな生を得たように。ただし、ヘルダーリンとは違って、ゲーテは無謀な逐語訳にはこだわらなかった。メディア理論家のフリードリヒ・キットラーが注目したように、ゲーテはむしろ、詩を散文に訳してもなお残り続けるものにこそ価値を見出した[10]。ゲーテ的翻訳においては原文の正確さはある程度犠牲になるが、それが失われた後でも残るものがゲーテにとっては本質的なのである。
そう考えると、ヘルダーリンではなくゲーテが《世界文学》の提唱者になったことには十分な理由があるだろう。ゲーテは通貨としてのドイツ語を用いて、まさに「言説の配信」(キットラー)としての翻訳のプロジェクトに積極的に関わった[11]。国外に翻訳=配信される作品が増えれば増えるほど、精神の交易もいっそう盛んになる。ヘルダーリン的翻訳が純粋言語を通過させるアーケードを築くことだとしたら、ゲーテ的翻訳はいわば、意味や価値のやりとりされるグローバルな配信プラットフォームを組織することに近かった。
[1]K・ポメランツ『大分岐』(川北稔監訳、名古屋大学出版会、二〇一五年)。
[2]モース・ペッカム『悲劇のヴィジョンを超えて』(高柳俊一他訳、上智大学出版、二〇一四年)一八頁。
[3]レイモンド・ウィリアムズ『文化と社会 一七八〇‐一九五〇』(若松繁信他訳、ミネルヴァ書房、一九六八年)三九-四〇頁。
[4]カール・ベッカー『一八世紀哲学者の楽園』(小林章夫訳、上智大学出版、二〇〇六年)五二頁以下。面白いことに、ゲーテの親世代にあたるカントは一七九六年の論説で、哲学という言葉がイージーに使用され「哲学という名称の装飾的な使用がモード」になっている状況に嫌味を言っている(「哲学における最近の高慢な口調」『カント全集』第一三巻、岩波書店、二〇〇二年所収)。カントからゲーテに到るまでに、哲学者の資格の捉え方が大きく変わったことは注目されてよい。
なお、この時期の「哲学の装飾的な使用」という観点から言えば、一七九五年に出たサド侯爵の『閨房哲学』以上に興味深い作品は少ない。この小説は、道徳的な若い女性に性教育を施し、悪徳に回心させるという趣旨のもと、三六歳のドルマンセをはじめとする若い男女四名の対話劇として展開される。哲学対話の場としての閨房――それは性と政治、快楽と暴力を混ぜあわせながら、哲学的言説に悪ふざけの要素を浸透させる。例えば、サドはそこに「フランス人よ、共和主義者になりたければあと一息だ!」という有名なアジテーションの文書を挿入しているが、これは当時の政治的なパンフレットのパロディとして読み解ける。この生気(性器?)溌溂とした「傍若無人の悲喜劇」のもつサタイア(諷刺)的性格については以下が詳しい。John Phillips, Sade: The Libertine Novels, Pluto Press, 2001, chap.3.
[5]アントワーヌ・ベルマン『他者という試練』(藤田省一訳、みすず書房、二〇〇八年)二六頁以下。
[6]ペーター・デーメツ『マルクス、エンゲルスと詩人たち』(船戸満之訳、紀伊國屋書店、一九七二年)五七頁以下。
[7]『ゲーテ゠カーライル往復書簡』(山崎八郎訳、岩波文庫、一九四九年)一五‐六頁。訳文は一部変更した。
[8]グローリア・フラハティ『シャーマニズムと想像力――ディドロ、モーツァルト、ゲーテへの衝撃』(野村美紀子訳、工作舎、二〇〇五年)の推測によれば、ディドロはロシアの女帝エカチェリーナと交流する一方、ロシアのシャーマニズム関連の文献も読み込んでおり、その情報を『ラモーの甥』の主人公の造形にも利用した。フラハティはこの近代のシャーマン的想像力の頂点に『ファウスト』を置いている。
[9]「翻訳者の使命」『ベンヤミン・コレクション2』(浅井健二郎編訳、ちくま学芸文庫、一九九六年)三九一、四〇五頁。
[10]フリードリヒ・キットラー『書き取りシステム1800‐1900』(大宮勘一郎他訳、インスクリプト、二〇二一年)一四二頁。
[11]同上、一四〇頁。
(続く)
プロフィール
福嶋亮大
1981年京都市生まれ。批評家。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。著書は『復興文化論』『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』『ハロー、ユーラシア』『感染症としての文学と哲学』『書物というウイルス』他。
noteで読む >>