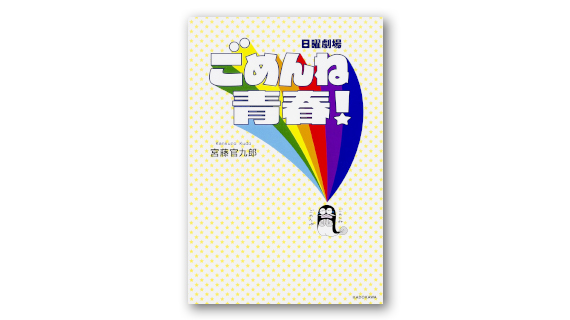
世界が「木更津」化したあとに――『ごめんね青春!』(PLANETSアーカイブス)
今朝のPLANETSアーカイブスは、宇野常寛による『ごめんね青春!』批評です。『木更津キャッツアイ』『あまちゃん』などで時代の空気を絶妙に掴んできたクドカンは、今作ではなぜこれまでのような切れ味を発揮できなかったのか? この10年余りの社会状況・情報環境の変化から考えます。(初出:『ダ・ヴィンチ』2015年3月号(KADOKAWA))
※この記事は2015年3月13日に配信した記事の再配信です。
クドカンこと宮藤官九朗の最新作『ごめんね青春!』は、主にその低視聴率による「苦戦」で世間に知られる結果になってしまった。しかし、そもそも彼の作品が視聴率的にヒットしたのは東野圭吾原作の『流星の絆』くらいの話で他は良くてもスマッシュヒット、といったところだろう。二度も映画化されたロングセラー『木更津キャッツアイ』も本放送の視聴率はぱっとしなかったし、あの『あまちゃん』でさえも、内容的には凡作としか言いようがない『梅ちゃん先生』に平均視聴率では負けていた。クドカン作品の魅力とは、端的に述べれば広く浅く拡散していくものではなく、深く刺さるタイプのものなのだ。
だから僕は本作をその視聴率的苦戦をもって何か言おうとは思わない。現に僕自身、このドラマを毎週楽しみにしていて、最後まで面白く観ていたのは間違いない。
しかし残念ながらその一方で、僕はこのただ楽しく、面白いドラマに物足りなさを感じていたことも正直に告白しようと思う。もちろん、テレビドラマに楽しく面白い以上の価値は必要ない、という考えもあるだろう。しかし、少なくとも僕はクドカンドラマにそれだけではないものを感じてこれまで追いかけてきたのだ。
今思えば『池袋ウエストゲートパーク』はモラトリアムの「終わりの始まり」の物語だった。長瀬智也演じるマコトが思春期の終わりに、それまで足場にしていた「ジモト」のホモソーシャルの限界に直面する。そして同じ長瀬智也が主演を務めた『タイガー&ドラゴン』はいわゆる「アラサー」になった主人公が、若者のホモソーシャルとは一線を画した大家族的な共同体に軟着陸していく過程を描いていた。そして長瀬が32歳で主演を務めた『うぬぼれ刑事』は、完全に「おじさん」になった主人公がもう一度、大人のホモソーシャルに回帰していくさまを描いていった。要するに、クドカンは自分よりも8つ年下の長瀬智也の肉体を借りて男性の成熟を、歳の取り方を描いてきた作家でもあるのだ。同世代の同性たちからなる若者のホモソーシャルが加齢とともにゆるやかに解体し、やがて(擬似)家族的なものに回収されていく。しかしクドカンの想像力は教科書的な成熟と喪失の物語を選ぶことはなく、やがて男の魂は新しい、大人のホモソーシャルに回収されていったのだ。
クドカンのドラマから僕がいつも感じるのは、部活動的なホモソーシャルだけが人間を、特に男性を支えうるという確信と、その一方でこうしたホモソーシャルの脆弱さに対する悲しみだ。この確信と悲しみの往復運動が、クドカン作品における長瀬智也の演じるキャラクターの変遷をかたちづくり、あるいは『木更津キャッツアイ』シリーズでクドカンが描いてきた儚いユートピアのビジョンに結実していった。
この視点から『木更津キャッツアイ』について振り返るのならば、人間がこうした部活動的なホモソーシャル、同世代の、同性からなる非家族的な友愛の、「仲間」的なコミュニティに支えられたまま(「まっとうな近代人」の感覚からすればモラトリアムを継続したまま)歳をとって死んでいくという人生観を提示し、しかもそれを幸福なものとして描き出したところが衝撃的だったと言える。そして『タイガー&ドラゴン』以降の作品は、クドカン自身がこの『木更津キャッツアイ』で提示したものを自己批評的に展開していったものに他ならない。
思えばクドカンが台頭したゼロ年代は、「仲間主義」と「ホモソーシャル」の台頭した時代だった。90年代的な恋愛至上主義文化の反動から、恋愛やファミリーロマンスでは人間の欠落は埋められないという世界観が支持を集め、まず『ONE PIECE』的な仲間主義が台頭し、そして「日常系」アニメ(『けいおん!』『らき☆すた』)からAKB48、EXILEまでホモソーシャル(では正確にはない。これらのコミュニティには紅/緑一点の異性すらいない。ミソジニー傾向の代わりに、ボーイズ・ラブ的な友愛の関係性が支配している)の中での非生殖的、反家族的な関係性がジャンル越境的に国内ポップカルチャーにおいて支配的になっていった。そう、今思えば『木更津キャッツアイ』はその後10年に起こることを先取りしていた作品だった。
あれから10年余り、世界はある意味すっかり「木更津」化した。
若者向けのポップカルチャーはすっかり木更津キャッツアイ的な「ホモソーシャル2.0」の原理が支配的になった。『木更津キャッツアイ』は企画当初『柏キャッツアイ』であったことが象徴的だが、彼らがジモトを愛する理由は、そこに地縁と血縁があるからではなく、自分たちの「仲間」の思い出が、歴史があるからだ。だから同作に登場した青年たちは自分たちの内輪ネタとサブカルチャーの「小ネタ」で凡庸な郊外都市である木更津を、自分たちにとっての「聖地」に変えていった。
そして今、こうしたコンテンツ依存のジモト愛の喚起、町おこしはむしろ地方自治体の常套手段と言っても過言ではなくなった。2013年に社会現象的ブームを巻き起こし、後世にはおそらくクドカンの代表作として語り継がれるであろう『あまちゃん』の放映時に、舞台となった岩手県三陸地方がこうした「聖地」化によって大きくクローズアップされたことは記憶に新しい。
そう、この10年余りのあいだに、世界はすっかり「木更津」化したのだ。
クドカンの話に戻そう。クドカンの一連の試行錯誤の集大成が『あまちゃん』だったことは間違いない。クドカンはここで、戦後の消費社会史をアイドルというアイテムを用いて総括した。ここでは前述のクドカンがそれまで培ってきた「ジモト」への視線が、戦後社会の精神史を描く上で大きく寄与していたのだが、本作『ごめんね青春!』では『あまちゃん』では扱われなかった男性の成熟とモラトリアムの問題が再浮上することになった。本作のプロデューサーはTBSの磯山晶、『池袋ウエストゲートパーク』にはじまる一連の長瀬智也主演作品や『木更津キャッツアイ』を担当した人物だ。主役を務めるのは長瀬よりも6歳若い錦戸亮。彼が演じる高校教師が、勤務先の男子校と近所の女子校の合併のために尽力しながら、30歳になっても引きずっている青春の日のトラウマに決着をつける、という物語が展開した。
これは言い換えれば、『木更津キャッツアイ』で一度男女を分離した、少なくともロマンチック・ラブ・イデオロギーやファミリー・ロマンス信仰とは異なるかたちの救済を提示したクドカンが、もう一度男女を出会わせようとしたもの、とひとまずは言えるだろう。しかし、残念ながらこのコンセプトは物語前半で空中分解してしまった。
本作では当初激しかった主人公の属する男子校と、合併先の女子校との対立は物語の序盤(第三話)であっさりと解決する。男子生徒嫌いの急先鋒だった黒島結菜演じる女子校側の生徒会長が、自分たちはこれから「男子」と書いて「アリ」と読む、と宣言する。あまり気の利いたセリフ回しではないが、それはまあ、いいだろう。しかし、その後同作はホモソーシャル同士の衝突を正面から描くことはなくなり、端的に言ってただの学園ラブコメになってしまう。もちろん、ただの学園ラブコメであることが悪いわけではない。ただ、この瞬間にどうしてこの複雑な設定が存在するのか、その意味はなくなってしまった。
こうして「再び〈男女〉を出会わせる」というコンセプトを失ってしまった同作は、最終回へ向けて主人公の教師・平助のトラウマの解消、高校時代に犯した罪の告白と清算(彼なりの「青春」への決別)に焦点を移すことになる。そして、最終回で平助は自分が担任していた学年の卒業式に学生服で乱入し、自分の「卒業」を宣言して青春に別れを告げる。思春期の恋が生んだ葛藤にケリをつけて、次のステージに進む。教師をやめ、満島ひかり演じる女子校の教師と結婚し、自分は学校をやめて地元FM局のDJになる。大いに結構だが、ここで提示された「成熟」モデルが、僕にはどうにも魅力的なものには見えなかった。
noteで読む >>
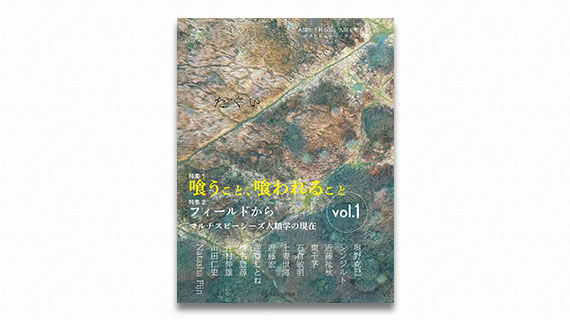
デジタルネイチャー時代の人類学 ──マルチスピーシーズが導く「制作論的転回」とは(前編)|奥野克巳(PLANETSアーカイブス)

『花子とアン』はなぜ「モダンガール」を描き切ることができなかったのか?|中町綾子×宇野常寛(PLANETSアーカイブス)

人間の「伸びしろ」を測定することは可能か? ──統計学的思考の教育への応用可能性 鳥越規央(統計学者)×藤川大祐(教育学者)(PLANETSアーカイブス)



もはやサブカルチャーは「本音」を描く場所ではなくなった――『バケモノの子』に見る戦後アニメ文化の落日(宇野常寛×中川大地)(PLANETSアーカイブス)

どこまでも遠くへ届くもの―― 宇野常寛、『ゴーマニズム宣言SPECIAL 大東亜論』を読む(PLANETSアーカイブス)

私は如何にして執筆するのを止めてアイドルを愛するようになったか――濱野智史が語る『アーキテクチャの生態系』その後(PLANETSアーカイブス)


木俣冬×宇野常寛 『真田丸』――『新選組!』から12年、三谷幸喜の円熟を感じさせるただただ楽しい大河の誕生(PLANETSアーカイブス)











