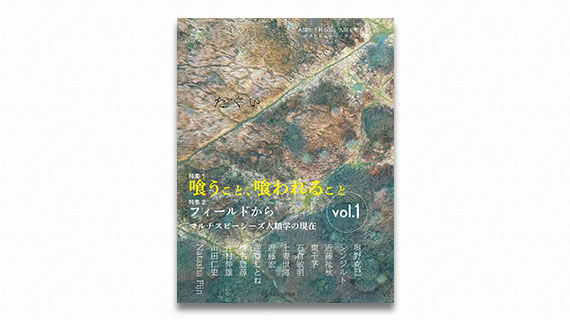
デジタルネイチャー時代の人類学 ──マルチスピーシーズが導く「制作論的転回」とは(前編)|奥野克巳(PLANETSアーカイブス)
今回のPLANETSアーカイブスは、人類学者・奥野克巳さんへのインタビュー前編をお届けします。人間以外の「他者」との関わりから新たに人類のあり方を捉えなおすべく「マルチスピーシーズ人類学」を主導する奥野さん。議論は人類学の歴史から、落合陽一さんの提唱する「デジタルネイチャー」へと広がっていきます。(聞き手:宇野常寛・中川大地 構成:石堂実花)
※本記事は2019年4月9日に配信した記事の再配信です。
現代人類学は何を課題にしているのか
──このたび創刊された『たぐい vol.1』は、奥野さんが2016年から主宰されている「マルチスピーシーズ人類学研究会」を母体にした雑誌です。この年は、中沢新一さんが現代における「野生の思考(レヴィ=ストロース)」の再生だと位置づけてきた『ポケモン』の拡張現実ゲームが世界的なブームを引き起こしたり、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』が邦訳されてベストセラーになったりと、人類学的な視座から現代の情報技術文明の在り方を捉え直そうとする機運が大きく高まってきたタイミングでした。
一方で、僕らが昨年刊行した『PLANETS vol.10』でも、落合陽一さんが「マタギドライヴ」というキーワードを提唱しています。これはつまり、デジタルネイチャー化した人工知能時代の情報環境では、人々の生き方はしだいに農耕民的なものから狩猟民的なものに近づいていくだろうという描像です。
ですので、こうした情報テクノロジー環境における新たなライフスタイルを展望するにあたっては、奥野さんたちが進めている新しい人類学の知見が、これから非常に重要になっていくのではないかという予感を持っています。そこでまずは、現代の人類学がどのような状況にあるかの見取り図からお伺いしたいと思うのですが。

▲『たぐい vol.1』

奥野 はい。雑誌の冒頭で人類学の現在についての論考を寄せていますが、20世紀初頭に確立された人類学には、われわれの文明とは異なる社会に出かけて、現地の「文化」を民族誌に記述するというスタイルが、イギリス人類学の立役者であるブロニスラフ・マリノフスキーらによって1920年代に制度化されました。
これが1980年代に入ると、アメリカ人類学からポストモダン的な反省モードが起こって、「再帰人類学」と呼ばれる時期がおよそ四半世紀続きました。要するに、近代的な観察者としての人類学者が、どこか局所的な地域に出かけて民族誌を生産するというシステムの正当性や権力性を自己反省していくモメントですね。
──たとえばポストコロニアルやカルチュラルスタディーズなど、植民地主義を批判するような議論とつながっていったということでしょうか。
奥野 そういうことですね。人類学としては、エドワード・サイードの『オリエンタリズム』(1978年)の批判の流れを引き受けたわけです。一言で言ってしまえば、西欧側の一方的な東側、オリエントに対する表象をめぐる問題ですね。この問題は、人類学の持っている西洋から出発し非西洋をまなざすという学的態度とパラレルです。オリエンタリズム批判を人類学が引き受けて、文化を書くこと、民族誌を書くということはいかなることかについて反省し始めた。そこにさらにポストコロニアルのような権力構造みたいなものが入ってきて、ポストモダンと合体して、二段構造になっているんですね。それを受けて、人類学は反省するような再帰的なモードを持ったと。
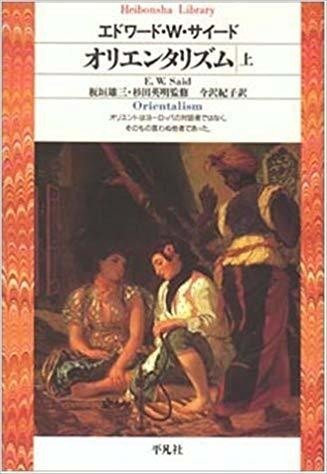
──なるほど。
奥野 そうした英米の人類学の流儀に対して、フランスのクロード・レヴィ=ストロースがブラジルで1938年に始めたフィールドワークは、単に局所的な文化を記述するものではありませんでした。いくつかの地域を比較しながら、汎用性のある普遍的な要素を考察するというやり方を、『親族の基本構造』(1949年)から『神話論理』(1964〜71年)にかけての著作で展開し、構造主義人類学を確立して一時代を築きました。つまり、『神話論理』が提示したのは、いわゆる「未開社会」の局所的な文化を観察・記述することではなく、一見異なる表層をもった神話でも、そこに登場した要素を記号的に変形していくことで、その根底にはしっかりとした共通の構造が見出だせるという考え方ですね。
この『神話論理』における構造抽出の核心にあるのは、自然と人間なんです。従来のマリノフスキー的な民族誌が人間内部の差異に着目していたのに対して、レヴィ=ストロースは人間内部ではなく、人間を超え出た自然と人間の関係をテーマとした。この立場を引き継ぐかたちで、レヴィ=ストロースの弟子たち、フィリップ・デスコラ、エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ、さらにはブルーノ・ラトゥールらが20世紀の後半から21世紀に入って台頭してきます。彼らは、アニミズムの再定義やパースペクティヴィズム、さらにはもっと大きなテーマとしては多自然主義やアクター・ネットワーク理論といった、新たな論点を打ち出しました。
自己反省モードからの脱却 人類学の現在形
──つまり、現在の人類学は、西欧近代の伝統的な価値観への単なる自己反省的なモードから、もっと新たな価値をポジティブに模索し始めているということでしょうか。
奥野 はい、内向きの自己反省モードから抜け出たという認識ですね。英米系の再帰人類学の自己反省的なモードが四半世紀続いて、そこを抜け出ようとする過程で、1990年代あたりには応用人類学や開発人類学といった領域が強くなりました。つまり、人類学には未開社会の知識が豊富にあるので、それは開発や国際協力の文脈で応用できるんじゃないかという流れになった。
しかしそれは、人類学を面白くなくさせたわけです。人類学というのはそもそも人間を考えるものであった。それは、現代社会の制度ややり方を前提としないということですよね。応用人類学や開発人類学が出てくると、その土地のことを良く知っている人類学者が関与し、第三世界に対しての開発協力をする。これは非常に実践的なものであって、再帰人類学をそもそも突破できてないんじゃないかっていう話ですね。
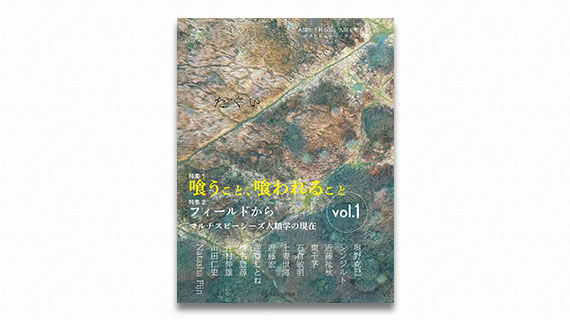
デジタルネイチャー時代の人類学 ──マルチスピーシーズが導く「制作論的転回」とは(前編)|奥野克巳(PLANETSアーカイブス)

『花子とアン』はなぜ「モダンガール」を描き切ることができなかったのか?|中町綾子×宇野常寛(PLANETSアーカイブス)

人間の「伸びしろ」を測定することは可能か? ──統計学的思考の教育への応用可能性 鳥越規央(統計学者)×藤川大祐(教育学者)(PLANETSアーカイブス)



もはやサブカルチャーは「本音」を描く場所ではなくなった――『バケモノの子』に見る戦後アニメ文化の落日(宇野常寛×中川大地)(PLANETSアーカイブス)

どこまでも遠くへ届くもの―― 宇野常寛、『ゴーマニズム宣言SPECIAL 大東亜論』を読む(PLANETSアーカイブス)

私は如何にして執筆するのを止めてアイドルを愛するようになったか――濱野智史が語る『アーキテクチャの生態系』その後(PLANETSアーカイブス)


木俣冬×宇野常寛 『真田丸』――『新選組!』から12年、三谷幸喜の円熟を感じさせるただただ楽しい大河の誕生(PLANETSアーカイブス)











