
ディズニー/ピクサー的CGアニメは「宮崎駿的手法」を取り込むことができるか?――落合陽一、宇野常寛の語る『ベイマックス』(PLANETSアーカイブス)
今朝のPLANETSアーカイブスは『ベイマックス』をめぐる落合陽一さんと宇野常寛の対談です。『アナ雪』大ヒット以降のディズニー/ピクサーが、「CGテクノロジーの進化」と〈宮崎駿的なもの〉という2つの課題にどう向き合ってくのかを考えます。(初出:『サイゾー』2015年3月号(サイゾー)/構成:有田シュン)
※この記事は2015年3月24日に配信した記事の再配信です。
▼作品紹介
『ベイマックス』
監督/ドン・ホール、クリス・ウィリアムズ 脚本/ジョーダン・ロバーツ、ドン・ホール 原作/『ビッグ・ヒーロー6』 製作総指揮/ジョン・ラセター 配給/ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ 公開/14年12月20日
“サンフランソウキョウ”に住む天才少年ヒロ・ハマダは、兄タダシに見せられた工科大学のラボや、彼が作ったケアロボット「ベイマックス」に衝撃を受け、飛び級入学のための研究発表会に参加する。見事合格を勝ちとるが、直後に会場で火災事故が発生。残されたキャラハン指導教授を助けるべく、タダシは火の中に飛び込んでいった。兄を亡くした失意からヒロは心を閉ざしてひきこもるが、タダシが残したベイマックスと再会し、さらに自身が研究発表会のために製作したマイクロボットが何者かに悪用されていることを知り、タダシの死に隠された真相があるのではないかと疑問を抱く。ベイマックスのバージョンアップと、兄のラボの友人たちにパワードスーツや武器等を製作し、共に敵の陣へと乗り込んでゆく。
東京とサンフランシスコを合わせたような都市が舞台だったり、主人公たちが日本人とのハーフだったり、設定からして日本の要素が多く取り入れられた、ディズニーアニメ。
落合 『ベイマックス』は予告編の印象と全然違って【1】、『アイアンマン』(08年)万歳! と思っているような理系男子の話をアニメで作るとこんな感じかな、と思っておもしろく観ました。ヒロがキーボードを叩いて、3Dプリンタとレーザーカッターでなんでもつくれる万能キャラという非常にコンティニュアスに成功したナードとして描かれているのは新しいし、研究と開発が一体化していることに誰も疑問を抱かないところを見ると、観る人の科学に対する意識がアップデートされているのかなとも思えた。頭のいい奴が手を動かせば、そのままモノをつくれるというイメージがつくようになったのはすごくいいなと思う。登場人物たちが、極めてナチュラルにモノをつくっているんですよね。ディズニー映画の製作期間はだいたい4~5年くらいと聞くから、『ベイマックス』はちょうど2010年代前半につくられたとすると、ちょうどプログラマーという人が簡単に社会変革を起こすものをアウトプットできるようになった時期なんですよね。だから、このタイミングでこういう作品というのは必然なのかもしれない。
【1】予告編の印象と全然違って:日本で公開されていた予告編では「少年とロボットのハートフルストーリー」のように見せられていたが、実際のところはアメコミ原作だけあってヒーローものになっている。
宇野 ゼロ年代のディズニー/ピクサーだったら、兄貴がラスボスになっていたと思うんだよね。対象喪失のドラマという要素をもっと前面に出して、科学のつくる未来に絶望した兄貴と、科学の明るい未来を信じるヒロ君が対決する。単純に考えたらそっちのほうが盛り上がったと思うけど、今回のスタッフはその方向を取らなかった。個人的な動機に取りつかれた教授が暴走【2】する話になっていて、ヒロと科学をめぐる思想的な対立をしていないんだけど、そこは意図的にそうしたんじゃないかな、と。ピクサーの合議制のシナリオ作り【3】の中で兄弟対決が挙がらなかったわけはないんだよね。そういうあえて選択された思想的な淡白さが、今回のひとつのポイントだと思う。
【2】教授が暴走:事故で兄タダシと一緒に死んだと思われていたラボの指導教官。ロボット工学の天才博士が、ある個人的な動機に基づいてヒロの発明品を悪用しようとしていた。【3】合議制のシナリオ作り:ディズニー/ピクサー作品においては、複数のスタッフがストーリー会議を行って脚本をつくり上げているのが有名。
落合 もういまや科学技術批判が意味を持たない、ということが重要なんだと思う。科学技術批判、コンピューター批判してられないだろうっていうのは、『ベイマックス』のひとつの重要なファクター。今までの流れだったら、ヒロ君が作ったナノボットが知恵を持って暴走して人間に攻めてくる、みたいなシナリオもありだったと思うんですよ。でもそっちにはもういけないよね、と。
宇野 ピクサーは、特にジョン・ラセター【4】は『トイ・ストーリー』(95年)から一貫してイノセントなもの、たいていそれは古き良きアメリカン・マッチョイズムに由来する何かの喪失を描いてきた。アニメでわざわざ現実社会に実在する喪失感を、それも一度過剰に取り込んで見せて、そして作中で限定的にそれを回復してみせることで大人を感動させてきたのがその手口。『バグズ・ライフ』(98年)も『ファインディング・ニモ』(03年)も『Mr.イングレディブル』(04年)も『カーズ』(06年)も全部そう。そして『トイ・ストーリー3』(10年)は、そんなラセターのドラマツルギーの集大成で、あれは要するに観客=アンディにウッディとの別れを告げさせることで、ピクサーが反復して描いてきたものが映画館を出たあとの現実社会には二度と戻ってこないことを、もっとも効果的なやり口で思い知らされる。
しかし、その後のディズニー/ピクサーはこの達成を超えられないでいると思う。『シュガー・ラッシュ』(12年)はガジェット的にはともかく内容的にはほとんどセルフパロディみたいなもので、『アナと雪の女王』(14年)は、保守帝国ディズニーでやったから現代的なジェンダー観への対応が騒がれたけど、要は思い切って非物語的なミュージカルに舵を切ったものだと言える。そしてこの流れの中で出てきた『ベイマックス』は、ラセターが持っていた強烈なテーマや思想を全部捨ててしまって、ほとんど無思想になっている。単にこれまで培ってきた「泣かせ」のテクニックがあるだけで、これまで対象喪失のドラマに込められてきた「思想」がない。そこで足りないものを補うために、今回はアニメや特撮といった日本的なガジェットをカット割りのレベルで借りてきている。言ってしまえば、定式化された脚本術と海外サブカルチャーの輸入だけで、ピクサー/ディズニーの第三の方向性としてこれくらいウェルメイドなものがつくれてしまったということにも妙な衝撃を受けたんだよね。
【4】ジョン・ラセター:ピクサー設立当初からのアニメーターであり社内のカリスマ。06年にディズニーがピクサーを買収し、完全子会社化したことでディズニーのCCOに就任。ディズニー映画にも多大な影響を及ぼしている。
3つに分岐したCG表現の矛先
落合 『モンスターズ・インク』(01年)の頃までのピクサー映画は、いかに新しいレンダリング技術を取り入れて映画を作るかがサブテーマだったんです。『トイ・ストーリー』の頃はツルツルしたものしかレンダリングできなかったけど、『モンスターズ・インク』はモッサリした毛の表現ができるようになった。そこからしばらくはそうした技術の進化を楽しむ作品がなかったんだけど、『アナ雪』では雪のリアルな表現ができるようになった。あの雪の表現をつくるために書かれた論文があって、それなんか本当にすごい。雪をサンプリングして一個一個の分子間力を分析することで自然のパウダースノーをレンダリングするっていう。またこれで技術を見せる作品が続くのかな、と思ったら『ベイマックス』には何もなかった。だから、またそういう時代が数年続いて、その後にまったく新しいものが出てくるんだろうと思っています。
この記事の続きは、有料でこちらからお読みいただけます!
ニコニコで読む >>
noteで読む >>
noteで読む >>
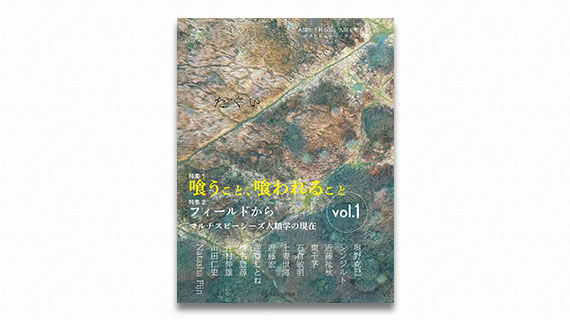
デジタルネイチャー時代の人類学 ──マルチスピーシーズが導く「制作論的転回」とは(前編)|奥野克巳(PLANETSアーカイブス)

『花子とアン』はなぜ「モダンガール」を描き切ることができなかったのか?|中町綾子×宇野常寛(PLANETSアーカイブス)

人間の「伸びしろ」を測定することは可能か? ──統計学的思考の教育への応用可能性 鳥越規央(統計学者)×藤川大祐(教育学者)(PLANETSアーカイブス)



もはやサブカルチャーは「本音」を描く場所ではなくなった――『バケモノの子』に見る戦後アニメ文化の落日(宇野常寛×中川大地)(PLANETSアーカイブス)

どこまでも遠くへ届くもの―― 宇野常寛、『ゴーマニズム宣言SPECIAL 大東亜論』を読む(PLANETSアーカイブス)

私は如何にして執筆するのを止めてアイドルを愛するようになったか――濱野智史が語る『アーキテクチャの生態系』その後(PLANETSアーカイブス)


木俣冬×宇野常寛 『真田丸』――『新選組!』から12年、三谷幸喜の円熟を感じさせるただただ楽しい大河の誕生(PLANETSアーカイブス)











