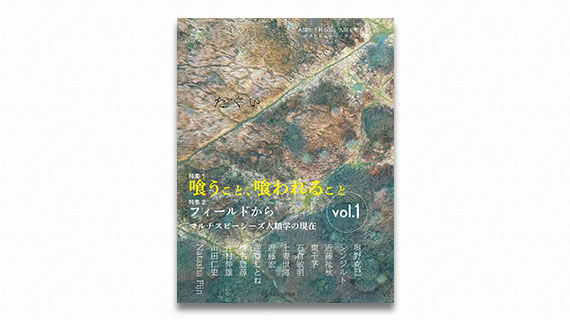ソーシャルネット時代のリアリティと「イスラム国」――日本人は”ヤツら”とどう向きあうべきなのか(軍事評論家・黒井文太郎インタビュー)(PLANETSアーカイブス)
今朝のPLANETSアーカイブスは、軍事評論家・黒井文太郎さんの「イスラム国」についてのインタビューです。90年代からビンラディンをはじめとしたイスラム過激派を追ってきたという黒井さんは、「ネットを有効活用して過激思想を広める恐ろしいテロ組織」とされる彼らのリアルをどう見ているのでしょうか――?(聞き手:中川大地、葦原骸吉+編集部、構成:葦原骸吉)
※この記事は2015年4月10日に配信された記事の再配信です。
■ バックパッカーからインテリジェンス研究へ
――黒井さんには、『PLANETS Vol.9』Dパートで、東京五輪に向けての治安・軍事面でのセキュリティホールを検証していただきました。その上で、本誌座談会ではポリティカル・フィクションとしてテロの可能性を検討したのですが、先進国社会が抱える共通したリスクとして、いわゆる「イスラム国(ISIS)」のような存在が、現在の社会に希望を持てない不満層にとっての駆け込み先になる可能性が無視できないのではないか。そんな話題が出ていた矢先に、例の邦人拘束殺害事件が起きたわけです。
そこで、今回は本誌での議論のフォローアップとして、『イスラム国の正体』という著書も上梓されている黒井さんに、イスラム国が出てくるに至った背景や、よく指摘されるインターネット普及との関連性、日本人がこの現象をどういう距離感で受け止めたらいいのかといったお話をうかがえればと思います。
まず、そもそも黒井さんはどのような経緯で国際インテリジェンス(情報機関・諜報活動)関係の仕事に就かれて、中東の武装集団に興味を持たれたのでしょうか?

▲『PLANETS vol.9 東京2020 オルタナティブ・オリンピック・プロジェクト』
黒井 もともと僕は、学生時代にバックパッカーをやっていて、その延長ですね。藤原新也さんとかが人気だった1980年代の中ごろで、『地球の歩き方』とかH.I.S.とかが出はじめたころです。それで、中南米のエルサルバドルやニカラグア、中東のイランとイラクの国境地帯などをよくうろうろしていました。当時、シリアの首都のダマスカスで安宿に泊まったら、何ヶ月も中東各地で現地調査している年上の日本人の大学生がいて、「これからちょっとPLOの事務所行くんだけど、黒井くんも来る?」という感じで、PLO事務所や難民キャンプなどに連れて行ってもらったんです。
この人は清水勇人さんという人で、すごい行動力があって、帰国後は政治家になって、今はさいたま市長をしています。僕は日本に帰ってから一度お会いしただけですけど、彼に出会わなければこういう道には入っていなかったですね。
――なるほど。冷戦時代の1970年代くらいまでは、それこそミュンヘン事件を起こした「黒い九月」と連携して日本赤軍もロッド空港での乱射事件を起こしたりとか、現在よりも日本人が中東のテロ組織と接点なりシンパシーを持つ土壌が強かったと思います。1980年代のバックパッカー文化の場合は、そういう政治的な意味でのシンパシーみたいな動機はあったのでしょうか?
黒井 あんまりないと思いますね。そこはもっと興味本位というか、秘境を旅しようという冒険心に近い感じです。当時は、アジアや中南米などで資源の買い付けをやってる現地採用の商社員にも、戦前の大陸浪人みたいな変な人がいましたよ。向こうの沈没組みたいなのが大手商社とかの名刺を持って、腰にピストルなんか下げて「飲みに行こう」とか言ってる。今はコンプライアンスの時代なので、そういう人は使わないで、情報収集や交渉は地元のコンサルタントや弁護士事務所に丸投げですけど……。
それで、僕は講談社の週刊『フライデー』編集部に入って、そこを辞めたあとフリーのライター兼カメラマンのような形で海外の紛争地の取材をしてました。冷戦も終わった1990年代の前半に日本に帰ってきたんですが、もう地域紛争が世界を変えるという時代でもなかったし、「次は何がテーマかな?」と考えたとき、当時はCIAなどのインテリジェンスやテロ問題は日本では他の人があまりカバーしていない世界だったので、興味を持ったんです。それで、イスラム過激派のテロなどを研究して、1998年に『世界のテロと組織犯罪』という最初の本を書きました。2000年からは『軍事研究』という雑誌の専属ライターになってます。
――インテリジェンスの専門家といえば、外務省出身の佐藤優や公安調査庁出身の野田敬生など政府機関のOBが多いですが、黒井さんの情報源はまったくの私的な人脈なのでしょうか?
黒井 僕は基本的に、自前の取材ではなくオープンソースから情報を集めてます。海外のジャーナリストや研究機関をどれだけフォローできるかが勝負みたいなところで、独自の人脈で「こんなネタ拾ってきました」というのは、あまり参考にならないです。フリーで戦場カメラマンみたいなことをやっていたころの後期、地元のジャーナリストや研究者、人権団体の人などから、いろいろと資料をもらっていたんです。そこから漏れる分は自分で洋書を買って調べたりしました。今だとネットでこういう情報ってすぐに集められますけどね。
当時、僕が調べていて、「これは面白いな」と思ったのが、アルカイダのビン・ラディンでした。9.11で注目される前ですね。『世界のテロと組織犯罪』では、その辺を詳しく書いていて、もともとたいして売れなかったんですけど、9.11後、すぐ売り切れました(笑)。
■冷戦後のリアリティを変えたアルカイダの台頭
――ビン・ラディンに興味を持たれたのは、どういう経緯だったのでしょうか。
黒井 90年代の半ばに僕は一時、カイロに住んでいたんですけど、「TIME」の記事で知りました。当時はエジプトですごいテロがあったんですが、その前から現地の研究機関やジャーナリストに話を聞いて、アフガニスタンのゲリラを支援しているサウジの大金持ちが居るという噂は何度か耳にしていてんです。
最初に「エコノミスト」というイギリスの雑誌で、五行情報くらいでその話が出たんですね。それで、あの噂ほんとうだな、と思って。どこかで誰か知らないかなと思ったんですけど、みんな具体例を知らなくて。そうこうしている間に、「TIME」の欧州版エディションにビン・ラディンのインタビューの記事が出たんですね。そこで初めて具体的なことを知りました。あれはアメリカ版とかアジア版には載ってないんですよ。当時は誰もビン・ラディンがどれだけ大物かは気づいてなかったので。
――その時点では、アルカイダっていう存在はどれだけの勢力だったんですか?
黒井 当時のアルカイダは、サウジアラビアを追われたビン・ラディンともどもスーダンのバシル政権というイスラム原理主義の政権にかくまわれていました。アフガニスタンにも仲間が残っていて、国際グループみたいなのを作っていましたが、勢力としては小さいです。
そこで農場をやったり工場をやったりして、元のアフガン義勇兵の連中を呼び集めて、会社を作って、仕事していたんですよ。みんなを食わせなきゃいけないので。そういう時期だったと思いますね。当時、彼が動かせる人は200人とか300人も居なかったと思います。
――なるほど……当然、僕らのような一般的な日本人がアルカイダを知ったのは9.11以後のことでした。ただでさえ映画みたいな衝撃的な事件で呆然としている間に、ブッシュ政権は瞬く間にビン・ラディンを指名手配して、またたく間にアフガンに攻め込んだという印象だったので、多くの日本人は戸惑うばかりだったと思います。あれはアメリカの自作自演だったのではないかという陰謀論まで、当時はしきりに囁かれました。
しかし今、黒井さんたちのような形で情報を追っていた人たちからすると、すでにその時点で感じているリアリティの違いがあったのではないかと。9.11が起きたときに、ビン・ラディンが特定されていく経緯というのは、黒井さんたち的には納得だったんでしょうか?
黒井 テロを追いかけてる人から見れば、あれがアルカイダの仕業だろうなっていうことは一発でした。1998年にケニアとタンザニアでテロをやって、最終的にアメリカを狙っているのはみんなわかってましたから。在韓米軍が狙われるんじゃないか、みたいな噂はけっこう出てて、どこかの国で、アメリカ大使館とかを狙ったりっていうのをそろそろまたやるだろうっていうのは、みんな思ってたんですね。
ただ、アメリカ本土でああいうハイジャック型の大規模な事件になったことには、意表を突かれました。だからあの事件が起きたときには、これはもうアルカイダ以外にないな、というのはすぐにみんなが考えることでした。当時、DFLPっていうパレスチナのゲリラがやったんじゃないかっていう第一報が流れたんですよ。そういう問い合わせが僕も新聞社から来たんですけど、「それはありえないです。アルカイダで間違いありません」って言ったのは覚えています。
――つまり、90年代の時点ではわずかな勢力でしかなかったけれど、2001年の時点では、そこまで確信を持てるほど急速な盛り上がりがあったわけですね。
黒井 1996年にアフガニスタンに戻って、タリバンと手を組んだのが転機ですね。ちょうど僕の最初の本が出た頃に、アルカイダはあちこちのイスラム過激派と連携して、十字軍と戦う世界イスラム軍だみたいな旗揚げをして、これからアメリカをやるぞって宣言したんですね。そのときに僕らの間では注目度が高まったんです。当時は、アルカイダって言い方はあまりしてなくて、ビン・ラディン派の連中はこれからどんどんやるぞという雰囲気が、98年くらいから盛り上がっていた。
――逆にそういう情報に対して、日本でのニーズはどうだったんでしょう。
黒井 ないですよ。だから、軍事雑誌でしか扱ってくれないんですね。
――つまり、赤軍派の時代とは違って、日本人にとってはテロというの自分の生活とは基本的には関係のない、マニアックな趣味の情報としてしか捉えられていなかった時期が長く続いていた、と。
黒井 日本だけじゃないですけどね。9.11後にアメリカが調査委員会を作って検証しているんですけど、おもしろいなと思ったのは、アメリカの情報機関ですら冷戦の終結後はテロへの警戒をやめてしまっているんですね。90年代にはCIAやFBIなんかも「テロ対策はもういいだろう」と、麻薬組織関係に人員をシフトしていったりだとか。CIAの「テロ対策センター」という本丸の組織でも、ビン・ラディン班なんて10人とかそこらの規模です。そこの人たちはさすがに「これからこいつらが危ないぞ」と声を大にして言ってたんですけど、CIAの中で誰も話を聞いてくれず、傍流の傍流あつかいをされていました。アメリカはニューヨークの貿易センタービルの地下駐車場を爆破されたり(1993年)とか何度かやられてるんですが、それでも大して動いてないです。
なんとなく冷戦終わったし、もうこれからあまり危ないことないんじゃないか、という油断はアメリカの中でもありました。そういう背景があったので、9.11はアメリカにとっても晴天の霹靂でした。
――とはいえ、中東地域では、紛争はずっと続いていたと思うんですね。
黒井 でも、ちっちゃかったですね。前は、大きな紛争がいくつもあって、イスラエルの話もそうでしたけども、戦争も起こったし、それぞれバックにソビエトとアメリカが居て、イスラエルが動いてみたいなガチンコだったんですけども、冷戦が終結してからあのへんもけっこうフラットになったんですよ。
その後には湾岸戦争があって、それが終わった頃からは、ここからもう大きな戦争はないだろうっていうような空気で、やっぱりシリアとかイラクとか、カタフィーのリビアとかもそうですけども、90年代以降になってから、わりとみんな大人しくなるんですよ。もう冷戦が終わってソビエトが助けてくれないから、アメリカと喧嘩してもしょうがないだろうということで、戦争ないし平和だよねみたいな空気が、アラブでも90年代以降には主流でした。
――それは、今の空気とはまったくちがうことですよね。やっぱり9.11がきっかけだったという理解で良いのでしょうか。
黒井 そうですね。ただ、9.11はアルカイダが突出しすぎたので、あれの模倣犯はけっこう出たんですけども、アラブ世界があれで反米になったというわけではなかった。「アメリカが悪い」というよりは「テロの人すごいね」みたいに、アラブの中でもちょっと他人事みたいなところがあって。 反米ブームが一気に来たのは、むしろ2003年のイラク戦争以降のことでした。
■ イスラム過激派は「幕末の志士みたいな意識高い系」?
――そこでアルカイダが、反米グローバル・ジハードの急先鋒という権威を獲得して、それまでになかった世界的な象徴性を帯びていったと思うんです。そこには、国境を超えるネット利用の効果が大きかったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
黒井 そもそもアルカイダは、ネットで人を集めていたわけではなくて、イスラム教の説法や軍事訓練風景などのビデオCDなんかを直接配ってました、今のイスラム国のものに比べればずっと手づくり感満載のものです。中東やヨーロッパなど各国のモスクにアジーテーターみたいな人がいて、人脈ネットワークでオルグしていくのがほとんどでしたね。それで「お前、やる気ならパキスタンに行ってみろ」と言われた人がビン・ラディンに会って「がんばれ」とか言われて帰ってくるみたいな感じです。あとは「俺の友だちがメンバーにいるから、お前も集会に来いよ」といった口コミによる紹介で人を集めて、そこで急にテロをやろうと決めたりする。それで終わったら「じゃあね」って言って、次の友だちに会ったら別のグループに行ったりとか、そういうのが普通にある。
――口コミから国際的なネットワークになっていくのが、日本人の感覚からすると意外ですよね。
黒井 日本人のイメージするテロ組織、たとえば、赤軍派やオウム真理教はガチっとした規律があって構成員が決まってる感じですけど、中東はもっとゆるいんですよ。パレスチナ人のグループもいっぱい派閥があって、アラファト派とアブ・ニダル派がケンカしてたりしたんですけど、アブ・ニダル派の人が明日からアラファト派に行くって言っても、「おお、そうか、がんばれよ」と言われるような雰囲気なんですよ。彼らは、なんとか解放戦線とかいう組織名もほとんど知らないで、ボスの名前でグループを呼んでるんです。自民党の宏池会とか清和会とか言ってもよくわかんないけど、安倍派とか言ったらわかるみたいな感覚に近いんですよね。だから、アラブの過激派のメンバーは、自分の所属組織の政策とか綱領なんか誰も気にしていません。それも自民党と似てますね。
9.11テロのプロットを考えたのはハリド・シェイク・モハメドという男で、彼は若いときからテロをやりたくてやりたくて、1993年に起きたアメリカの世界貿易センタービル爆破事件などを仕掛けた人物ですが、ビン・ラディンにすごいライバル意識を持っていたんですね。行動力はあるんだけども、お金も子分も持ってないから、世界じゅうを渡り歩いて「お前ら一緒にやらないか」みたいにオルグをしてる。それでも自前では限界があって、最終的に9・11テロの計画をビン・ラディンに売り込みに行って、ビン・ラディンをある意味で“引きずり込む”のに成功するのです。それこそ、長州や薩摩の尊皇攘夷志士の間で顔つなぎ役をしてた坂本龍馬みたいな感じですよ。
▲ハリド・シェイク・モハメド
――それは面白い表現ですね。そういった「テロ浪人」のようなイスラム過激派というのは、もはや貧困ゆえのテロというより自己実現的な意識なんでしょうか。
黒井 彼らは悪い意味で、非常にロマン派ですよ。テロリストの人たちは、承認欲求がすごい強くて、イスラム教徒全般にウケることをしたいというモチベーションが高い。評価されたいんですよ。それを命がけやってます。それで、たとえばアフガニスタンのキャンプに世界中から賛同者を集めて軍事訓練をして、「あっちこちでアメリカ人殺したらすげえ楽しいぜ」みたいな感じで世界に散らしてる。昔の幕末志士や、世界革命を唱えていた左翼もそういう面があったでしょう。
――ネットの普及がそれを後押しするようになった面はあるでしょうか?
黒井 ツールとしてはあると思います。ただ、よく勘違いされていると僕が思うのは、イスラム国もネットを使ってますけど、ネットありきで始まった運動ではなくて、ただ便利だから使ってるっていうことなんです。ヨーロッパあたりからイスラム国に行ってる連中には「ネット見ました!」という人もいますが、実際は、EU圏内で「イスラム国はいいぞ」とアジってる過激なイスラム説法師などの紹介で来る人の方が多いです。どうもイスラム国報道ではネットが誇張されている気がしますね。
――もしイスラム国が片付いても、そういう、かつての志士気取りのようなテロ志願者の受け皿は別の場所にまた現れると思いますか?
黒井 イスラム過激思想自体はなくなりはしないです。ただ、時々こういう感じでテロの流行はくるでしょうけれど、集まってきた人たちも、上手くいかないとだんだん現実に適応していくんですね。かつての左翼もそうです。学生運動がバーッと盛り上がって、その内のいくつかの勢力がテロに走りましたけど、「どうせ社会は変えられない」と、おおかたの人は就職して辞めていってしまう。でも、辞めない少数派がまた違う形で始めたり……それの繰り返しですね、テロは全部そうです。
■ イスラム国のネット利用はむしろ下手だった?
――アルカイダは明確な拠点がない国際ネットワークのまま転々と活動していましたが、そこから影響を受けながら勢力を伸ばしていったイスラム国が、領域的に浸透したのはなぜでしょうか?
黒井 それはやっぱり、2011年の「アラブの春」以降のシリア内戦と、イラクからの米軍撤退で、この両国がぐちゃぐちゃになったからですね。本当に偶然ですよ。
――まさに「アラブの春」では、インターネットが独裁打倒に寄与しましたが、皮肉にもそれがイスラム国の台頭を招いてしまった。軍事的なリアリズムから見ると、テクノロジー環境の進歩自体は社会の改善につながらないのでしょうか?
黒井 でも、ネットがなければ「アラブの春」は起こってないですよね。昔であれば反政府運動を唱えてもすぐ弾圧されちゃうけど、それが、携帯などで連絡を取り合って動いたとか、彼らを支える自由な言論空間が出現したとかいう点はやっぱり大きい。情報化が進んだので一方的な統制みたいなものが効かなくなってますから、独裁が崩れていくのは歴史的な必然なんだろうなと思います。僕はシリアで反政府運動を仕掛けた人たちを知ってますが、彼らは最初のデモのときから、ネットを使えば世論が盛り上がるし、世界も見てるから民主化されるだろうという戦略で、隠しカメラも使って撮ってるんです。それで、アサド政権による虐殺などの情報をたくさん流して、国際社会が自分たちを助けてくれると期待した。実際には裏切られてしまったわけですが。
けれども、そうして現地の情報が世界に流れたことで、イスラム国ができる前の早い段階から「シリア人を助けよう」という義勇兵がいっぱい来てるんですよ。そもそもはそういう人道的な動機で来た人たちがイスラム国に流れてるんですね。今後は、たとえばウクライナなど、どこかで紛争が起こったらネット経由で「世直し義勇兵」みたいな意識で参加する人は間違いなく増えると思いますね。
――ネットの利用がそうした人道的な動機に合致することもありますが、一方でイスラム国は斬首映像をYouTubeにアップしたり、残虐性を強調していますね。あれは実際に宣伝効果が高いのでしょうか?
黒井 僕は逆効果だと思うんですよ。ああした残虐性は、戦略として洗練されているとは思えません。普通だったら残虐な面を出さずに「自分たちは正義の味方だ、ホラ、捕虜も改心して仲間になってるから、一緒に戦おう」なんて感じのプロパガンダの方がよいはずです。昔の中国共産党がそれが上手かったですね。