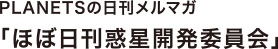『ドラがたり――10年代ドラえもん論』(稲田豊史)第6回 ふたりのファム・ファタール 後編
本日は稲田豊史さんの連載『ドラがたり』をお届けします。2回にわたってお届けしている「しずか・ジャイ子」編ですが、今回は篠原ともえ・光浦靖子・前田敦子という「ジャイ子系女子」の系譜を辿りつつ、「なぜしずかは出木杉ではなくのび太を選んだのか」というドラえもんシリーズ全体を貫く謎について考察します。
●サブカル女子のプロトタイプ:ジャイ子系女子
前回【第5回】は、『ドラえもん』の作中で唯一「セクシャリティ」を託されたしずかと、唯一「成長」を託されたジャイ子が、作中でどのように描かれていたかを例証した。
連載が晩年期に差しかかった90年代、女子がしずかのように類型的かつ前時代的な「オーソドックスな昭和マンガ的マドンナ」の属性を追い求めることでサバイブできるような時代は、既に去っていた。「やきいも好き」を隠す程度のイメージコントロールで、スクールカーストの上は目指せない。そもそも、持って生まれた容姿がしずかレベルにある人間は限られており、「カワイイ」だけで世を渡ろうとするしずか流サバイブには、まるで現実感がなくなったからだ。
代わってその実用性を買われたのが、手に職(マンガを描く能力)を持って世界に立ち向かう、ジャイ子流サバイブという方法である。ブスでガサツ、忌み嫌われる当て馬キャラ、のび太にとって「失敗した未来」の象徴として創造されたジャイ子は、長い年月をかけ、「容姿には難ありだが、一芸に秀でた女子」として、ようやくまともな人権を得た。そんなジャイ子の最終的な成長段階が描かれたのは、「小学六年生」1990年8月号に掲載された「ジャイ子の新作まんが」(てんコミ44巻収録)である。
しかしジャイ子というキャラクターの本質は、おそらく作者の藤子・F・不二雄も予想だにしなかったかたちで、90年代以降の日本社会において“市民権”を得ていくことになる。
90年代半ばのこと。突如「ジャイ子系女子」とでも呼ぶべき10〜20代の女子クラスタが、日本全国で同時多発的に出現した。おもな生息場所は高校や大学の文芸部、漫研、演劇部など。美大進学者ほか、写真系、服飾系、デザイン系専門学校生にもよく見られた。
彼女たちの見た目は、ぽっちゃり体型の低身長。言葉を選んで慎重に形容するなら、「顔面偏差値に際立った優位性は見いだせない」娘たち。そんな生来的な容姿のビハインドを、カギカッコ付きの“個性”やサブカルに代表されるマニアックな情報の武装をもってカバーする彼女たちは、近年で言うところの「文化系女子」「サブカル系女子」「腐女子」などの予備軍にしてプロトタイプ(原型)だった。
彼女たちは、自分たちが持ち得ない「男子受けする容姿・女子力」以外のスペックを異常発達させることで、居場所とアイデンティティを確立し、社会をたくましくサバイブしていった。その姿はまるで、「およそ小学校中学年が読まないような作品をマニアックに読み解き、かつオリジナルを創作する能力」という一芸を武器に人権を取り戻していった、ジャイ子の勇姿をも彷彿とさせる。
女子の類型を歴史的・体系的に論じた松谷創一郎氏の著書『ギャルと不思議ちゃん論 女の子たちの三十年戦争』(原書房、2012年)にも、「美大のジャイ子」が登場する。1994年、美大に入学した松谷氏がキャンパスで遭遇した彼女の特徴は、「たしか短大のデザイン系の学科」「背が低くて太っていて」「ジャイ子とよく似たルックス」「篠原ともえのような幼児的な格好」「本人もジャイ子と自称していたそうだ」「日々躁状態」と説明される。
複数の友人から「うちの学校にもジャイ子がいた」と聞き、「さまざまな高校や大学に、それぞれのジャイ子がいたのだ」とする松谷氏は、ジャイ子のくだりをこう結ぶ。
国民的マンガをリソースとした“ジャイ子”は、「イケてるわけではないが、だれに対しても存在感をアピールできるキャラ」として機能する。それはイケてるキャラクターを目指すことなく、かと言って“地味な存在”として生きることには抵抗した、不思議ちゃんのひとつの生き方だったのだろう。(松谷創一郎・著『ギャルと不思議ちゃん論 女の子たちの三十年戦争』P.155より)
実際、90年代半ばを10代で過ごした筆者の周囲にも、文字通りジャイ子のごとき「小太り・黒髪おかっぱorマッシュルームカット・ベレー帽」といういでたちのジャイ子系女子がいた。愛知県の公立高校の同級生に1人、横浜の四年制大学のキャンパスにちらほら。特に大学には建築学科があり、『スタジオ・ボイス』を熟読しつつ都内の美大生と交流するような“感度の高い学生”が多かったため、ジャイ子系女子が生まれやすい環境だったのかもしれない。
●救済者としてのシノラー
サブカルに傾倒し、ファッションや言動が“個性的”な彼女たちの一部は、松谷氏も指摘するように「不思議ちゃん」と呼ばれた。
1995年にデビューし、90年代後半にテレビを中心として強烈な存在感を残した「シノラー」こと篠原ともえも、この文脈で言及しておくべきだろう。当時10代後半だった彼女は、短いぱっつん前髪と珍奇なファッションに身を包み、異常なハイテンションでスタジオの大人たちを戸惑わせていた。
初期のジャイ子系女子にサブカル要素が不可欠だとすれば、彼女たちにとって篠原はうってつけの心情的ロールモデルだった。歌い手・パフォーマーとしての篠原をプロデュースしたのは電気グルーヴの石野卓球。電気クルーヴは、前身であるバンド「人生」時代からインディーズシーンでは名の知れた存在であり、当時のサブカル界における有力レーベル「ナゴムレコード」の中核をなす人気バンドだった。篠原は生まれながらにして、血統正しき「ザ・サブカル女子」だったのだ。
篠原は、当時のジャイ子系女子にとって救済の受け皿としても機能した。男受けする容姿でなくとも、“個性オシ”でキャラクターを作り上げてしまえば、いっぱしのアイデンティティと自尊心は獲得できる。彼女たちは、はなから望めない「男子受け」要素を自ら完全放棄し、歪な幼児性をたたえたお団子頭やサスペンダー、羽根つきランドセルや極彩色の靴下などで、自らの「メス性」を完全に塗りつぶしたのだ。
ロリコンの劣情を催させる美少女子役が「チャイドル」などと呼ばれていた90年代中盤から後半、篠原およびそのフォロワーたちは、決して男子の(一般的な)性的対象にはなりえなかった。否、なろうとしなかった。おもしろ系の飛び道具キャラとして、教室内ジェンダー的な意味での「女子」にカウントされることを拒み、キャラとしてのジャイ子を地で行った。それが、「容姿に恵まれない、小太りな彼女たち」なりの、やっと見つけた生存戦略だったからだ。
教室内の一般的な評価軸に頼るだけではスクールカーストの上位に登れない女子が、生き残る道として「シノラー≒ジャイ子系女子」キャラを選択し、既存の評価軸で計測されることに徹底抗戦する。それは、「のび太の失敗結婚相手」として創造されたジャイ子が、「マンガ」という特殊能力を駆使して、別の評価軸を独力で獲得したプロセスと同じ旋律を奏でているようにも見える。
モデルの市川実和子を筆頭に呼称された「ブスカワイイ」「ブスカワ系」という身も蓋もない言葉が生まれたのも 90年代半ば頃だ。要は「異性に媚びるモテカワ系ではなく、同性に好かれる・愛嬌のある・個性的な造作のご尊顔」を一言で言い表した形容である。
ブスカワ系モデルが活躍していたのは、『CUTiE』『Zipper』などのストリートファッション誌、いわゆる青文字系雑誌だ。『JJ』『CanCam』といった男ウケ至主義的な赤文字系ファッション誌とは対極をなすこれらは、誌面で「男子に媚びない・サービス精神でメス性をアピールしない・モテより個性重視」(筆者意訳)の信条を掲げ、ジャイ子系女子を含む多くの女子たちの支持を得た。
このように、ブスを個性と読み替えるムーブメント……もとい、容姿より一芸を売りにする女子ムーブメントが若者文化空間内に吹き荒れたのが90年代後半である。その端緒にしてコンセプト上のルーツを、1990年の「小学六年生」に描かれたジャイ子に求めることは、十分に可能だ。
なお、1979年3月生まれの篠原は1990年時点で11歳。当時ちょうど小学六年生であった。
●ジャイ子と光浦靖子
ジャイ子系女子が新たなる評価軸(という名の市民権)を獲得していったことに追随してか、オフィシャルの『ドラえもん』においても、ジャイ子の地位向上がみられた。2001年の劇場公開短編作『がんばれジャイアン』での扱いである。
本作は原作におけるジャイ子と茂手もて夫(のちにジャイ子と同人誌仲間になる小学生男子/原作にも登場)との出会いをベースにしたオリジナルストーリー。物語自体はジャイアンとジャイ子の兄妹愛を描いた感動系のイイ話だが、問題はジャイ子のキャラクターデザインである。驚くべきことに、ジャイ子が「かわいい」のだ。
『がんばれジャイアン』で画像検索していただければ一目瞭然だが、キービジュアルのジャイ子は、アイドルが写真館で撮ったブロマイドのように愛嬌たっぷり。原作の無愛想かつクール、ミニマムな線でソリッドに描かれたジャイ子の造作を見慣れた者としては、違和感が拭えない。正直、気持ち悪い。
また、劇中のジャイ子は原作の後期同様、健気な努力女子として描かれているが、「兄思いの妹属性」が異常に底上げされている点も気になる。冒頭、ジャイアンに原稿を奪われたジャイ子がジャイアンを追いかけるが、ジャイアンが信号待ちで足止めされるのを見るや、ジャイ子は距離を詰めずにその場で足踏みするのだ。『トムとジェリー』の「仲良くケンカしな」状態である。
このようにして「疎まれる存在としてのブスな女の子」は、ジャイ子系女子の発生という潮流を経由し、最終的には「公式が追認する」形をとって、「愛嬌のある文化系少女」としての地位を獲得する。
記憶に頼る形で恐縮だが、揶揄も含めた「サブカル女子」のルックスアイコンのひとつに、「ベレー帽+黒髪おかっぱ」が加わったのもゼロ年代初頭、この頃ではなかったかと思われる。
『がんばれジャイアン』公開以降、「ジャイ子的なるパーソナリティ」の社会的許容範囲は広がっていった。それは、乙女ゲーやBL好きといった「腐女子」の一般的認知度向上にも寄与してはいないだろうか。また、文化的素養部分から切り離した「見た目のビハインド」だけに着目するなら、10年代以降、小太り女子を「マシュマロ女子」「ぷに子」などと言い換えて半ば強引に持ち上げた一部女性誌の風潮に、その残滓が確認できなくもない。