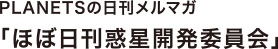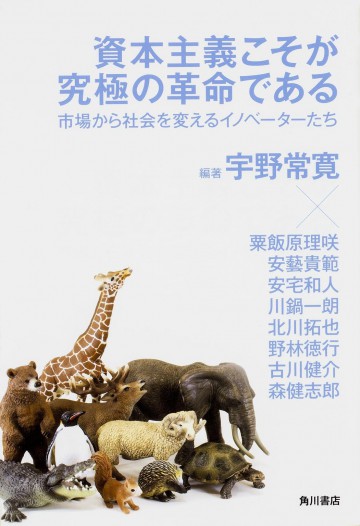「速さ」がデザインに宿るとき、伝説が生まれる――誇り高きサムライ、国産スポーツカー【前編】(根津孝太『カーデザインの20世紀』第8回)
この連載は『カーデザインは未来を描く』として書籍化されています!
今朝のメルマガではデザイナー・根津孝太さんの連載『カーデザインの20世紀』をお届けします。今回は前後編に分けて、国産スポーツカーを取り上げます。前編では、日本が世界に誇る名車を紹介しながら、スポーツカーという存在の意外な本質に迫ります。
今回からは前後編にわたって日本のスポーツカーを語ってみたいと思います。
やや勢いあまって、中二病的なタイトルをつけてしまいましたが、「スポーツカー」という言葉を聞いて、みなさんはどんなことを思い浮かべるでしょうか。
車に詳しくなくても「なんとなくカッコいい」「高級品だ」というイメージを持っている人、現在であれば「速いだけで燃費の悪い使いにくい車に乗っているなんてカッコ悪い」と思う人もいるかもしれません。
でも僕は、スポーツカーは単なる過去の流行ではなく、人類の根本的な欲望に根ざした存在なんだと思っています。
「スポーツカーに乗る」ということには、特別な意味があります。美しい車への憧れや所有欲、速い車を乗りこなしてみたいという衝動が、人をスポーツカーに向かわせるのはもちろんですが、それだけではなく、そこには「身体の機能を補いたい、拡張したい」という欲望もあるような気がします。僕もそうなのですが、走るのが遅い人が速いスポーツカーに憧れるというように、身体の拡張感とそれによる高揚感や陶酔感がスポーツカーの魅力の根本にあることは確かではないでしょうか。パワードスーツや、ガンダムのモビルスーツへの憧れと同じものと言っていいかもしれません。かなり偏った考え方だとは思いますが、今回はこのような視点からスポーツカーを考えてみたいと思います。
▲パワードスーツ。身体機能を強化する。SFによく登場するが、近年は実用化が進められている。(出典)
人間はどこかで、自分の尊厳を保てる場所を作りたいのだと思います。他のところでは負けても、いや負けているからこそ、ここでは勝ちたい。そんな思いの受け皿として機能してきたのが、スポーツカーというジャンルなんだと僕は思っています。
日本は自動車大国でありながら、スポーツカーの分野では欧米の後塵を拝してきた国でもあります。しかしそんな日本で生まれたスポーツカーにも、世界に誇れるものはたくさんあります。今回は、そんな日本の「サムライ」たちを語っていきたいと思います。
■スピードを追い求めるという原初の欲求
スポーツカーは、もともとレースなどのモータースポーツのために開発されたものでした。その歴史は古く、自動車の誕生とほぼ同時に生まれています。
▲20世紀初頭のレーシングカー。ペイントのカーナンバーがレースらしい。(出典)
スピードを追い求めるということ自体、人間のプリミティブな欲求に根ざしています。人類は車輪の発明以前から、動物に乗ったり、そりのような原始的な乗り物で坂を下ってレースをしていました。スポーツカーも「どうやったらより速くなれるか」を追求していく上で、自然に生まれてきた存在です。
エンジニアリングで速さを追求していくと、乗り物のデザインもどんどん変わっていきます。例えば自転車はわかりやすい例でしょう。チェーンドライブが発明される以前の自転車は、ペダルの一回転がそのまま車輪の一回転になっていました。車輪が一回転したときに進む距離は、円周の長さに等しくなります。円周は直径に比例しているので、車輪が大きければ大きいほど速いということになります。この時代の自転車は、前輪の大きなデザインがスポーティで「速そう」なデザインとして受け入れられていたのです。
▲前輪が大きな「オーディナリー型」と呼ばれる自転車。19世紀後期に流行した。重心が高いため乗りこなすのは大変だったというところもスポーツ的。(出典)
事情は自動車も同じで、実際にモータースポーツで活躍している「速い」車であること、そしてデザインとしては「速そう」であることが何より大切です。さらに言えばそこに思い入れやストーリーが宿っていることが、スポーツカーの条件だと言えます。
■世界が認めた国産スポーツカー「トヨタ 2000GT」
日本のスーパースポーツカーの元祖と言えば、1967年に登場した「トヨタ2000GT」は間違いなくそのひとつと言えるでしょう。連載の第1回でもお話ししましたが、僕が小学生の頃はスーパーカーブームが盛り上がっていた時期でした。でも華々しく取り上げられるのはイタリアやドイツ、イギリス、アメリカなど海外の車ばかりで、国産のスポーツカーはあまり目立っていませんでした。
僕が小学生だった70年代後半は『サーキットの狼』という、実在するスーパーカーがたくさん登場して公道やサーキットで命を賭けたレースを繰り広げる漫画が大人気で、当時の男子小学生の多くが読んでいました。その『サーキットの狼』の作中で隼人・ピーターソンというキャラクターの愛車としてトヨタ2000GTが登場したのが最初の出会いです。作中でピーターソンが、外国製のスポーツカーに乗る主人公たちに向かって「日本にもすばらしい車があるのに、なんできみたちは外国の車に乗るんだ?」というようなことを言うシーンがあるのですが、「日本にもスーパーカーがあったんだ!」と興奮したのを覚えています。
▲トヨタ 2000GT。ヤマハ発動機の技術供与により完成した。流麗なデザインは現代の視点から見ても古臭さを感じさせない。(出典)
▲京商オリジナル 1/43 サーキットの狼 トヨタ 2000GT 隼人ピーターソン。ちなみに隼人・ピーターソンは一人称が「ミー」の悪役として登場する。(出典)
さらにこのトヨタ2000GTは、映画『007は二度死ぬ』(1967年)でボンドカーにも抜擢されています。それまで『007』シリーズのボンドカーはアストンマーチンやベントレーなどのイギリス車だったのですが、外国の車がボンドカーになったのはこれが最初でした。トヨタ2000GTは、プライドの高いイギリス人も納得させられるような美しさを持っていたということなのかもしれません。
▲主演のショーン・コネリーが長身で窮屈だったため、オープン仕様となった2000GT。『007は二度死ぬ』はボンドガールも日本人だった。(出典)
デザイン的には、似ているものが他にないかというとそうでもありません。こうしたノーズが長くてキャビンが後ろにある構成は、当時のスポーツカーとしては一般的なもののひとつでした。現代のスペース重視の車では、エンジンを横置きして前輪を駆動し、走るための機構をギュッと車両の前方に追いやって、その分、広い室内空間を確保するのが普通です。しかしこの2000GTでは、エンジンを堂々と縦にレイアウトし、それを内包する長いノーズを、どうだ!と言わんばかりにスタイリングの特徴にしています。運転席に座れば、助手席との間を隔てるトンネルに、エンジンからの力を伝達するトランスミッションとプロペラシャフトの存在をしっかりと感じとることができます。このスタイルがスポーツカーとしての理想的なレイアウトのひとつであり、典型的な記号でもあったのです。
もちろん走行性能も高く、過酷なスピード・トライアルにチャレンジし、国際記録を幾つも樹立しています。スター性と実力、その双方を兼ね備えた日本のスポーツカーとして、僕にとってはすごく輝かしい存在でした。
僕は決してナショナリストというわけではありませんが、日本車が世界市場で活躍していると、どうしても嬉しくなってしまうんですね。イチローや松井秀喜、中田英寿の海外での活躍を見る喜びにも似ているかもしれません。日本人は自分の作ったものを自分で認めるのが苦手なので、こうして外から認められることでようやく価値をはっきりと認識できる、ということもあるように思います。
■この車だけが未来のエンジンを積んでいた――「マツダ サバンナ RX-7」
トヨタ2000GTは、70年代後半当時は既に生産を終了していた「幻のスーパーカー」でした。しかし、スーパーカーブームの後半の1978年、もう一台の国産スーパーカーが登場しました。それがこの、マツダ「サバンナ RX-7」です。
▲マツダ サバンナRX-7。(出典)
この車の最大の特徴は、ロータリーエンジンという特殊なエンジンを搭載していることです。これはおむすび型のローターが8の字で回るというとても不思議なものです。一般的な自動車に搭載されているレシプロエンジンはピストンの上下運動をクランク軸を使って回転運動に変えているのですが、このロータリーエンジンは最初から回転運動なので効率がいいと言われていました。実際は燃費の点で不利な点もあったりするのですが、高回転域までスムーズに回り、軽量コンパクトで高出力なことからも「未来のエンジン」として持て囃されていました。
▲ロータリーエンジンの動作。おむすび型の頂点に位置する気密用の「アペックスシール」の開発が難航した。(出典)
アイディアとしては第二次世界大戦当時からある古いものです。当初、ドイツでは低振動・低騒音であると見込まれ、戦車に搭載すれば、搭乗員の疲労を減らし、作戦行動時間を延長できるのではないかと構想されました。そして戦後の1964年に、西ドイツ(当時)の自動車メーカーであるNSUがロータリーエンジンを搭載した自動車を開発しましたが、故障が多く実用化というにはほど遠いものに終わっていました。つまり当時の世界の技術力をリードしていた西ドイツでさえ量産には成功しなかった、いわく付きのエンジンなんですね。
それをなんと、日本のマツダが1967年に完成させ、「コスモスポーツ」というスポーツカーに搭載して発売してしまったんです。『帰ってきたウルトラマン』に防衛隊の特殊車両として登場するので、特撮ファンの方にはおなじみかもしれませんね。そして、そのコスモスポーツの正統な流れをくむサバンナ RX-7が、スーパーカーブームの真っ只中に彗星のように登場するのです。当時の小学生たちのスーパーカーか否かの判断基準はややお粗末で、使用しない時には収納される「リトラクタブルヘッドライト」(当時の通称は「隠しライト」)がついているかどうかが最大の影響力を持っていました。サバンナ RX-7にはまごうことなきリトラクタブルヘッドライトが搭載されていますから、間違いなくスーパーカーに分類されるわけです。
しかもスーパーカーとしては非常に安い価格で販売されたところもポイントです。僕が通っていた小学校の先生が、サバンナRX-7を買って学校に乗って来ていて、それまでなんとも思っていなかったその先生が急に神様のように見えたのを覚えています(笑)。当時の公立学校の先生のお給料ですから、それほど高いというわけではなかったと思いますが、それでも頑張れば買えるくらいの価格だったんですね。「実際に手の届くスーパーカー」というそれまでには考えられなかったプロダクトだったんです。ちなみに、僕も小学生ながらディーラーに行ってカタログをもらってきたりしました。