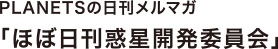ライフスタイル化するランニングとスポーツの未来 『走るひと』編集長・上田唯人×宇野常寛・前編(毎週金曜配信「宇野常寛の対話と講義録」)
今朝は、雑誌『走るひと』編集長の上田唯人さんと宇野常寛の対談をお届けします。東京マラソン以降現れたアスリートとも、かつてのジョギングブームで走っていたランナーとも異なる、新しいタイプの「走るひと」たち。体育とは違うランニングのあり方や、自分の物語性が求められるようになったスポーツの現在、そして2020年の東京オリンピックとスポーツの関係について語りました。
▼雑誌紹介
雑誌『走るひと』
東京をはじめとする都市に広がるランニングシーンを、様々な魅力的な走るひとの姿を通して紹介する雑誌。いま、走るひととはどんなひとなのか。プロのアスリートでもないのになぜ走るのか。距離やタイム、ハウツーありきではなく、走るという行為をフラットに見つめ、数年前とはひとも景色もスタイルも明らかに異なるシーンを捉える。 アーティストやクリエイター、俳優など、各分野で活躍する走るひとたちの、普段とは少し違った表情や、内面から沸き上がる走る理由。もはや走ることとは切っても切れない音楽やファッションなど、僕らを走りたくてしようがなくさせるものたちを紹介。
待望の第3弾となる『走るひと3』(2016年1月16日発行)は、発売後まもなくAmazonカテゴリー新着「1位」、総合「19位」をつけるなど、大変な好評を博している。
https://instagram.com/hashiruhito.jp
https://twitter.com/hashiruhito_jp
▼プロフィール
上田唯人(Yuito Ueda)
走るひと編集長 / 1milegroup株式会社 Founder CEO。早稲田大学在学中にアップルコンピューター(現Apple Japan)にてipodのプロモーション、上場前のDeNAで新規事業に携わる。卒業後、野村総合研究所に入社、企業再生・マーケティングの戦略コンサルタントとして、主にファッション・小売業界のコンサルティングを行う。その後、スポーツブランド役員としてファイナンス・事業戦略・海外ブランドとの事業提携などを手がける。
2011年7月、1milegroup株式会社を設立。『走るひと』の前身となるWEBメディア・クリエイティブ組織を立ち上げ、様々なブランドのクリエイティブ、ブランディングプロジェクトを実施。2014年5月、雑誌『走るひと」創刊。
現在、ひととカルチャーに関わる領域にて様々な制作・メディア事業を手掛ける。
http://instagram.com/yuito_ueda
https://twitter.com/yuito_ueda
◎構成:望月美樹子
■「体育」ではなく「ライフスタイル」としてのランニング
上田:日本に「走るひと」というのはすごく多いんですね。トップアスリートもいるし、1970年くらいにジョギングブームがあって、マラソンをする中高年の方も大勢現れました。だけど、東京マラソンが2007年に始まって以降、それまでとは違うタイプの20代〜30代で走る人が増えてきたんです。
そこで雑誌『走るひと』では、今までの「ランナー」という言葉を使わずに「走るひと」という象徴的な言葉を使って、これまでの枠組みとは関係のない動機で走ってる人たちを大きく捉えて、その人たちがなぜ走っているのか、そこから文化として何が言えるのかを紹介しています。アーティストやタレント、モデル、文化人の方に話を聞いていくことで、新しい「走るひとのリアル」が見えてくるというのが、『走るひと』を始めた動機であり、作っている中での結果でもあります。
宇野:なるほど。よくわかります。
上田:走ることは身体を動かすということなので、東京オリンピックに向けて東京がどうなるのかについての関心は我々としてもすごく高かったんです。それでオリンピックにどう関わっていくかを考えていた時に『PLANETS vol.9』を拝見しました。そこで、どんなことをお考えなのかや、この本ができた経緯、見えてきた視点を伺えればというのが、今回取材をお願いさせていただいた経緯です。今ざっくりと、我々が見たランニングの市場の変化や様子をお話したんですけど、どんなことを思われましたか?
宇野:まず、僕自身のランニング経験から話しましょうか。震災前後くらいの半年間ですけど、一時期走ってたんですよ。時間のある時に自宅から新宿東口のヨドバシカメラまで走って、ミニカー1台買って帰ってきていました。ダイエットが目的だったんですけど、今は、事務所に電話して仕事しながらできるし、人と話しながら歩くのも楽しくてウォーキングに切り替えています。自営業だから細かい時間を取れるので、1日5キロとか7キロとか、時間があれば10キロくらい歩いてるんですよ。
僕はずっとマラソン大会を始めとする「走ること」が大嫌いでした。走ること自体も嫌いだったけど、「苦しさを我慢して肉体を痛めつけないと一人前にはなれない」というような、マッチョな世界観に基づいた体育会系なイデオロギーがものすごく嫌だったんですね。走ることが苦手な人も、体が弱い人もいるのに、そういうところを全然考慮せずに、あるタイプの運動を我慢してこなせないと「ちゃんとした」人間じゃない、という価値観が嫌で、スポーツ文化自体にどちらかというと苦手なものを感じていたんです。
でも、会社をやめて独立して少し経ったころかな、体重が80キロくらいになっていた時期があって、医者に「あんたこの数年ですごい太ってるから痩せなよ」と言われ、食生活を変えて運動も始めて20キロくらい痩せたんです。その時に友達から「最近ランニングが面白い」と言われたんですね。当時NIKE+がすごく流行ってる時期で、彼が言うには、自分の走っているスピードや消費カロリーが全部計測されるから、どうすれば速くなるかを考えながらゲーム的に走るのが面白いということだったんです。
それで、友達と一緒に新宿東南口のオッシュマンズに行って、ランニング用のウェアやグッズを一通り大人買いしました。僕は普段からジャージとかを着ている人間なんですよ。伊勢丹のメンズ館にある衣類よりも、オッシュマンズにある服の方がデザイン的に好きで。トレーニングウェアは普通にかっこいいし、ガジェット的にスペックにも萌えられるし、オタク的な感性にフィットするんですよね。そうやってグッズを身に付けて走ったらすごく楽しくて、それでハマりました。その流れで今でもウォーキングしています。
僕にとっては、というかいま大抵の人にとってはランニングもウォーキングもライフスタイルなんですよね。走るとゲーム的に面白いし、夜もぐっすり眠れて健康にも良い。だから僕は、スポーツというイデオロギーから切り離されて、より良いライフスタイルのひとつとして、走ることと出会い直した気がするんです。中高の友達と再会して、僕がランニングしているとか1日何キロも歩いているって言うと、「あの体を動かすことが嫌いな宇野が、180度転換してしまうとは」みたいな感じでびっくりされるんですよ。僕自身、ライフスタイルとしてのランニングに出会ったことで、身体を動かすことをすんなり受け入れて、しかもハマってしまったという体験をしているので、今おっしゃったったことはすごくわかります。僕としてはスポーツをしているという自意識があまりないですね。
上田:マラソンが嫌いだったのは、体育のマラソンということですよね。それは体育、要するに学校教育や社会制度のようなものを嫌悪するのと同じような感覚だったんですか?
宇野:言ってしまうと全体主義ですよね。ひとつの理想とする身体と精神があって、そこにどれだけ近いかによって、人間の価値がはかられることに抵抗がありました。体育教育やスポーツの歴史を見たら、近代スポーツがそういった全体主義と親和性が高いことは、誰の目にも明らかじゃないですか。歴史上、もっともスポーツを政治的に利用した人間はヒトラーですよね。それでずっと抵抗があったんですけど、自分の生活の中の楽しみというか、「走ること自体が楽しい」という観点から出会い直すことで、受け入れることができた。
上田:そういう意味で言うと、「スポーツ(sports)」という言葉の語源は「楽しみ」や「遊び」なんですよね。ただ、今の「スポーツ」という言葉が持つイメージは「体育」も含有していて、条件付きで使わないと誤解を与えてしまう可能性がある。
宇野:そうですね。僕自身がスポーツにコミットするときの考え方は二つあって、ひとつは「遊びとしてのスポーツ」をもう一回見直したいということ。今お話したように体育は、本来遊戯であるはずのスポーツを近代国家が政治化したものだと思うんです。もうひとつが、スポーツを通して、五体満足主義的で画一的な身体像を理想化するのではなくて、多様性につなげたい。これが、僕がこれからのスポーツに必要だと思っているテーマですね。
■スポーツに求められるのは「他人の物語」から「自分の物語」に
上田:遊びとしてのスポーツや多様性という要素は、『PLANETS vol.9』でのオルタナティブオリンピックプロジェクトの編集でも主軸とされたのですか?
宇野:ヒトラーのベルリンオリンピックをはじめ、ある時期から近代オリンピックは国家統合の手段として利用されてきた歴史がありますよね。そしてロサンゼルスオリンピック以降は、グローバルなテレビコンテンツとしての意味付けが大きくなっていった。どちらもバラバラのものを無理矢理ひとつにまとめる装置としてスポーツが使われてきたし、その背景には、画一的な身体観があると思うんです。僕自身は体育化した近代スポーツの持つ狭い人間観や窮屈さ、ある種の全体主義性にずっと抵抗を覚えていた人間なので、それには乗れなかった。だけど、実はそういう性質こそが、スポーツの楽しさや身体を動かす楽しみを失わせていたのではないか、というのは自分の経験から実感するんですよ。
それを踏まえて、スポーツが本来持っている多様性を取り戻すべきだと思ったんです。例えば開会式は、中心から周辺に拡散するテレビ的なモデルではなく、世界各地からインターネットを使って参加できる形式を提案しています。また、パラリンピックも非常に重視しました。オリンピックがある種の五体満足主義に基づいた近代スポーツ思想の代名詞なら、パラリンピックは「多様な身体」の象徴であるべきなんです。現代のパラリンピックは、障害の重度によってかなり恣意的に線を引いているけれど、この本ではプレイヤーの身体が画一的でないことを前提として、eスポーツやサイボーグ技術の分野の知見を総合しながら、多様性を活かせるゲームを再発明する方向に発想を切り替えています。
上田:いまのお話にあった多様性について、スポーツブランドの動きを見ていると面白いことがあるんです。今までサッカーや野球、バスケなどの競技にはスーパースターがいました。各ブランドはそのスターをサポートして、何十億というお金を払って広告塔にして、スターとブランドのイメージを重ねることで商品を売ってきたんです。ナイキもアディダスも「スターをいかに味方にするか」がマーケティングの始まりだったんですね。だけどランニングにおいては、その方法では一般のランナーには響かないことが分かってきて、スポーツブランドは今困っているんです。
宇野:なるほど。僕もナイキのランニングシューズを愛用していて、ウォーキング用にクッション性に優れたモデルを4、5足持ってます。中にはNIKEiDから取り寄せたオリジナルカラーもありますね。でも、現役のマラソン選手は一人も知らないです。これが今、起こってることのすべてで、大事なのは他人の物語ではなくて、自分の物語だということですよね。体育から遊戯やライフスタイルへとランニングが変わったときに必要とされているのは、自分の等身大の物語だと思うんです。僕は体育が嫌いだった頃もスポーツ観戦は嫌いではなくて、プロ野球ファンだったんです。それも、よりにもよって巨人ファンだった(笑)。でも今は、時間がないという事情もあるけど、スポーツ観戦は年に1、2度行くか行かないかで、自分で歩いている時間の方が圧倒的に長い。

京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第15回 ナデシコとウテナ――第三次アニメブームの風景(PLANETSアーカイブス)

京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第14回 ラブコメと架空年代記のはざまで――完全自殺マニュアルと地下鉄サリン事件(PLANETSアーカイブス)

京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第13回 教室に「転生戦士」たちがいた頃――「オカルト」ブームとオタク的想像力(PLANETSアーカイブス)

京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第10回 戦後ロボットアニメの「終わり」のはじまり(PLANETSアーカイブス)


京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 最終回 三次元化する想像力――情報化のなかで再起動するフューチャリズム【金曜日配信】

京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第26回 ノスタルジー化する音楽・映像産業――〈情報〉よりも〈体験〉が優位になった時代に【金曜日配信】

京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第25回 〈近さ〉から〈遠さ〉へ――48Gの停滞と坂道シリーズの台頭【金曜日配信】


京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第23回 〈メディアアイドル〉から〈ライブアイドル〉へ――情報環境の変化とAKB48のブレイク【金曜日配信】