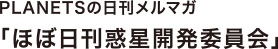履歴書に「?」を盛り込め!――超難関・オクスフォード入試を突破するために必要なこと(橘宏樹『現役官僚の滞英日記 オクスフォード編』第4回)
今朝のメルマガでは英国留学中の橘宏樹さんによる『現役官僚の滞英日記』をお届けします。今回のテーマは「オクスフォードの入り方」。独特の入学者選抜の在り方から、「徹底的な徒弟制」「完全主観主義採用」というオクスフォード流教育哲学の核心を読み解きます。
※本稿の内容(過去記事も含む)に関して、皆様からのご質問や、今後取材して欲しいことを受け付けたいと思います。こちらのフォームまたはTwitter(@ZESDA_NPO)にお寄せいただければ、できるかぎりお応えしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。橘です。関東、九州をはじめ各地の大雪のニュースに驚いていますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。オクスフォードも氷点下まで冷え込んでおります。朝、自転車に乗ろうとすると、サドルに霜が降りていて、硬いし冷たいし座れません。池や川にも氷が張っています。
最近は「オクスフォードの教育とは何か」について、つらつらと考えているこの連載ですが、前回は「ネオ・パターナリズム」と仮称しつつ、結論を出すことから逃げない姿勢を示す教師の指導スタイルについて論じました。
サンデル教授の「白熱教室スタイル」では足りない!? オクスフォード教育の本質は「ネオ・パターナリズム」にあり (橘宏樹『現役官僚の滞英日記:オクスフォード編』第3回)
今回は、制度としての側面、つまり組織・コミュニティ全体として、オクスフォードが教育というものをどのように捉えているか、ということについて、学生の選考方法という切り口から論じてみたいと思います。その上で日本人がオクスフォード(主に大学院)に入学するにはどうすればいいか、受験対策にも踏み込んで書いてみたいと思います。
いかにもキャッチーな表題で少し恥ずかしいのですが、「ドラゴン桜」でも描かれているように、入学試験の形式や選考方法を追究していくことは、その大学が求める学生像や教育哲学を理解する大きなヒントを与えてくれると考えます。
▲マンスフィールド・カレッジの図書室で勉強する学生。
▲パブでのイベント。オクスフォード大のJAZZクラブのメンバーが演奏しています。かなり上手!
「どういう学生がオクスフォードに合格するのか」「なぜ自分はオクスフォードに合格したのか」
様々な国籍の学生や教授らと話す機会を通じてそういったことを考えているうちに、文系・理系、修士課程・博士課程問わず、学生の選考は、ある一貫した「哲学」に基づいて行われているな、と思うに至りました。そしてこれは、ほとんど同じ種類の提出書類を要求し、カレッジ制度や少人数指導制を共有するケンブリッジ大学にもおそらく通底するものであるように思います(もともとケンブリッジ大学はオクスフォード大学から派生してできた学校です)。
オックス・ブリッジ(英国のエリートは多くがオクスフォードとケンブリッジから輩出されることから、この両校を併せて「オックス・ブリッジ」と呼びます)に合格するには、まずこの哲学をよく理解することが大事だと思います。そして、この哲学から当然導かれてくる要求内容をどのようにして満たすかを考えるのが、合格戦略であり、その具体的諸施策が合格戦術になってきます。
しかし、このようなアプローチが日本ではどこまで共有されているか、少し疑問に思います。というのも、僕が日本で受験準備をしていた頃、周りの人々は、「仕事や学業の傍らIELTSやTOEFLのスコアを上げるのに精一杯で、論文や研究計画には時間が割けず、どこかで入手したテンプレに沿って適当に書き、推薦状も頼みやすい上司に頼んで、締切ギリギリに提出して、間に合った!と安堵する。学歴の高い人は受かりやすいらしい。自分も運が良かったら通るかも。とにかくあとは祈るだけ」という考えの人が大半だったように思いました。これは、日本人の社会人留学のリアルそのものでもあると思います。しかし、このアプローチは、僕が仮説として持っている「オクスフォードの教育哲学」にはことごとく沿いません。
僕はほとんど同じリアルを共有しながらも、「オックス・ブリッジはこういう人が合格するはずだ」「僕が合格するにはこういう風にするしかない」という仮説・戦略をある程度立てて受験し合格しました。そして現在、オクスフォードには100人程の日本人が学んでいるようですが、飲み会などで色々話す中で、僕の戦略は一般的にもかなり正しそうだという感触を得るに至りました。
僕は、オクスフォードやケンブリッジに学ぶ日本人を増やしたいと思っています。この気持ちは必ずしも母校礼賛主義からのものではありません。オクスフォードには最先端があるだけではなく、800年かけて培われてきた「最先端を切り拓くチカラを養うノウハウ」があるからです。このノウハウを文化として身につけた人材は、どの分野でも必ずや世界の最先端で闘い続けていけると思います。
また、より正しい戦略がより広く理解されたならば、人口比という観点からも、ここで学ぶ日本人を増やすことができる余地も大きいように思います。「神は細部に宿る」と申しますし、オクスフォードの教育哲学に対する考察から始めつつ、ややテクニカルで具体的な戦術にまで踏み込んで、僕のオクスフォードへの合格戦略論をご紹介したいと思います。
▲ロンドンの高級デパート、セルフリッジでジャパンフードの催し。賑わっていました。
1.オクスフォードは「徒弟制の集合体」
オクスフォードの教育哲学は、一言で言うと、「教育は個人に施すものである。」というものです。つまり、Aさんの知性を育てるには、Aさんに合った方法に依らねばならない。Aさんに合った方法は、経験豊富な教師がじっくり丁寧に指導するなかで、教師が創造的に開発し適用していく、というものです。
教育方法は、十人十色、テイラー・メイドが当然です。ひとりひとりに合った教育には、もちろん試行錯誤も伴いますけれども、経験豊富な優れた教師であれば、試行錯誤のコストは少なくて済みます。
オクスフォードのこうした手法は、極めて贅沢な教育思想であるとも思います。もともと貴族の子弟を教育する機関だったので当然かもしれません。ですから、学生たちは「知識や技術を求める者が教わりにやって来る」というよりも、極論すると「さあ、名家の跡を継がなくてはならない私を偉大なエリートに育て上げてください」と育成されにやって来る、という感じがあります。
幼いアレクサンダー大王が、マケドニア貴族の子弟のためにアリストテレスが設立した「ミエザの学園」に放り込まれる感じに近いのです。よくオックス・ブリッジの教育の特徴は全人格的教育だ、と言われるのは、こういう点を指しているのだと思います。最先端の知見を日本に移植するべくやって来た、夏目漱石や森鴎外のような明治期の国費留学のセンスとは、根本的なすれ違いがあります。まるで、立派な雌鶏を育てているところに、卵をもらいに来るというような感じです。
しかし、日本の留学希望者達は、現代でもこの古いセンスを引きずっている方が多いように思われるのですが、どうでしょうか。
800年の歴史の中で、オクスフォード大学の規模は大きくなりました。カレッジの数も38個になりました。と同時に財政が厳しい時期も幾度となくありました。しかし、学生と教師の人数比は維持しています。教育の「効率化」は必死で拒絶し続けているのです(昨今設立されたMBAやMPP(公共政策大学院)など「稼ぎ頭」のコースは除きます……)。
なぜそうしたスタイルを堅持しているかというと、テイラー・メイド型教育こそが、オクスフォード教育の本質だという確信があるからでしょう。テイラー・メイド型教育を貫いたまま規模だけ拡大してきたこの大学の最小構成単位は、必然的に、徒弟関係であり続けています。そう、オクスフォードは、徒弟制の集合体なのです。オックス・ブリッジに入学するということは、学部やコース、クラスに所属するというよりも、特定の教授に弟子として採ってもらった、ということにほかならないのです。
そしてこれは、「決まった採点基準で採点された共通の試験で何点以上」というような客観的な評価基準をクリアしたから合格したわけでもないのです。弟子は「総合的で全人格的」な観点から選抜されます。「育ちの良さが見られる」というような意味ではありません(礼儀正しいかは厳しく見られると言われています)。入門したら「総合的で全人格的」な付き合いをすることになる教授が全権を委任されて判断する、ということです。
日本の研究者養成コースの大学院受験でも、指導教官への弟子入りという側面が強いところも多いように思いますが、いずれにせよ、イメージとしては、落語家の「弟子入り」に近い印象です。つまり、徒弟として入門するための受験対策は、師匠の個性に沿って計画されなくてはならない、ということを意味します。ですから、後にも述べますが、自分を受け入れてくれるような教授との出会いや、教授に自分を受け入れてもらえるようなアピールが大事になってくるのです。
▲クライストチャーチ・カレッジの壁面の蔦。夏は真っ青、秋は真っ赤でした。
2.「完全主観主義採用」とは
総合的で全人格的な観点から教授が選抜すると言いましたが、では、教授は何を基準に判断するのでしょうか。一言で言うと、「コイツを教えたいか」――つまり、教えたくなる何かを感じさせれば良い、ということであるようです。
オックス・ブリッジの教授職は、アカデミアにおいては世界最高に名誉ある地位であり、基本的には「アガリ」のポジションです。まだまだ追い求めるものがある研究者は、もっと研究費を貰える大学に引き抜かれていったりもしますが、余生はじっくりとエリート教育に取り組もう、と、椅子が自分の机よりも学生の方にしっかりと向いている教授が多く見受けられます。もちろん講師や准教授クラスは次のポストを求めてキャリアを形成しなくてはならないので、7割くらいは自分の机の方に体が向いている人も多いです。理系などでは同じ問題関心のバリバリの若手研究者とラボで最先端をともに歩みたい場合もあるかもしれませんが、学生たちは概して、全人格的教育を求めるからこそここに来ているわけで、同じ学費を収めているのであれば、なるべくシニアな教授クラスの指導を受けたがります。
入学選考ではまず書類選考があり、それに通るとスカイプ等での面接があります。面接では指導教官になる可能性のある教授や学部の責任者級の教授2~3名によって30分程度問答が行われます。面接に通れば最終合格です。書類選考を通るには、「コイツの顔を見てみたい」「とりあえず話を聞いてみたい」と思わせる何かが必要なようです。そして、面談においては、何らかの理由で、面接官の教授の1人以上に「私がコイツを教えてみたい」「あの先生ならコイツを教えたいと思うだろうな」と思わせることに成功することが目標になってきます。そのためには、当意即妙で鋭くて妥当でユニークな回答を、緊迫した中でも笑顔で魅力的に話すことが大事だと思われる方も多いでしょう。そのことを否定はしませんが、困難です。でも、事前に会ったことがあり、意気投合もした教授が、その面接の場に出てくるように仕向けることができたならば、尚良いですよね。
■「?」と「!」を積み重ねる
では、オクスフォード大教授はどういう受験生なら教えたいと思うか。端的に言うと「?」と「!」がある人だと思います。「?」とは、「なんでそんなことやってきたの?」「おもしろい」「謎」「一見、意味不明だけど価値は感じる」といった印象要素です。
「!」とは、「すごい」「意外」「驚嘆すべき美点アリ」です。大学時代の成績が良いとか、出版物があるとか、受賞経験があるとかのイメージで結構ですが、そこまでのものは必ずしも必要ありません。受験者の属性から想像される普通の人物像に比したとき「!」と「?」を抱かせればよいのです。
例えば僕であれば、「普通の日本人の官僚だったら普通は推薦状は課長からなのに、こいつは『!』な人から貰ってるなあ」「そして履歴書のここは『?』だなあ。とりあえず話してはみたいかもな」という風に思ってもらえるように、提出書類を工夫するわけです。そして、抱かせておいた「?」に対する答えを二次の面接で回答することで、それも「!」に変えて、「なるほど。おもしろい。うん。教えてもいい」と思ってもらうことを狙うのです。より具体的には後半の受験対策のところで詳述します。
■ オクスフォードの学生たちから立ち上る「獅子のオーラ」
加えて、いい歳の社会人として役所の採用にも何年も携わっており、一応修士号を2つ持っている「上から目線」で20代半ばのクラスメイト達を傍から見ていると、何となく、教授がこの子らを採用した理由がわかるなぁと思う時があります。例えば、ただ笑顔で人の話に頷いている様子を見ているだけでも、この瞬間にかなり高度で深い理解を進めたな、という印象を受けます。のびしろが実力に変わる時の轟(ごう)という勢いといいますか、「わかったぞ!! 覚えたぞ!! 思いついたぞ!!」ということだけである種の圧を人に与えるチカラ、喉奥で唸りを転がす若獅子のオーラのようなものが背中に立ち上っているのが見えるような若者が多いように感じます。その上、とても素直で可愛らしいのです。「そりゃあ、おじいちゃん、おばあちゃん達、教えたくなるよなあ」という子達ばかりです。
ちなみに、LSEの同級生たちのクレバーさにも、もちろん目を見張るものがありましたが、ものすごく頭の回転も速くて賢いけれど、根本的に学問だの理論だのという話には気乗りしないビジネスエリートたちの知性、というものだったかもしれません。
若獅子の圧力というより、「あー、はいはい。わかったわかった。」「さもありなん。ふふん。」というような、軽さと爽やかさとキレを備えた食えない奴ら――言うなれば誇り高き狐のような連中だったように思います(ちなみに、LSEのマスコットはビーバーですが)。
無論、限られた人数の友人たちに抱く感覚論に過ぎませんけれど、同じように多国籍な学校なのに少し校風を描写しようとすると、そういう雰囲気の違いはあるかなと思います。
こうして教授らは、自分が教えたくて採った学生を、当然のように手塩にかけて丁寧に育てることになります。自分が見込んだ人物なのだから、立派に育てなければならないし、育つはずだという自負もありましょう。義務や責任も当然ありますが、それを上回る愛情も伴うことになります。そして師の愛情に感謝し、応えようと弟子も頑張る。ここが徒弟制の良いところだと思います。
そして、ちゃんと育てているかどうかは、カレッジや学部がつぶさに管理する制度が充実しています。問題があれば指導教官も換えられます。学生たちは何重もの視線に見守られているのです。
しかし、客観主義採用と同様に、完全主観主義採用にも、もちろん失敗があります。修士課程に入れても学業を怠ったり、修了の見込みが立たない学生もいます。そういう場合はなるべく中退させたりせず、教授が判断して除籍にします。大学・学部としても、教授の評価基準として、卒業率をチェックしているからです。
▲オクスフォードのヘディントン地区、屋根にサメが突っ込むユニークなオブジェ。「ヘディントン・シャーク」





ブリティッシュ・ドリームの叶え方――英国版「わらしべ長者」と3つのキャピタリズム(橘宏樹『現役官僚の滞英日記 オクスフォード編』第10回)【毎月第2水曜配信】

エリートの自滅――問われるコミュニティブ・リーダーシップの真価(橘宏樹『現役官僚の滞英日記:オクスフォード編』第9回)【毎月第1木曜日配信】


Brexit(英国EU離脱)国民投票2016――読めない行方の読み解き方(橘宏樹『現役官僚の滞英日記 オクスフォード編』第8回)【毎月第1木曜配信】


「英国型プラットフォーム」と2つのキャピタリズム――「プロデュース理論」で比較する日英のイノベーション環境(橘宏樹『現役官僚の滞英日記 オクスフォード編』第6回)