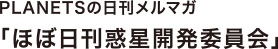大見崇晴『イメージの世界へ 村上春樹と三島由紀夫』序章 世界の終わりとイメージの世界で
今朝のメルマガでは大見崇晴さんの新連載『イメージの世界へ 村上春樹と三島由紀夫』第1回をお届けします。1970年に三島由紀夫が遺作『豊饒の海』で設定し、2012年に村上春樹が『1Q84』で克服しようとした「終わり」とは何なのか。序章では、三島の戦後の足跡を辿りながら、終生抱え続けていた虚無について論じます。
「旗は汚らしい風景をめざし、おれたちの田舎ことばが太鼓の音をかき消す。
「都市という都市で、破廉恥きわまりない売春をはびこらせてやろう。理詰めの反抗などは踏みつぶしてやろう。
「胡椒まみれで水浸しになった国々へ!――産業上の、あるいは軍事上の、極悪非道の開発に仕えるために。
「別れをいおう、ここで、いやどこででも。この熱意のために駆り出された新兵であるおれたちは、情容赦のない哲学を身につけるだろう。科学にかけては無知蒙昧、安逸にかけては放埒三昧。こんな世界など吹っ飛んじまえ。これこそ、ほんものの前進だ。前へー、進め!」
――アルチュール・ランボー「民主主義」
イリュージョニズム;錯視法 Illusionism
美術が錯視によって成立するのは、人為的なものを本物と思い込ませようとするからである。壁に掛かった風景画がまったく本物の風景となる。教会堂のドームに描かれた像が鑑賞者にとっては特別に観ることを許された天界の光景の一部となる。肖像が実際に呼吸する。あるいは、徒弟である画家が親方の作品の中に描き、親方が塗り消そうとする一匹のハエは、本物である。一房のブドウがあまりにも真に迫っているので、小鳥がついばもうとする。
――ポール・デューロ、マイケル・グリーンハルシュ『美術の辞典』
序章 世界の終わりとイメージの世界で
私には祖父が二人いた。それは比較的当然のことだった。近親婚でない限り、大抵祖父は二人いるものだ。
どちらの祖父も長生きだった。一人は父方の祖父で私が幼稚園児から小学生に上がるか否かの時期に亡くなった。もう一人は母方の祖父で、こちらはつい最近まで生きていた。若いころはフィリピンに出征して生き残った。
文壇の天皇とのちに呼ばれた作家・大岡昇平もフィリピンに派遣されていた。大岡昇平の代表作である『野火』や『俘虜記』、『レイテ戦記』といった小説は、彼自身の兵隊経験を題材とし、それを資料によって補い拡張したしたものとして知られている。おそらく母方の祖父は、大岡によって、数多くの兵士と同様に資料によって数字や文字として記録されたもの、小説の素材として処理されたのだろう。
今では戦地においても使用されないが、第二次大戦中、兵隊の脚に巻きつける包帯のようなものがあった。これは脚絆(ゲートル)と呼ばれる。足の疲労や外傷を防ぐために利用された。南方戦線(フィリピン)に出向いた兵士の脚にも脚絆は巻かれた。だが、学歴も知識も無い兵士の多くはその利用価値をよく知らなかった。脚絆の巻き方は自然と緩いものとなり、シラミや蚊を媒介にした感染症を防ぐ役割を捨て、むしろ害虫の温床ともなった。多くの兵隊がそのようにして疾病にかかり命を落とした。さる大物政治家の秘書を務めた人物から、私は第二次世界大戦の一挿話としてそのように教えられた。その人物は南方戦線の生き残りだった。戦中からエリートとして生きてきた。戦地から日本に戻ると複数の官庁から暴力団まで引く手数多だった。エリートの殆どが戦争で死んでいたからだ。だから大物政治家の秘書を勤めることになった。
母方の祖父は単なる一兵卒として日本に戻ってきた。戦地でマラリアに罹患したから、もしかしたら脚絆の役割など知らない兵士の一人だったのかもしれない。
私が祖父がマラリア持ちだと知ったのは妹が生まれる時だった。母の出産に伴って場合によっては輸血が必要になると医者から話を持ちかけられたのだが、母と同じ血液型だった祖父はマラリア持ちなので輸血が不可能だったのだ。一九八〇年代のことだった。あのころは「敗戦」がふとした瞬間に顔を覗かせることがちらほらとあった。県庁があるような街を歩けば傷痍軍人が目に入った時代だった。
二〇一四年に祖父は亡くなった。小柄ながら骨は太く、骨壷に納めるのが難しかった。幾つかの部位の骨に関しては砕いてから骨壷に納めた。亡くなる寸前まで祖父は頗る元気だった。よく肉を食べた。ステーキや焼肉、鰻のような脂が乗ったものを愛好していた。死の直前に鮭を食べたがったことに家族は驚いた。脂が乗っている魚よりも肉を食べ続けていたのに。もしかしたら歳のせいもあるんじゃないか。そんなことを話し合っているうちに間もなくして天に召されてしまった。
祖父は生涯戦争のことは一切語らなかった。戦地のことが話題になるように水を向けるととぼけたような顔をして、それから読売巨人軍のことしか口にしてくれなかった。ごく稀に戦地で世話になった人物の名前を時折思い出すように口にすることはあった。だが問い質しても具体的に何の世話になったか親族に明かすことは無かった。家族も問うてはならないと思った。
祖父の生涯を振り返ると、私は一人の人物を思い出す。三島由紀夫である。
この作家は祖父と対照的だった。祖父との共通点と言えば好んで牛肉を食べたことぐらいだ。戦地について語ることがない祖父とは反対に、死や武士道について余りにも饒舌だった。
三島は南方戦線に出兵するはずだった。三島と戦友になるはずだった兵士たちは、その殆どがフィリピンで死んだ。戦死することを覚悟しながら、三島由紀夫は出兵前に高熱を患い戦地に赴かなかった。もし三島が戦地に出征し、生き延びていれば祖父や大岡昇平といった俘虜達と肩を並べていたかもしれない。だが、三島は高熱を発症し、戦地へ赴くこともなく日本で終戦を迎えた。
三島由紀夫は死ぬこともなく、俘虜になることもなかった。
高熱が引いたあとの三島は、戦争の終わりを、この世の【終わり】を、待ち望んでいた。
▼プロフィール
大見崇晴(おおみ・たかはる)
1978年生まれ。國學院大学文学部卒(日本文学専攻)。サラリーマンとして働くかたわら日曜ジャーナリスト/文藝評論家として活動、カルチャー総合誌「PLANETS」の創刊にも参加。戦後文学史の再検討とテレビメディアの変容を追っている。著書に『「テレビリアリティ」の時代』(大和書房、2013年)がある。