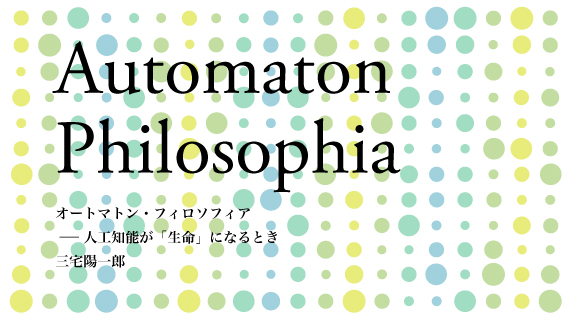
三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第零章 人工知能を巡る夢【不定期配信】
ゲームAIの開発者である三宅陽一郎さんが、日本的想像力に基づいた新しい人工知能のあり方を論じる『オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき』。人工知能はいかにして誕生したのか。その背景となった西欧世界における医学・工学・哲学の発展史を踏まえつつ、人工知能と東洋的思想との接続の可能性について考えます。
1. 知能とは何か?
「知能とは何か?」という問いは人間の最も深淵な問いである。しかし、この問いを思索のみから探求することはできない。この問いの答えを得るためには、思索し、行動し、仮説を立て、実験し、実際に作ってみて、再び反省する、という哲学、科学(サイエンス)、工学(エンジニアリング)の絶え間ない連携した活動が必要である。それが人工知能という試みである。
この連載の出発点として、目指すべきところをあらかじめ明確にしておきたいと思う。この連載は全十回に渡って「知能とは何か?」を探求する。その方向は3つである。一つは「知能を解明する」という純粋なサイエンスの探求、一つは「知能を作る」というエンジニアリングの探求、一つは「知能とは何か?」を探求する思弁的探求である。この3つの探求を同時に行うというのが、人文科学、自然科学、哲学を横断する「知能学」そのものの姿である、この3つを少し詳しく見ていこう。

図 人工知能をめぐる活動
2. 3つの探求のクロスロード
「知能とは何か?」という問いは哲学的な思弁の深淵へ向かって軌道が伸びている一方で、実際に知能を作り出そうとするエンジニアリングの可能性の平野が広がっている。また作ることで知るのがエンジニアリングなら、知るために分解して行くのがサイエンスである。知能を知ろうというサイエンスは、多面的なサイエンスであり、一つの分野の形を取らず心理学、精神医学、生物学を横断している。また社会学、人類学、あらゆる人文科学は、「知能とは何か?」という問いの周りに展開された科学である。これが知能を巡る学問「知能学」の持つ地平である。
人工知能を生み出す人間の欲求は、科学、工学、哲学の3つの衝動に起因している。
科学的衝動 「人間や動物の知能を分解して理論を作りたい」
工学的衝動 「人工知能を作り出し、実際に世の中を変革したい」
哲学的衝動 「知能と人工知能の探求から、生きている意味を解明したい」
人工知能に関わる人々がこのような欲求を持つのは、人工知能が人間から独立した対象として生み出す機械やソフトウェアと異なる傾向があるからである。知能とは我々自身であると同時に、探求し作り出す対象である。この単純な事実が、通常の科学と人工知能の探求の様相を大きく異なるものにする。

図 人工知能をめぐる3つの欲求
我々は知能を内側から生きている存在である。人間という(自然)知能が(人工)知能を作り出そうとするというトートロジーの中に「人工知能」の開発の運動はある。人工知能を作ろうとする者にとって、知能は対象であると同時に、我々自身をもう一度作り出そうとする「鏡像構造創造的な体験」である。常に自己を見つめつつ、その写し姿を電子回路の中に掘り起こして行く。そこで人工知能という分野は、知能を対象化することでサイエンスとなり、 自らを探求するという意味で哲学的となり、それを作り出そうとする意味で工学的となるのである。
3. 知能感受性
知能には知能を感じ取る力がある。これを私は知能感受性と呼ぶ。知能を感じ取る力、この人はこんな知能があるな、この熊はこんな知能を持っているな、このキャラクターはこれぐらいの知能を持っているな、という総合的に知能を感じ取る力である。誰もが持っている力だが、適切な言葉がないので、こう呼ぶことにする。ゲームAI開発の現場で私が作り出した言葉である。ユーザーにこのキャラクターをどんなふうに知能として感じてほしいか、という点を実現することにデジタルゲームのAI開発は終始すると言って良い。
知能感受性は五感を基にするが、より高次の総合的な感覚である。知能は知能に対して厳格である。動物にせよ、生物にせよ、相手の知能を感じ取ることは自分の生存に切実に関わる問題だからである。初めて会った相手に、森で出会う動物に、敵に、どのような知能を感じ取るということで、動物は行動を決定するのである。
この鋭敏過ぎる感覚は時にあらゆるものに知能を見出すことになる。風に、森に、川に、あらゆる森羅万象に知能を感じ取る。あらゆるものに知能を見出すのが森の文化であり、所謂「八百万の神」感であり、あらゆる生命を横のつながりの中で捉える感覚である。一方で、砂漠の文化とは、極めて対象化され序列化された文化である。人工知能でいえば「神―人間―機械」という縦の知能の序列を与えることである。便宜上、前者の森の文化を東洋的、後者の砂漠の文化を西洋的と本書では呼ぶことにする。
4. 擬人化・自動化・知能化
「擬人化」という言葉がある。世界の中でいろいろなものを人に見立てて、話かけたり聴き入ったりすることだ。人は人の似姿を求める。ファンタジーや神話ではいろいろなものが人の似姿を取る。コンピュータが出現する以前から、人は自らの知能と良く似たものを作り出したいという欲求を持っていたのである。
一方で「自動化」という思想がある。人間の代わりに肉体労働・知能労働を「自動化する」という思想である。そういった欲求は当初は産業革命で「自動化」(オートメーション)という形で明確化され広められた。まずは身体の「自動化」がなされ、たくさんの機械たちが人間の代わりに力仕事を、ロボットは物理的な組み立ての仕事をするようになった。しかし、その本質的延長として人間の頭脳の中の活動も、同じ動力で再現できたら、というアイデアがあったことだろう。「フランケンシュタイン」(メアリー・シェリー、1818年)、「R.U.R.」(ロボットの語源、カレル・チャペック、1920年)、が書かれたのも、そんな産業革命以来の「自動化」の流れの中であった。
また「知能化」という概念がある。これは現在に第三次AIブームと呼ばれている2010年来の潮流の中で「ディープラーニング」と並ぶ最も大きな特徴である。「知能化」とは、ロボットやゲームキャラクターのように、一つの新しい知能をまるごと生み出す、のではなく、既にあるものに知能を付与する、というアプローチである。ドアに知能を付け登録した顔の人にのみ開く、デジタルサイネージ(電子ポスター)にカメラを付け前に立った人物を認識して広告を変える、自動車に知能をつけて自動運転をさせる、家電に知能をつけて入れたものを判定して自動的に食料や調理をアレンジする、などがそうだ。このように「知能化」によって、現実を変革していくというのが「知能化」である。
人工知能はこの「擬人化・自動化・知能化」の3つを内包しており、「エージェント化、オートメーション、インテリジェンス化(スマート化)」と呼ばれる。それぞれの背景には、錯綜した人間の人工知能への欲求が隠れている。
noteで読む >>
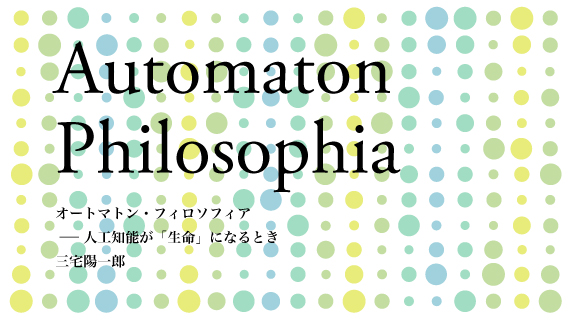
三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア──人工知能が「生命」になるとき〈リニューアル配信〉 第六章 人工知能とオートメーション(自動化)
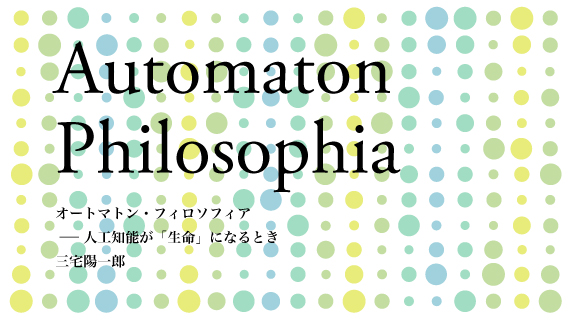
三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア──人工知能が「生命」になるとき〈リニューアル配信〉第五章 人工知能が人間を理解する
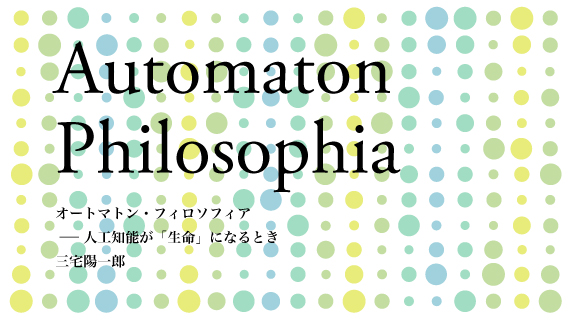
三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第十章 人と人工知能の未来 -人間拡張と人工知能-(後編)
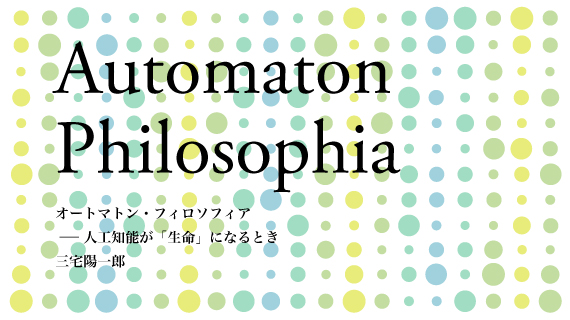
三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第十章 人と人工知能の未来 -人間拡張と人工知能-(前編)
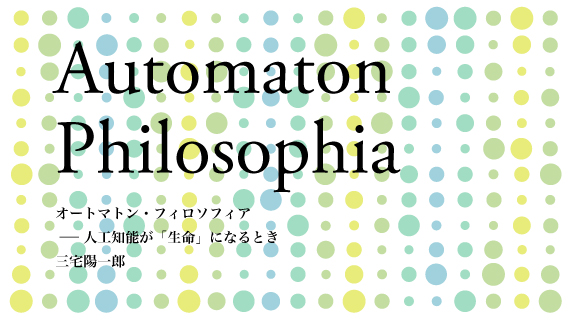
三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第九章 社会の骨格としてのマルチエージェント(後編)
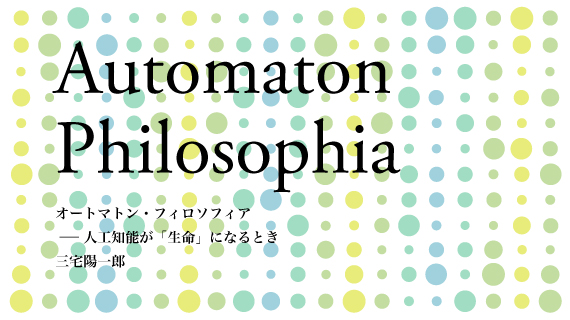
三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第九章 社会の骨格としてのマルチエージェント(前編)
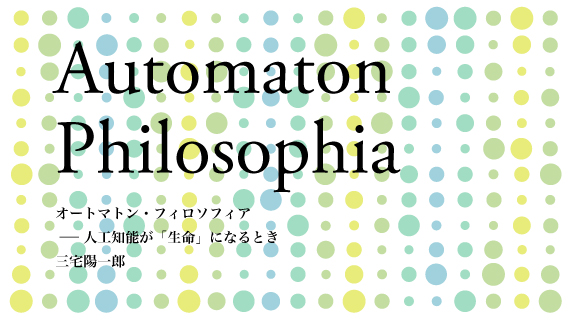
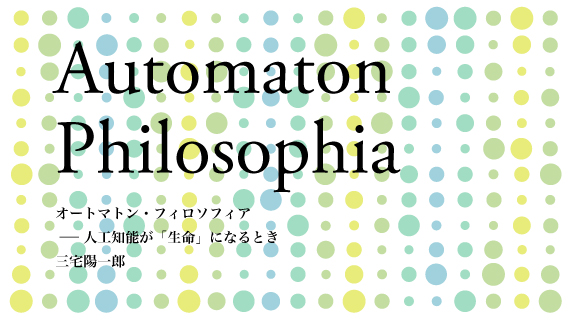
Daily PLANETS 三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第八章 人工知能にとっての言葉(前編)
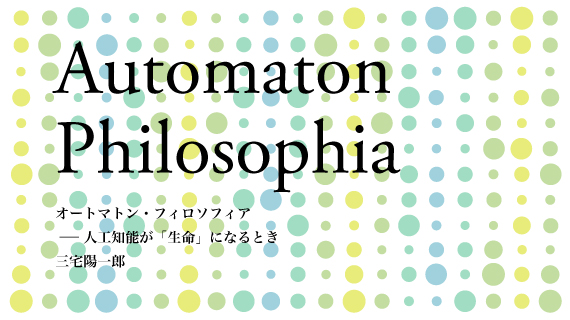
三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第七章 街、都市、スマートシティ【不定期配信】
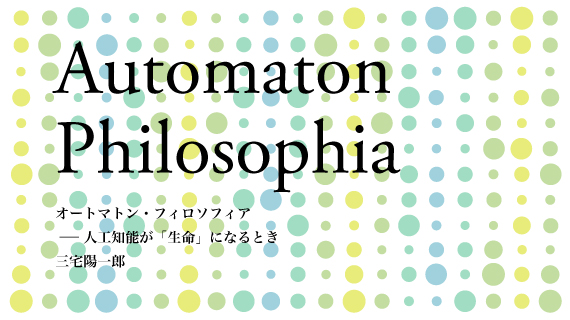
三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア――人工知能が「生命」になるとき 第六章 キャラクター認識論・感情論【不定期配信】








![ゲームとゲーミフィケーションのあいだで 〈人間と情報〉の関係はいかに更新されてきたか[Kindle版]](http://wakusei2nd.com/wp-content/uploads/2015/09/71CHwEZ-d1L._SL1500_.jpg)







